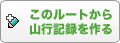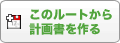HOME > ルートWiki
大富山(高倉山経由)
| 日程 |
日帰り  往復/周回ルート 往復/周回ルート |
|---|---|
| エリア | 東北 |
| ジャンル | 積雪期ピークハント/縦走 |
| 技術レベル |
    4/5
※技術レベルの目安
4/5
※技術レベルの目安
|
| 体力レベル |
   3/5
※体力レベルの目安
3/5
※体力レベルの目安
|
| 見どころ |
 眺望あり 眺望あり |
| 距離/時間
[注意] |
 水平移動距離: 5.49km
水平移動距離: 5.49km
 最高点の標高: 998m
最高点の標高: 998m
 最低点の標高: 479m
最低点の標高: 479m
 累積標高(登り): 665m
累積標高(登り): 665m
 累積標高(下り): 652m
累積標高(下り): 652m
|
| アクセス |
車・バイク |
ルート説明:
国道48号線を作並温泉から山形に向かって走るとき、いつも気になるのがこの道の北側に並び立つ“名もなき”山々である。このあたり、関山峠から寒風山を経て粟畑に至る稜線に一般ルートがある以外、地図には登山道は記されておらず、それどころか山名の記載すらない。そのためここは、私自身の山行空白地帯となっている。今春は念願の六方山、川音岳、新川岳の登頂を果たして、いよいよこの作並の北に広がる不思議の山に意識が向かい始めた。そこで調べてみると、この地には大倉五岳と称される山があり、その最高峰は大富山、1024メートル峰ということであった。かつて車で定義から熊沢林道というスリルあふれる道を作並に抜けたことがあり、大倉五岳とはその辺りだな、と一応わかった気になる。日頃、私が頼りにしている「東北の山遊び」というブログに、2月末に大富山に登ったというSONEさんの記事を見つけて、そのルートをまずはトレースしてみることにした。従ってここに報告する記事はルート的には新奇性がない。それでも公開することにしたのは、融雪進む4月の藪と雪の按配を知りたい方々に、多少はお役にたつのでは、と考えたためである。
そこで、SONEさん記事に従い、十里平の最奥に車を置いて、8時40分、行動を開始する。道路の西側の杉林を抜けて十里平の背後に伸びる低い尾根の裾につく。斜面の傾斜の緩いところを選び、稜線を目指して登る。雑木林から杉の植林となり、林の切れ間から仙台カゴのピラミッドが遠望される。そして稜線に達すると再び雑木林となるが、どこにも道型はない。獣道の一本もない山というのも珍しい。結局、今日の全行程を通じ、全く道はなく、人の気配の全くないところであった。取りつきから終始、藪にルートを探るが、幸い篠竹はさして密でもなく、丈も低めである。十里平の裏の稜線を右手に進んでいくが、このあたり起伏が乏しいため主稜の見定めが難しく、しかも支尾根が複雑に分岐しているので、登りはともかく下りに際しては慎重にルートを確認する必要がある。
まもなくすると稜線らしくなり、右手には消え残った雪だまりが点々と続くようになる。林もブナやカラマツが目立ってくる。左手には中腹に真一文字に林道の走る綱取山が、意外に多くの雪を残して大きい。これから登る高倉山の山頂直下まで、この綱取山を眺めつつ進む。しばらく稜線らしい地形をしていたのが、突如尾根は消え、かわって丸く盛り上がった高倉山の側面にぶち当たる。挑戦状を突きつけるかのようなこの急斜面を、篠竹や木の幹を掴みながら、度々ずり落ちる自分の体を立て直して一気に登る。それにしてもここの笹はぶっといな。あと一か月すれば、超立派なタケノコがとれるかも! と想像するが、よく考えればその頃には猛烈な藪になっていて近づけないだろう。それに、もうこれだけブヨが出ているのだから、たとえ藪を制覇したとしても、その時には想像を絶するブヨとの戦いとなるに違いない。ふと横を見ると、綱取山が低く見える。先ほどまで綱取山の林道と同じ高さになかなか達しないことをじれったく思っていたのだが、この急登のお蔭で一直線に走るあの林道の高さをあっという間に越えて、ぐいぐいと高度を稼いでいた。そして見上げると、すっかり角の取れた雪庇の名残が、急峻な傾斜をもって山頂直下を埋めている。固い雪を数回ずつキックしてステップを切り、登りきる。目前に山頂があるが、そこで目にしたものは、壮絶な篠竹の密藪! でかいタケノコの夢を与えてくれたあの猛々しいネマガリダケが、ぎっしりと稜線を埋め尽くしている。今日はここが終点になるのかもしれない、と少々弱気になる。しかし、高倉山のいただき(981m)だけは倒木のお蔭で空間があいており、ここで昼飯とする。何故か、あの疎ましいブヨが山頂では消えた。篠竹の上から周りを見回すと、周囲は雪を頂いた兄貴分の立派な山々がそびえている。見慣れないアングルの為、山座同定は断念。左手のお隣さんは、綱取山だね、と私が言うと、同行のKINUASAは、いや、ここにきて初めて見えた山だという。あれっと、目をきた方角に動かすと、確かに本物の綱取山がそこにあった。この「新しい山」こそ、今日の目的地、大富山であった。それにしても、ものすごい密藪の中を、果たしてあそこまで行けるのだろうか。
昼飯もそこそこに、大富山へ向かうことにする。地図上では、登ってきた方角の延長線上に大富山があるように見えるが、実際には高倉山の山頂から左に直角に折れるように進むことになる。「藪漕ぎに不可能の言葉はない」を座右の銘とする私も、さすがにこの密藪にひるんだ。幸い、丸まった山頂直下の雪庇が、行く手の西尾根に沿って残っている。まずはこれを辿る。しかし、この雪庇跡はほんの百メートル程度しか続かない。覚悟を決めて稜線に突っ込む。「あれっ」、藪がいきなり薄くなっている! それどころか、土が露わとなって点々とカタクリが咲いているではないか! これ幸いに尾根を下る。途中で再び篠竹の藪となるが、それもつかの間、高倉山と大富山の鞍部に出る。大富山側には雪がかなり残っているので、ここでアイゼンを装着する。木々の間から、仙台カゴ、最上カゴが大きくそびえたって見える。アイゼンを効かせてサクサクと登る。どんどん視界が開け、背後にゆったりと船形山が雪をまとって優美な姿で横たわる。仙台カゴ、最上カゴの岩峰の左になだらかな山容で半身雪をまとった姿を見せるのは白髪山であろう。
一歩登るごとに大パノラマは刻々と山々の威容を変化させ、圧倒する。やがて、林道跡を横切る。雪に覆われた林道の路面からは灌木が顔を覗かせ、夏場なら車はおろか、人の通行すら困難であろうことが容易に推察される。さて、ここから大富山の山頂に向かって、稜線は篠竹の密藪である。そこで、雪がまだ残っている北側斜面に回り込みながら、残雪を頼りに登り続ける。最初のピークの左を巻き込むようにして雪庇上を進み、十里平から実質歩行3時間半(休憩等を含まず)で、大富山の最高点に達した。ここまで来ると左側の眺望も開け、大東岳、南面白山が雪に覆われて勇壮な姿を誇示している。大富山山頂は、北に船形連山、南に二口の山々を見渡す絶景地であった。ブナの大木に守られた静かなこの山の息遣いに、心洗われるひと時を過ごした。薄い黄色の毛に包まれたテン?が藪から雪面に飛び出してきて、我々に気付くや否や、慌ててまた藪に戻っていった。
帰路は、忠実に来たルートを戻った。ただし、十里平の裏尾根に入るところで、やはり一度、ルートを外してしまい、10メートルほど戻って正しい方角に修正する破目になった。だだっ広い尾根での方角の把握には十分注意されたい。
結論としては、この山は4月上旬までに登らないと、雪が消えて藪また藪の試練となるということである。時期をうまく選べば、最上級の里山歩きを満喫できる。
この記事は、ASAKINUが記載し、同行のKINUASAがアップしています。
そこで、SONEさん記事に従い、十里平の最奥に車を置いて、8時40分、行動を開始する。道路の西側の杉林を抜けて十里平の背後に伸びる低い尾根の裾につく。斜面の傾斜の緩いところを選び、稜線を目指して登る。雑木林から杉の植林となり、林の切れ間から仙台カゴのピラミッドが遠望される。そして稜線に達すると再び雑木林となるが、どこにも道型はない。獣道の一本もない山というのも珍しい。結局、今日の全行程を通じ、全く道はなく、人の気配の全くないところであった。取りつきから終始、藪にルートを探るが、幸い篠竹はさして密でもなく、丈も低めである。十里平の裏の稜線を右手に進んでいくが、このあたり起伏が乏しいため主稜の見定めが難しく、しかも支尾根が複雑に分岐しているので、登りはともかく下りに際しては慎重にルートを確認する必要がある。
まもなくすると稜線らしくなり、右手には消え残った雪だまりが点々と続くようになる。林もブナやカラマツが目立ってくる。左手には中腹に真一文字に林道の走る綱取山が、意外に多くの雪を残して大きい。これから登る高倉山の山頂直下まで、この綱取山を眺めつつ進む。しばらく稜線らしい地形をしていたのが、突如尾根は消え、かわって丸く盛り上がった高倉山の側面にぶち当たる。挑戦状を突きつけるかのようなこの急斜面を、篠竹や木の幹を掴みながら、度々ずり落ちる自分の体を立て直して一気に登る。それにしてもここの笹はぶっといな。あと一か月すれば、超立派なタケノコがとれるかも! と想像するが、よく考えればその頃には猛烈な藪になっていて近づけないだろう。それに、もうこれだけブヨが出ているのだから、たとえ藪を制覇したとしても、その時には想像を絶するブヨとの戦いとなるに違いない。ふと横を見ると、綱取山が低く見える。先ほどまで綱取山の林道と同じ高さになかなか達しないことをじれったく思っていたのだが、この急登のお蔭で一直線に走るあの林道の高さをあっという間に越えて、ぐいぐいと高度を稼いでいた。そして見上げると、すっかり角の取れた雪庇の名残が、急峻な傾斜をもって山頂直下を埋めている。固い雪を数回ずつキックしてステップを切り、登りきる。目前に山頂があるが、そこで目にしたものは、壮絶な篠竹の密藪! でかいタケノコの夢を与えてくれたあの猛々しいネマガリダケが、ぎっしりと稜線を埋め尽くしている。今日はここが終点になるのかもしれない、と少々弱気になる。しかし、高倉山のいただき(981m)だけは倒木のお蔭で空間があいており、ここで昼飯とする。何故か、あの疎ましいブヨが山頂では消えた。篠竹の上から周りを見回すと、周囲は雪を頂いた兄貴分の立派な山々がそびえている。見慣れないアングルの為、山座同定は断念。左手のお隣さんは、綱取山だね、と私が言うと、同行のKINUASAは、いや、ここにきて初めて見えた山だという。あれっと、目をきた方角に動かすと、確かに本物の綱取山がそこにあった。この「新しい山」こそ、今日の目的地、大富山であった。それにしても、ものすごい密藪の中を、果たしてあそこまで行けるのだろうか。
昼飯もそこそこに、大富山へ向かうことにする。地図上では、登ってきた方角の延長線上に大富山があるように見えるが、実際には高倉山の山頂から左に直角に折れるように進むことになる。「藪漕ぎに不可能の言葉はない」を座右の銘とする私も、さすがにこの密藪にひるんだ。幸い、丸まった山頂直下の雪庇が、行く手の西尾根に沿って残っている。まずはこれを辿る。しかし、この雪庇跡はほんの百メートル程度しか続かない。覚悟を決めて稜線に突っ込む。「あれっ」、藪がいきなり薄くなっている! それどころか、土が露わとなって点々とカタクリが咲いているではないか! これ幸いに尾根を下る。途中で再び篠竹の藪となるが、それもつかの間、高倉山と大富山の鞍部に出る。大富山側には雪がかなり残っているので、ここでアイゼンを装着する。木々の間から、仙台カゴ、最上カゴが大きくそびえたって見える。アイゼンを効かせてサクサクと登る。どんどん視界が開け、背後にゆったりと船形山が雪をまとって優美な姿で横たわる。仙台カゴ、最上カゴの岩峰の左になだらかな山容で半身雪をまとった姿を見せるのは白髪山であろう。
一歩登るごとに大パノラマは刻々と山々の威容を変化させ、圧倒する。やがて、林道跡を横切る。雪に覆われた林道の路面からは灌木が顔を覗かせ、夏場なら車はおろか、人の通行すら困難であろうことが容易に推察される。さて、ここから大富山の山頂に向かって、稜線は篠竹の密藪である。そこで、雪がまだ残っている北側斜面に回り込みながら、残雪を頼りに登り続ける。最初のピークの左を巻き込むようにして雪庇上を進み、十里平から実質歩行3時間半(休憩等を含まず)で、大富山の最高点に達した。ここまで来ると左側の眺望も開け、大東岳、南面白山が雪に覆われて勇壮な姿を誇示している。大富山山頂は、北に船形連山、南に二口の山々を見渡す絶景地であった。ブナの大木に守られた静かなこの山の息遣いに、心洗われるひと時を過ごした。薄い黄色の毛に包まれたテン?が藪から雪面に飛び出してきて、我々に気付くや否や、慌ててまた藪に戻っていった。
帰路は、忠実に来たルートを戻った。ただし、十里平の裏尾根に入るところで、やはり一度、ルートを外してしまい、10メートルほど戻って正しい方角に修正する破目になった。だだっ広い尾根での方角の把握には十分注意されたい。
結論としては、この山は4月上旬までに登らないと、雪が消えて藪また藪の試練となるということである。時期をうまく選べば、最上級の里山歩きを満喫できる。
この記事は、ASAKINUが記載し、同行のKINUASAがアップしています。
ルート詳細
1.
Start
2.
End
お気に入りした人
人