 今日は二宮駅から旧東海道を辿って湯本位迄行って見ようと思います。駅前の「ガラスのうさぎ」像です
今日は二宮駅から旧東海道を辿って湯本位迄行って見ようと思います。駅前の「ガラスのうさぎ」像です
 2
2
4/18 8:04
今日は二宮駅から旧東海道を辿って湯本位迄行って見ようと思います。駅前の「ガラスのうさぎ」像です
 1国を歩き出すと、右手に吾妻山を見ながら進みます。
1国を歩き出すと、右手に吾妻山を見ながら進みます。
 1
1
4/18 8:10
1国を歩き出すと、右手に吾妻山を見ながら進みます。
 梅沢で旧道へ
梅沢で旧道へ
 1
1
4/18 8:18
梅沢で旧道へ
 暫く歩くと右手に等覚院。階段を上がって入ると・・・・
暫く歩くと右手に等覚院。階段を上がって入ると・・・・
 1
1
4/18 8:28
暫く歩くと右手に等覚院。階段を上がって入ると・・・・
 見頃を過ぎたフジですが、まだ見られました。
見頃を過ぎたフジですが、まだ見られました。
 2
2
4/18 8:26
見頃を過ぎたフジですが、まだ見られました。
 別名藤巻寺と言われているようです。
別名藤巻寺と言われているようです。
 1
1
4/18 8:26
別名藤巻寺と言われているようです。
 寺の周りは、満開のツツジ
寺の周りは、満開のツツジ
 6
6
4/18 8:28
寺の周りは、満開のツツジ
 道祖神の所で、1国へ
道祖神の所で、1国へ
 1
1
4/18 8:30
道祖神の所で、1国へ
 箱根駅伝のTV固定カメラが設置される押切坂に入ります。左の旧道へ進みます
箱根駅伝のTV固定カメラが設置される押切坂に入ります。左の旧道へ進みます
 1
1
4/18 8:37
箱根駅伝のTV固定カメラが設置される押切坂に入ります。左の旧道へ進みます
 坂の入口に押切一里塚跡
坂の入口に押切一里塚跡
 1
1
4/18 8:38
坂の入口に押切一里塚跡
 梅沢の立場と言われ、商店や茶屋が並んでいたそうです。
梅沢の立場と言われ、商店や茶屋が並んでいたそうです。
 1
1
4/18 8:38
梅沢の立場と言われ、商店や茶屋が並んでいたそうです。
 梅沢の立場の中心となっていた松屋本陣跡。押切坂を下ると1国に合流。
梅沢の立場の中心となっていた松屋本陣跡。押切坂を下ると1国に合流。
 1
1
4/18 8:41
梅沢の立場の中心となっていた松屋本陣跡。押切坂を下ると1国に合流。
 押切橋を渡って緩い坂を上がって行くと、相模湾が望めるようになります。昔の人は、相模湾を眺めて何を思ったのかな
押切橋を渡って緩い坂を上がって行くと、相模湾が望めるようになります。昔の人は、相模湾を眺めて何を思ったのかな
 1
1
4/18 8:55
押切橋を渡って緩い坂を上がって行くと、相模湾が望めるようになります。昔の人は、相模湾を眺めて何を思ったのかな
 下りに入るがこの坂は、車坂と言うらしい。この辺りで読まれた歌が書かれている。
下りに入るがこの坂は、車坂と言うらしい。この辺りで読まれた歌が書かれている。
 1
1
4/18 8:59
下りに入るがこの坂は、車坂と言うらしい。この辺りで読まれた歌が書かれている。
 すぐ大山道の入口
すぐ大山道の入口
 1
1
4/18 9:01
すぐ大山道の入口
 国府津駅1km位手前には、近戸神社
国府津駅1km位手前には、近戸神社
 1
1
4/18 9:06
国府津駅1km位手前には、近戸神社
 国府津駅を過ぎ1国を歩きます。所々に大きな松の木が残っています。これは、当時からある松だろうね。当時を偲べるものは、松くらいかな
国府津駅を過ぎ1国を歩きます。所々に大きな松の木が残っています。これは、当時からある松だろうね。当時を偲べるものは、松くらいかな
 2
2
4/18 9:50
国府津駅を過ぎ1国を歩きます。所々に大きな松の木が残っています。これは、当時からある松だろうね。当時を偲べるものは、松くらいかな
 三寶寺。江戸時代は増上寺の末寺としてこの辺りの寺院を管理していらしい
三寶寺。江戸時代は増上寺の末寺としてこの辺りの寺院を管理していらしい
 2
2
4/18 9:56
三寶寺。江戸時代は増上寺の末寺としてこの辺りの寺院を管理していらしい
 鐘楼から見た眺め。晴れていれば富士山が見られるかな
鐘楼から見た眺め。晴れていれば富士山が見られるかな
 1
1
4/18 9:57
鐘楼から見た眺め。晴れていれば富士山が見られるかな
 1国に戻って進むと、また大きな松が見られます。
1国に戻って進むと、また大きな松が見られます。
 2
2
4/18 10:05
1国に戻って進むと、また大きな松が見られます。
 道祖神は、あちこち残っています。
道祖神は、あちこち残っています。
 1
1
4/18 10:08
道祖神は、あちこち残っています。
 こんな古そうな建屋も見られます。長屋門みたいです
こんな古そうな建屋も見られます。長屋門みたいです
 1
1
4/18 10:17
こんな古そうな建屋も見られます。長屋門みたいです
 酒匂川が近くなって来ました。その前に、法船寺へ。日蓮が一泊した霊跡の一つとして、信徒の巡拝コースに入っているそうです。
酒匂川が近くなって来ました。その前に、法船寺へ。日蓮が一泊した霊跡の一つとして、信徒の巡拝コースに入っているそうです。
 1
1
4/18 10:24
酒匂川が近くなって来ました。その前に、法船寺へ。日蓮が一泊した霊跡の一つとして、信徒の巡拝コースに入っているそうです。
 ミニの五重塔。1994年に完成した最近の物でした。高さ6.4m、でも総檜本瓦葺きの本格建築です
ミニの五重塔。1994年に完成した最近の物でした。高さ6.4m、でも総檜本瓦葺きの本格建築です
 2
2
4/18 10:25
ミニの五重塔。1994年に完成した最近の物でした。高さ6.4m、でも総檜本瓦葺きの本格建築です
 酒匂川に出ました。晴れてれば富士山が綺麗に見れたでしょう。昔は、今の橋より北がわに道があったそうです。
酒匂川に出ました。晴れてれば富士山が綺麗に見れたでしょう。昔は、今の橋より北がわに道があったそうです。
 4
4
4/18 10:32
酒匂川に出ました。晴れてれば富士山が綺麗に見れたでしょう。昔は、今の橋より北がわに道があったそうです。
 左岸を北に少し進むと石碑がありました。広重の小田原酒匂川の浮世絵のようですが、よくわかりません。
左岸を北に少し進むと石碑がありました。広重の小田原酒匂川の浮世絵のようですが、よくわかりません。
 1
1
4/18 10:33
左岸を北に少し進むと石碑がありました。広重の小田原酒匂川の浮世絵のようですが、よくわかりません。
 冬以外は橋が掛っていなかったから、渡し場から川越し人足によって川を渡らなければならなかったそうだから、不便この上なしだったに違いない。
冬以外は橋が掛っていなかったから、渡し場から川越し人足によって川を渡らなければならなかったそうだから、不便この上なしだったに違いない。
 1
1
冬以外は橋が掛っていなかったから、渡し場から川越し人足によって川を渡らなければならなかったそうだから、不便この上なしだったに違いない。
 橋を渡り右岸を歩いてみました。古い松の木が見えますが、あのあたりが昔の渡し場があった所でしょうか
橋を渡り右岸を歩いてみました。古い松の木が見えますが、あのあたりが昔の渡し場があった所でしょうか
 2
2
4/18 10:49
橋を渡り右岸を歩いてみました。古い松の木が見えますが、あのあたりが昔の渡し場があった所でしょうか
 土手脇に二宮金次郎が藩主から表彰された地の石碑がありました。
土手脇に二宮金次郎が藩主から表彰された地の石碑がありました。
 2
2
4/18 10:56
土手脇に二宮金次郎が藩主から表彰された地の石碑がありました。
 こんもりとした松林があったので行って見ました。旧道は、この辺りを通っていたのかも
こんもりとした松林があったので行って見ました。旧道は、この辺りを通っていたのかも
 1
1
4/18 11:00
こんもりとした松林があったので行って見ました。旧道は、この辺りを通っていたのかも
 湘南バイパスの出口と合流した所に、山王神社
湘南バイパスの出口と合流した所に、山王神社
 1
1
4/18 11:22
湘南バイパスの出口と合流した所に、山王神社
 山王神社の説明書き
山王神社の説明書き
 1
1
4/18 11:24
山王神社の説明書き
 山王神社の隣には、宗福寺。書いていないけど、ここまでにいくつお寺があったのか、お寺さん多いですね
山王神社の隣には、宗福寺。書いていないけど、ここまでにいくつお寺があったのか、お寺さん多いですね
 1
1
4/18 11:28
山王神社の隣には、宗福寺。書いていないけど、ここまでにいくつお寺があったのか、お寺さん多いですね
 境内の右手に山王大権現社。崇福寺の鎮守だったそうだ
境内の右手に山王大権現社。崇福寺の鎮守だったそうだ
 1
1
4/18 11:29
境内の右手に山王大権現社。崇福寺の鎮守だったそうだ
 すぐ山王口。ここから小田原宿
すぐ山王口。ここから小田原宿
 1
1
4/18 11:31
すぐ山王口。ここから小田原宿
 道路の反対側には、江戸口見附跡
道路の反対側には、江戸口見附跡
 1
1
4/18 11:32
道路の反対側には、江戸口見附跡
 元に戻るとこちら側にも江戸見附跡と一里塚跡
元に戻るとこちら側にも江戸見附跡と一里塚跡
 1
1
4/18 11:33
元に戻るとこちら側にも江戸見附跡と一里塚跡
 箱根の山を見ながら小田原宿に入ります。
箱根の山を見ながら小田原宿に入ります。
 1
1
4/18 11:34
箱根の山を見ながら小田原宿に入ります。
 晴れていれば富士山も眺められたでしょう
晴れていれば富士山も眺められたでしょう
 1
1
4/18 11:34
晴れていれば富士山も眺められたでしょう
 この先1国を左折すると旧道
この先1国を左折すると旧道
 1
1
4/18 11:41
この先1国を左折すると旧道
 鍋を作っているところが多かったのかな。町名や小路名が刻まれた石碑が多く設置されています。
鍋を作っているところが多かったのかな。町名や小路名が刻まれた石碑が多く設置されています。
 1
1
4/18 11:44
鍋を作っているところが多かったのかな。町名や小路名が刻まれた石碑が多く設置されています。
 ここを右折。名の通りかまぼこ屋が多いから蒲鉾通り
ここを右折。名の通りかまぼこ屋が多いから蒲鉾通り
 1
1
4/18 11:45
ここを右折。名の通りかまぼこ屋が多いから蒲鉾通り
 「よろっちょう」と読むらしい。小田原市では昭和60年度から「歴史的町名碑保存事業」を実施し、市内105カ所に歴史的町名碑を設置したそうです。
「よろっちょう」と読むらしい。小田原市では昭和60年度から「歴史的町名碑保存事業」を実施し、市内105カ所に歴史的町名碑を設置したそうです。
 1
1
4/18 11:49
「よろっちょう」と読むらしい。小田原市では昭和60年度から「歴史的町名碑保存事業」を実施し、市内105カ所に歴史的町名碑を設置したそうです。
 高梨町。古くから商家や旅篭がならんでいたようです。町の中央寄りには、「下の問屋場(人足や馬による輸送の取り次き所)」があり、中宿町の「上の問屋場」と 10 日交代で勤めていたそうです
高梨町。古くから商家や旅篭がならんでいたようです。町の中央寄りには、「下の問屋場(人足や馬による輸送の取り次き所)」があり、中宿町の「上の問屋場」と 10 日交代で勤めていたそうです
 1
1
4/18 11:52
高梨町。古くから商家や旅篭がならんでいたようです。町の中央寄りには、「下の問屋場(人足や馬による輸送の取り次き所)」があり、中宿町の「上の問屋場」と 10 日交代で勤めていたそうです
 宮前町。江戸時代には、東海道に面した町の西側に城主専用の出入り口である「浜手門」と「高札場」があり、同時代末期、町内には、本陣 1 軒(大清水)、脇本陣2 軒、旅篭が 23 軒ほどあって、隣の本町とともに小田原宿の中心だったようです
宮前町。江戸時代には、東海道に面した町の西側に城主専用の出入り口である「浜手門」と「高札場」があり、同時代末期、町内には、本陣 1 軒(大清水)、脇本陣2 軒、旅篭が 23 軒ほどあって、隣の本町とともに小田原宿の中心だったようです
 1
1
4/18 11:56
宮前町。江戸時代には、東海道に面した町の西側に城主専用の出入り口である「浜手門」と「高札場」があり、同時代末期、町内には、本陣 1 軒(大清水)、脇本陣2 軒、旅篭が 23 軒ほどあって、隣の本町とともに小田原宿の中心だったようです
 清水金左衛門本陣跡
清水金左衛門本陣跡
 1
1
4/18 11:56
清水金左衛門本陣跡
 明治天皇も泊ったらしい
明治天皇も泊ったらしい
 1
1
4/18 11:59
明治天皇も泊ったらしい
 小田原宿なりわい交流館。昭和7年に建設された旧網問屋を再整備し、休憩所、観光案内等として活用されている。ここで1国と合流。
小田原宿なりわい交流館。昭和7年に建設された旧網問屋を再整備し、休憩所、観光案内等として活用されている。ここで1国と合流。
 2
2
4/18 12:03
小田原宿なりわい交流館。昭和7年に建設された旧網問屋を再整備し、休憩所、観光案内等として活用されている。ここで1国と合流。
 道路を渡った所に高札場跡
道路を渡った所に高札場跡
 1
1
4/18 12:01
道路を渡った所に高札場跡
 小田原宿の説明書。この辺りが当時の中心地か
小田原宿の説明書。この辺りが当時の中心地か
 1
1
4/18 12:04
小田原宿の説明書。この辺りが当時の中心地か
 片岡本陣跡
片岡本陣跡
 1
1
4/18 12:10
片岡本陣跡
 清水本陣跡
清水本陣跡
 1
1
4/18 12:14
清水本陣跡
 小田原北条氏時代からの旧家「外郎(ういろう)家」(永正元年(1504)、北条早雲の招きに応じて京都から小田原に移り住み、祖先伝来の秘薬「透項香(とうちんこう)」を製造販売しました。)がある
小田原北条氏時代からの旧家「外郎(ういろう)家」(永正元年(1504)、北条早雲の招きに応じて京都から小田原に移り住み、祖先伝来の秘薬「透項香(とうちんこう)」を製造販売しました。)がある
 1
1
4/18 12:17
小田原北条氏時代からの旧家「外郎(ういろう)家」(永正元年(1504)、北条早雲の招きに応じて京都から小田原に移り住み、祖先伝来の秘薬「透項香(とうちんこう)」を製造販売しました。)がある
 ういろ屋が派手になって目立っています。コンビニに寄ってお昼でも食べようかと、コンビニに。買物して食べようとしたら、そのコンビニイートインスペースなし!! しょうがないのでどこかの公園ででも食べようかと・・・
ういろ屋が派手になって目立っています。コンビニに寄ってお昼でも食べようかと、コンビニに。買物して食べようとしたら、そのコンビニイートインスペースなし!! しょうがないのでどこかの公園ででも食べようかと・・・
 2
2
4/18 12:13
ういろ屋が派手になって目立っています。コンビニに寄ってお昼でも食べようかと、コンビニに。買物して食べようとしたら、そのコンビニイートインスペースなし!! しょうがないのでどこかの公園ででも食べようかと・・・
 明治33年に開業した国で4番目の電車で、国府津−湯本間の12.9km軌道線の市内電車。この車両は、路線廃止後、長崎で活躍し、令和2年に里帰り。レストランの敷地の一角に置かれている
明治33年に開業した国で4番目の電車で、国府津−湯本間の12.9km軌道線の市内電車。この車両は、路線廃止後、長崎で活躍し、令和2年に里帰り。レストランの敷地の一角に置かれている
 4
4
4/18 12:23
明治33年に開業した国で4番目の電車で、国府津−湯本間の12.9km軌道線の市内電車。この車両は、路線廃止後、長崎で活躍し、令和2年に里帰り。レストランの敷地の一角に置かれている
 1国を左折すると静かな住宅街です。小田原藩主稲葉正則
1国を左折すると静かな住宅街です。小田原藩主稲葉正則
の時代、この地に上方から杜氏を招いて諸白酒をつくらせたことから、この地名が生まれたといわれています。
道の両側は、昔は、中級の藩士の武家地だったようです。
 1
1
4/18 12:33
1国を左折すると静かな住宅街です。小田原藩主稲葉正則
の時代、この地に上方から杜氏を招いて諸白酒をつくらせたことから、この地名が生まれたといわれています。
道の両側は、昔は、中級の藩士の武家地だったようです。
 静山荘の所で右折し西に。この通りは、サクラ並木で桜の季節は、さぞ綺麗でしょうね
静山荘の所で右折し西に。この通りは、サクラ並木で桜の季節は、さぞ綺麗でしょうね
 1
1
4/18 12:37
静山荘の所で右折し西に。この通りは、サクラ並木で桜の季節は、さぞ綺麗でしょうね
 この道は、西海子小路。地名の由来は、この地に「さいかち」(マメ科の落葉高木)の木が植えられていたためといわれています。今はない
この道は、西海子小路。地名の由来は、この地に「さいかち」(マメ科の落葉高木)の木が植えられていたためといわれています。今はない
 1
1
4/18 12:37
この道は、西海子小路。地名の由来は、この地に「さいかち」(マメ科の落葉高木)の木が植えられていたためといわれています。今はない
 御厩小路にぶつかります。地名の由来は、西海子小路がこの小路に交差した地点の西側に小田原藩の馬屋があったことによるそうです。ここを1国に戻ります。
御厩小路にぶつかります。地名の由来は、西海子小路がこの小路に交差した地点の西側に小田原藩の馬屋があったことによるそうです。ここを1国に戻ります。
 1
1
4/18 12:38
御厩小路にぶつかります。地名の由来は、西海子小路がこの小路に交差した地点の西側に小田原藩の馬屋があったことによるそうです。ここを1国に戻ります。
 豆相人車鉄道(人間が客車を押すという世界的にも珍しい鉄道)と呼ばれ明治29年3月に熱海〜小田原間(25.6km)が開通しました。その時の小田原駅跡。
豆相人車鉄道(人間が客車を押すという世界的にも珍しい鉄道)と呼ばれ明治29年3月に熱海〜小田原間(25.6km)が開通しました。その時の小田原駅跡。
 2
2
4/18 12:40
豆相人車鉄道(人間が客車を押すという世界的にも珍しい鉄道)と呼ばれ明治29年3月に熱海〜小田原間(25.6km)が開通しました。その時の小田原駅跡。
 東海道線のガードをくぐってすぐ左に大久寺
東海道線のガードをくぐってすぐ左に大久寺
 1
1
4/18 12:45
東海道線のガードをくぐってすぐ左に大久寺
 大久寺。大久保家の菩提樹
大久寺。大久保家の菩提樹
 1
1
4/18 12:46
大久寺。大久保家の菩提樹
 大久寺を出て1国を渡ると板橋見附跡
大久寺を出て1国を渡ると板橋見附跡
 1
1
4/18 12:50
大久寺を出て1国を渡ると板橋見附跡
 見附跡から1国を離れ旧道に入ります。
見附跡から1国を離れ旧道に入ります。
 2
2
4/18 12:54
見附跡から1国を離れ旧道に入ります。
 古い蔵みたいな建物が
古い蔵みたいな建物が
 1
1
4/18 12:59
古い蔵みたいな建物が
 昔の醤油屋だったらしい
昔の醤油屋だったらしい
 1
1
4/18 13:00
昔の醤油屋だったらしい
 板橋地蔵尊。本尊は弘法大師の御作「延命子育地蔵大菩薩」。公園がなかなか見つからなかったので、ここのペンチでやっとお昼に
板橋地蔵尊。本尊は弘法大師の御作「延命子育地蔵大菩薩」。公園がなかなか見つからなかったので、ここのペンチでやっとお昼に
 1
1
4/18 13:06
板橋地蔵尊。本尊は弘法大師の御作「延命子育地蔵大菩薩」。公園がなかなか見つからなかったので、ここのペンチでやっとお昼に
 大黒尊天。ここの大祭はかつては露天が200も出て賑やかでしたが、今はどうなんでしょうか。子供が小さい時に来た事あったな〜
大黒尊天。ここの大祭はかつては露天が200も出て賑やかでしたが、今はどうなんでしょうか。子供が小さい時に来た事あったな〜
 1
1
4/18 13:07
大黒尊天。ここの大祭はかつては露天が200も出て賑やかでしたが、今はどうなんでしょうか。子供が小さい時に来た事あったな〜
 暫く歩くと1国と合流。
暫く歩くと1国と合流。
 1
1
4/18 13:31
暫く歩くと1国と合流。
 山に近くなって来ました。箱根の山が見えるように。
山に近くなって来ました。箱根の山が見えるように。
 1
1
4/18 13:32
山に近くなって来ました。箱根の山が見えるように。
 箱根登山線を横切り旧道に
箱根登山線を横切り旧道に
 2
2
4/18 13:42
箱根登山線を横切り旧道に
 一里塚跡
一里塚跡
 1
1
4/18 13:48
一里塚跡
 サクラの綺麗な紹太寺の前を通過します。
サクラの綺麗な紹太寺の前を通過します。
 1
1
4/18 13:57
サクラの綺麗な紹太寺の前を通過します。
 再び箱根登山線を横断
再び箱根登山線を横断
 3
3
4/18 14:01
再び箱根登山線を横断
 一国 に入る手前には、こんな説明文が。日本初の有料道路だったようです。湯本があったので、明治に入って軽便鉄道や有料道路等当時としては、進んでいたようです。
一国 に入る手前には、こんな説明文が。日本初の有料道路だったようです。湯本があったので、明治に入って軽便鉄道や有料道路等当時としては、進んでいたようです。
 1
1
4/18 14:05
一国 に入る手前には、こんな説明文が。日本初の有料道路だったようです。湯本があったので、明治に入って軽便鉄道や有料道路等当時としては、進んでいたようです。
 三枚橋が見えて来ました。
三枚橋が見えて来ました。
 1
1
4/18 14:19
三枚橋が見えて来ました。
 あじさい橋にもそこそこ人がいます。外人さんがおおいですね
あじさい橋にもそこそこ人がいます。外人さんがおおいですね
 4
4
4/18 14:25
あじさい橋にもそこそこ人がいます。外人さんがおおいですね
 箱根湯本到着。今日は、ここまでで終わりに。足が痛くなってきた。昔の人は、健脚だったのでしょうね。
箱根湯本到着。今日は、ここまでで終わりに。足が痛くなってきた。昔の人は、健脚だったのでしょうね。
 3
3
4/18 14:26
箱根湯本到着。今日は、ここまでで終わりに。足が痛くなってきた。昔の人は、健脚だったのでしょうね。


 aruaru
aruaru

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手







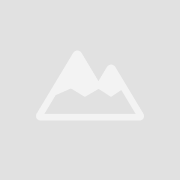





いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する