 24日の午前中に成田を出て、昼頃に済州国際空港に到着し、2日間家族で観光を楽しんだ後、3日目の26日に単独で漢拏山(ハルラ山)を登る予定を立てていました。ただし、空港に降り立った時はくっきり拝めた漢拏山も、水曜日の天気予報はあいにくの雨マーク。しかし、せっかくここまで来たのだから登らないと損なので、予定通り登ることにしました。
24日の午前中に成田を出て、昼頃に済州国際空港に到着し、2日間家族で観光を楽しんだ後、3日目の26日に単独で漢拏山(ハルラ山)を登る予定を立てていました。ただし、空港に降り立った時はくっきり拝めた漢拏山も、水曜日の天気予報はあいにくの雨マーク。しかし、せっかくここまで来たのだから登らないと損なので、予定通り登ることにしました。
 0
0
24日の午前中に成田を出て、昼頃に済州国際空港に到着し、2日間家族で観光を楽しんだ後、3日目の26日に単独で漢拏山(ハルラ山)を登る予定を立てていました。ただし、空港に降り立った時はくっきり拝めた漢拏山も、水曜日の天気予報はあいにくの雨マーク。しかし、せっかくここまで来たのだから登らないと損なので、予定通り登ることにしました。
 前日にタクシーを手配していたので、朝7時に済州市内のホテルに迎えに来てもらって、およそ25分くらいで城坂岳(ソンパナク)登山道入口に到着。当初、勾配が厳しいためにハイカーが少ない観音寺(クァヌムサ)登山道から登る予定でしたが、あいにくの雨でしたので、登山道が滑って歩き辛くなるのを避けて、歩きやすい城坂岳(ソンパナク)登山道から登ることにしました。入口にある施設ではさまざまなものが売られているようです。
前日にタクシーを手配していたので、朝7時に済州市内のホテルに迎えに来てもらって、およそ25分くらいで城坂岳(ソンパナク)登山道入口に到着。当初、勾配が厳しいためにハイカーが少ない観音寺(クァヌムサ)登山道から登る予定でしたが、あいにくの雨でしたので、登山道が滑って歩き辛くなるのを避けて、歩きやすい城坂岳(ソンパナク)登山道から登ることにしました。入口にある施設ではさまざまなものが売られているようです。
 0
0
前日にタクシーを手配していたので、朝7時に済州市内のホテルに迎えに来てもらって、およそ25分くらいで城坂岳(ソンパナク)登山道入口に到着。当初、勾配が厳しいためにハイカーが少ない観音寺(クァヌムサ)登山道から登る予定でしたが、あいにくの雨でしたので、登山道が滑って歩き辛くなるのを避けて、歩きやすい城坂岳(ソンパナク)登山道から登ることにしました。入口にある施設ではさまざまなものが売られているようです。
 これが漢拏山の登山地図。右横(東側)からなだらかな稜線を登るのが城坂岳(ソンパナク)登山道で、入口の標高が750m、山頂までの距離は9.6kmになります。頂上の白鹿潭(ペクロクタム)から北に下る観音寺(クァヌムサ)登山道は、入口の標高が580m、距離が8.7kmになり、多くが勾配の厳しい区間になります。
これが漢拏山の登山地図。右横(東側)からなだらかな稜線を登るのが城坂岳(ソンパナク)登山道で、入口の標高が750m、山頂までの距離は9.6kmになります。頂上の白鹿潭(ペクロクタム)から北に下る観音寺(クァヌムサ)登山道は、入口の標高が580m、距離が8.7kmになり、多くが勾配の厳しい区間になります。
 0
0
これが漢拏山の登山地図。右横(東側)からなだらかな稜線を登るのが城坂岳(ソンパナク)登山道で、入口の標高が750m、山頂までの距離は9.6kmになります。頂上の白鹿潭(ペクロクタム)から北に下る観音寺(クァヌムサ)登山道は、入口の標高が580m、距離が8.7kmになり、多くが勾配の厳しい区間になります。
 ここが城坂岳(ソンパナク)登山道のスタート地点です。先行者はビニール合羽を着ていますが、これは前の画像の建物の中で売られているものです。
ここが城坂岳(ソンパナク)登山道のスタート地点です。先行者はビニール合羽を着ていますが、これは前の画像の建物の中で売られているものです。
 0
0
ここが城坂岳(ソンパナク)登山道のスタート地点です。先行者はビニール合羽を着ていますが、これは前の画像の建物の中で売られているものです。
 せっかくだから記念写真をセルフタイマーでパチリ。ウィンドブレーカー兼レインパーカーと新品のゴアテックスのパンツを持ってきていましたので、よほどの土砂降りでない限りこれで問題ないでしょう。ただし、フィルムカメラはそのままではヤバイので、ウェストバッグもそうですが、コンビ二のビニール袋に包んで固定しておきました。
せっかくだから記念写真をセルフタイマーでパチリ。ウィンドブレーカー兼レインパーカーと新品のゴアテックスのパンツを持ってきていましたので、よほどの土砂降りでない限りこれで問題ないでしょう。ただし、フィルムカメラはそのままではヤバイので、ウェストバッグもそうですが、コンビ二のビニール袋に包んで固定しておきました。
 1
1
せっかくだから記念写真をセルフタイマーでパチリ。ウィンドブレーカー兼レインパーカーと新品のゴアテックスのパンツを持ってきていましたので、よほどの土砂降りでない限りこれで問題ないでしょう。ただし、フィルムカメラはそのままではヤバイので、ウェストバッグもそうですが、コンビ二のビニール袋に包んで固定しておきました。
 まずはこんな感じの石畳みたいな道が続きます。あまり大きくない岩をランダムに並べて埋め込んだ感じで、あまり凹凸が大きくないために歩きやすいです。案内板がおよそ500m毎に立っていて、山頂までの図とともに詳細な距離が描かれていて大変便利でした。
まずはこんな感じの石畳みたいな道が続きます。あまり大きくない岩をランダムに並べて埋め込んだ感じで、あまり凹凸が大きくないために歩きやすいです。案内板がおよそ500m毎に立っていて、山頂までの図とともに詳細な距離が描かれていて大変便利でした。
 0
0
まずはこんな感じの石畳みたいな道が続きます。あまり大きくない岩をランダムに並べて埋め込んだ感じで、あまり凹凸が大きくないために歩きやすいです。案内板がおよそ500m毎に立っていて、山頂までの図とともに詳細な距離が描かれていて大変便利でした。
 こうした木道区間も多いです。勾配は大変緩やかで、今のところ全く疲れることなく歩けます。
こうした木道区間も多いです。勾配は大変緩やかで、今のところ全く疲れることなく歩けます。
 0
0
こうした木道区間も多いです。勾配は大変緩やかで、今のところ全く疲れることなく歩けます。
 この表示板は時間制限を示したもので、12時30分までに標高1500m程のところにある有人のつつじ畑休憩所を通過しないとUターンさせられることになります。ちなみに山頂でも2時30分には下山を促されるそうです。
この表示板は時間制限を示したもので、12時30分までに標高1500m程のところにある有人のつつじ畑休憩所を通過しないとUターンさせられることになります。ちなみに山頂でも2時30分には下山を促されるそうです。
 1
1
この表示板は時間制限を示したもので、12時30分までに標高1500m程のところにある有人のつつじ畑休憩所を通過しないとUターンさせられることになります。ちなみに山頂でも2時30分には下山を促されるそうです。
 標高900m地点。なだらかな登り坂ですが、もう結構な距離は歩いています。入口が750mでしたから、まだ150mしか登ってはいません。こちらの登山道には標高100m毎にこの岩の表示が立っていました。
標高900m地点。なだらかな登り坂ですが、もう結構な距離は歩いています。入口が750mでしたから、まだ150mしか登ってはいません。こちらの登山道には標高100m毎にこの岩の表示が立っていました。
 0
0
標高900m地点。なだらかな登り坂ですが、もう結構な距離は歩いています。入口が750mでしたから、まだ150mしか登ってはいません。こちらの登山道には標高100m毎にこの岩の表示が立っていました。
 標高1000m地点。前を行く3人組もやはりビニール合羽ですね。この辺からちょっと勾配がそれなりになってきました。
標高1000m地点。前を行く3人組もやはりビニール合羽ですね。この辺からちょっと勾配がそれなりになってきました。
 0
0
標高1000m地点。前を行く3人組もやはりビニール合羽ですね。この辺からちょっと勾配がそれなりになってきました。
 このようにベンチは結構たくさん設けられていましたので、疲れたら適宜休むことができます。でも、この日は雨でしたから、座ると濡れてしまうので、ほとんど立って休んでいました。
このようにベンチは結構たくさん設けられていましたので、疲れたら適宜休むことができます。でも、この日は雨でしたから、座ると濡れてしまうので、ほとんど立って休んでいました。
 0
0
このようにベンチは結構たくさん設けられていましたので、疲れたら適宜休むことができます。でも、この日は雨でしたから、座ると濡れてしまうので、ほとんど立って休んでいました。
 最初の休憩所であるソクバッ待避所。ここは無人の東屋ですが、トイレも完備されていて建物もきれいでした。
最初の休憩所であるソクバッ待避所。ここは無人の東屋ですが、トイレも完備されていて建物もきれいでした。
 0
0
最初の休憩所であるソクバッ待避所。ここは無人の東屋ですが、トイレも完備されていて建物もきれいでした。
 そこにあった頂上までの案内板。漢字と仮名はこちらで追加していますが、ちょっとだけ間違えちゃいました。「観音寺」は「クァヌムサ」と読みます。
そこにあった頂上までの案内板。漢字と仮名はこちらで追加していますが、ちょっとだけ間違えちゃいました。「観音寺」は「クァヌムサ」と読みます。
 0
0
そこにあった頂上までの案内板。漢字と仮名はこちらで追加していますが、ちょっとだけ間違えちゃいました。「観音寺」は「クァヌムサ」と読みます。
 ソクバッ休憩所から先は勾配がそれなりになってきますが、まだここは緩やかですね。このすぐ後から一般登山道レベルの勾配になります。
ソクバッ休憩所から先は勾配がそれなりになってきますが、まだここは緩やかですね。このすぐ後から一般登山道レベルの勾配になります。
 0
0
ソクバッ休憩所から先は勾配がそれなりになってきますが、まだここは緩やかですね。このすぐ後から一般登山道レベルの勾配になります。
 1300m付近で紗羅岳(サラオルム)入口の分岐に至ります。ここから0.6km15分ほどの階段区間を歩けば紗羅岳泉と言う山上湖に至ります。もちろんここは立ち寄ってみますが、韓国人ハイカーさんらは皆先を急ぐように直進して行きます。せっかく来たのだから寄っておかないともったいない気がするんですけどねぇ。
1300m付近で紗羅岳(サラオルム)入口の分岐に至ります。ここから0.6km15分ほどの階段区間を歩けば紗羅岳泉と言う山上湖に至ります。もちろんここは立ち寄ってみますが、韓国人ハイカーさんらは皆先を急ぐように直進して行きます。せっかく来たのだから寄っておかないともったいない気がするんですけどねぇ。
 0
0
1300m付近で紗羅岳(サラオルム)入口の分岐に至ります。ここから0.6km15分ほどの階段区間を歩けば紗羅岳泉と言う山上湖に至ります。もちろんここは立ち寄ってみますが、韓国人ハイカーさんらは皆先を急ぐように直進して行きます。せっかく来たのだから寄っておかないともったいない気がするんですけどねぇ。
 階段区間が長く続くので結構疲れますが、もしこれがなかったら熊笹の生える土の区間だけに、雨の中では泥ヌタになって大変でしょうね。それにしても、これでもかと言うくらい整備されています。
階段区間が長く続くので結構疲れますが、もしこれがなかったら熊笹の生える土の区間だけに、雨の中では泥ヌタになって大変でしょうね。それにしても、これでもかと言うくらい整備されています。
 0
0
階段区間が長く続くので結構疲れますが、もしこれがなかったら熊笹の生える土の区間だけに、雨の中では泥ヌタになって大変でしょうね。それにしても、これでもかと言うくらい整備されています。
 紗羅岳(サラオルム)に到着。この湖は実は雨後にしか見られないものだそうで、昨晩から降った雨が溜まって見えるようになっていますが、何しろ漢拏山は休火山なので、地表が土質ではなくて火山岩ばかりですから、水はすぐに地中に吸い込まれて下の方で湧き水になって流れ出るんだそうです。確かに済州市内の川には、ほとんどどこにも水が流れていませんでしたね。
紗羅岳(サラオルム)に到着。この湖は実は雨後にしか見られないものだそうで、昨晩から降った雨が溜まって見えるようになっていますが、何しろ漢拏山は休火山なので、地表が土質ではなくて火山岩ばかりですから、水はすぐに地中に吸い込まれて下の方で湧き水になって流れ出るんだそうです。確かに済州市内の川には、ほとんどどこにも水が流れていませんでしたね。
 1
1
紗羅岳(サラオルム)に到着。この湖は実は雨後にしか見られないものだそうで、昨晩から降った雨が溜まって見えるようになっていますが、何しろ漢拏山は休火山なので、地表が土質ではなくて火山岩ばかりですから、水はすぐに地中に吸い込まれて下の方で湧き水になって流れ出るんだそうです。確かに済州市内の川には、ほとんどどこにも水が流れていませんでしたね。
 今回持って行ったフィルムカメラは1973年から生産されたトプコン・スーパーDMで、標準の50mm F1.4の他に28mm F2.8を持って行きました。100mmも日本から持って来ていましたが、天気が悪いので、遠景はまず絶望的ですから、ホテルに置いてきました。
今回持って行ったフィルムカメラは1973年から生産されたトプコン・スーパーDMで、標準の50mm F1.4の他に28mm F2.8を持って行きました。100mmも日本から持って来ていましたが、天気が悪いので、遠景はまず絶望的ですから、ホテルに置いてきました。
 1
1
今回持って行ったフィルムカメラは1973年から生産されたトプコン・スーパーDMで、標準の50mm F1.4の他に28mm F2.8を持って行きました。100mmも日本から持って来ていましたが、天気が悪いので、遠景はまず絶望的ですから、ホテルに置いてきました。
 結局、紗羅岳(サラオルム)には他に誰もやってきませんでした。こちらもUターンして本線に戻って上を目指します。勾配は画像の通りしっかりしたものになっています。
結局、紗羅岳(サラオルム)には他に誰もやってきませんでした。こちらもUターンして本線に戻って上を目指します。勾配は画像の通りしっかりしたものになっています。
 0
0
結局、紗羅岳(サラオルム)には他に誰もやってきませんでした。こちらもUターンして本線に戻って上を目指します。勾配は画像の通りしっかりしたものになっています。
 この岩の敷き詰められたところは、ぱっと見穴だらけの火山岩ゆえにグリップが良さそうに思いますが、晴れた日はもの凄い登山客が訪れ、さんざん踏まれて磨かれてきたので、雨の日では結構滑りました。それにしても、右の女性はスニーカーを直履きしていますが、靴ずれしないのかなぁ…。
この岩の敷き詰められたところは、ぱっと見穴だらけの火山岩ゆえにグリップが良さそうに思いますが、晴れた日はもの凄い登山客が訪れ、さんざん踏まれて磨かれてきたので、雨の日では結構滑りました。それにしても、右の女性はスニーカーを直履きしていますが、靴ずれしないのかなぁ…。
 1
1
この岩の敷き詰められたところは、ぱっと見穴だらけの火山岩ゆえにグリップが良さそうに思いますが、晴れた日はもの凄い登山客が訪れ、さんざん踏まれて磨かれてきたので、雨の日では結構滑りました。それにしても、右の女性はスニーカーを直履きしていますが、靴ずれしないのかなぁ…。
 標高1400m地点。ここの階段は四角く切った岩を並べたものですが、勾配がますます強まってきました。
標高1400m地点。ここの階段は四角く切った岩を並べたものですが、勾配がますます強まってきました。
 0
0
標高1400m地点。ここの階段は四角く切った岩を並べたものですが、勾配がますます強まってきました。
 一旦勾配が緩みますが、不揃いの岩が敷き詰められたところは歩きづらいですね。韓国のハイカーさんらはとにかく歩くのが速いですが、多くの皆さんが休憩所でゆっくり休むようで、さっき抜かしていった人がいつの間にか後ろにいることも結構ありました。
一旦勾配が緩みますが、不揃いの岩が敷き詰められたところは歩きづらいですね。韓国のハイカーさんらはとにかく歩くのが速いですが、多くの皆さんが休憩所でゆっくり休むようで、さっき抜かしていった人がいつの間にか後ろにいることも結構ありました。
 0
0
一旦勾配が緩みますが、不揃いの岩が敷き詰められたところは歩きづらいですね。韓国のハイカーさんらはとにかく歩くのが速いですが、多くの皆さんが休憩所でゆっくり休むようで、さっき抜かしていった人がいつの間にか後ろにいることも結構ありました。
 そしてつつじ畑(チンダルレバッ)休憩所に到着。ここに12時30分までに到着しないとUターンさせられることになります。ここは有人の待避所で、しっかり管理されている訳です。施設内部では多くの皆さんが休んで、窓口で買えるカップラーメンを食べていましたが、こちらは全くお腹が空いていないので、休憩所内部だけ確認して先を急ぎます。
そしてつつじ畑(チンダルレバッ)休憩所に到着。ここに12時30分までに到着しないとUターンさせられることになります。ここは有人の待避所で、しっかり管理されている訳です。施設内部では多くの皆さんが休んで、窓口で買えるカップラーメンを食べていましたが、こちらは全くお腹が空いていないので、休憩所内部だけ確認して先を急ぎます。
 1
1
そしてつつじ畑(チンダルレバッ)休憩所に到着。ここに12時30分までに到着しないとUターンさせられることになります。ここは有人の待避所で、しっかり管理されている訳です。施設内部では多くの皆さんが休んで、窓口で買えるカップラーメンを食べていましたが、こちらは全くお腹が空いていないので、休憩所内部だけ確認して先を急ぎます。
 休憩所のすぐ先に標高1500mの碑がありました。結構高いところまで来ていますが、まだ450mもありますね。案内表示では山頂まで1時間30分となっていました。
休憩所のすぐ先に標高1500mの碑がありました。結構高いところまで来ていますが、まだ450mもありますね。案内表示では山頂まで1時間30分となっていました。
 0
0
休憩所のすぐ先に標高1500mの碑がありました。結構高いところまで来ていますが、まだ450mもありますね。案内表示では山頂まで1時間30分となっていました。
 またこの石階段になります。これを見ると阿夫利神社下社からの大山登山を思い出しますね。
またこの石階段になります。これを見ると阿夫利神社下社からの大山登山を思い出しますね。
 1
1
またこの石階段になります。これを見ると阿夫利神社下社からの大山登山を思い出しますね。
 標高1600mの碑。他の碑と異なって出っ張った岩に直接刻んでいるようです。
標高1600mの碑。他の碑と異なって出っ張った岩に直接刻んでいるようです。
 0
0
標高1600mの碑。他の碑と異なって出っ張った岩に直接刻んでいるようです。
 標高1700m地点は画像のようにかなり岩の凹凸があって歩き辛いです。ルートから逸れないようにロープが張られた区間が大変多く、とにかく過剰なほど管理されていますが、残念ながらゴミはちらほらと全線で見られました。
標高1700m地点は画像のようにかなり岩の凹凸があって歩き辛いです。ルートから逸れないようにロープが張られた区間が大変多く、とにかく過剰なほど管理されていますが、残念ながらゴミはちらほらと全線で見られました。
 0
0
標高1700m地点は画像のようにかなり岩の凹凸があって歩き辛いです。ルートから逸れないようにロープが張られた区間が大変多く、とにかく過剰なほど管理されていますが、残念ながらゴミはちらほらと全線で見られました。
 もう8kmくらい進みましたが、これまでずっと鬱蒼とした林の中で展望が利かない道を黙々と歩いてきました。すると突然前が開けて山頂が見えるところに出ました。ここからしばらく長い階段+木道が続きます。
もう8kmくらい進みましたが、これまでずっと鬱蒼とした林の中で展望が利かない道を黙々と歩いてきました。すると突然前が開けて山頂が見えるところに出ました。ここからしばらく長い階段+木道が続きます。
 0
0
もう8kmくらい進みましたが、これまでずっと鬱蒼とした林の中で展望が利かない道を黙々と歩いてきました。すると突然前が開けて山頂が見えるところに出ました。ここからしばらく長い階段+木道が続きます。
 ちょっとすると展望台のようなスペースがあり、しばらく前から頭痛が起こっていたので、ここで座って荷物から薬を取り出して服用しました。実は初日の夜に寝冷えしたようで、2日目に頭が痛くなって薬を飲んでおいたら治ったので、大丈夫だと思いましたら、やはり雨の中の登山で気温も低かったせいもあって、ぶり返してしまったようです(;´д`) 山頂方面にはハイカーが連なっているのが見えますが、雨の中でもこんなに人がいるのですから、晴れた日の日曜日なんかはどうなっちゃうんでしょうね。それにしても、全員ビニール合羽とはねぇ…。
ちょっとすると展望台のようなスペースがあり、しばらく前から頭痛が起こっていたので、ここで座って荷物から薬を取り出して服用しました。実は初日の夜に寝冷えしたようで、2日目に頭が痛くなって薬を飲んでおいたら治ったので、大丈夫だと思いましたら、やはり雨の中の登山で気温も低かったせいもあって、ぶり返してしまったようです(;´д`) 山頂方面にはハイカーが連なっているのが見えますが、雨の中でもこんなに人がいるのですから、晴れた日の日曜日なんかはどうなっちゃうんでしょうね。それにしても、全員ビニール合羽とはねぇ…。
 1
1
ちょっとすると展望台のようなスペースがあり、しばらく前から頭痛が起こっていたので、ここで座って荷物から薬を取り出して服用しました。実は初日の夜に寝冷えしたようで、2日目に頭が痛くなって薬を飲んでおいたら治ったので、大丈夫だと思いましたら、やはり雨の中の登山で気温も低かったせいもあって、ぶり返してしまったようです(;´д`) 山頂方面にはハイカーが連なっているのが見えますが、雨の中でもこんなに人がいるのですから、晴れた日の日曜日なんかはどうなっちゃうんでしょうね。それにしても、全員ビニール合羽とはねぇ…。
 こんなニーチャンもいました。半袖半ズボンにスニーカー履きで傘を差しての登山ですからねぇ。まぁ、確かに整備された登山道ですから、晴れた日なら分からんでもないですが、雨が降って気温も5〜10℃未満ですから、やっぱり無謀でしょう。実際彼は山頂でじっとしていられず、傘も役に立たずになり、早々に同じ道を下って行きました。富士山にサンダルで登ろうとする人がいるそうですが、それよりは安全ながら、発想は全く同じですよね。
こんなニーチャンもいました。半袖半ズボンにスニーカー履きで傘を差しての登山ですからねぇ。まぁ、確かに整備された登山道ですから、晴れた日なら分からんでもないですが、雨が降って気温も5〜10℃未満ですから、やっぱり無謀でしょう。実際彼は山頂でじっとしていられず、傘も役に立たずになり、早々に同じ道を下って行きました。富士山にサンダルで登ろうとする人がいるそうですが、それよりは安全ながら、発想は全く同じですよね。
 0
0
こんなニーチャンもいました。半袖半ズボンにスニーカー履きで傘を差しての登山ですからねぇ。まぁ、確かに整備された登山道ですから、晴れた日なら分からんでもないですが、雨が降って気温も5〜10℃未満ですから、やっぱり無謀でしょう。実際彼は山頂でじっとしていられず、傘も役に立たずになり、早々に同じ道を下って行きました。富士山にサンダルで登ろうとする人がいるそうですが、それよりは安全ながら、発想は全く同じですよね。
 この展望台付近では雲が高いところにあって、下の方の遠景が見ることができました。向かいの小さな山は風水学では幸福を呼ぶ山なんだとか。
この展望台付近では雲が高いところにあって、下の方の遠景が見ることができました。向かいの小さな山は風水学では幸福を呼ぶ山なんだとか。
 2
2
この展望台付近では雲が高いところにあって、下の方の遠景が見ることができました。向かいの小さな山は風水学では幸福を呼ぶ山なんだとか。
 もう森林限界を超えているので、高い木はありませんで、溶岩が露出したところが多くなります。晴れていたらさぞワイルドで面白い景色が広がっていただろうと想像すると、ガックリきますので考えないようにしました。
もう森林限界を超えているので、高い木はありませんで、溶岩が露出したところが多くなります。晴れていたらさぞワイルドで面白い景色が広がっていただろうと想像すると、ガックリきますので考えないようにしました。
 1
1
もう森林限界を超えているので、高い木はありませんで、溶岩が露出したところが多くなります。晴れていたらさぞワイルドで面白い景色が広がっていただろうと想像すると、ガックリきますので考えないようにしました。
 木の階段区間が終わると溶岩と石段の登りになります。こうしたところですといつもは嫌がる階段が有り難く思えますね。一時的に雨が止んだので、前のハイカーさんらは合羽を脱いでいますが、この先ですぐにまた降り始めました。
木の階段区間が終わると溶岩と石段の登りになります。こうしたところですといつもは嫌がる階段が有り難く思えますね。一時的に雨が止んだので、前のハイカーさんらは合羽を脱いでいますが、この先ですぐにまた降り始めました。
 0
0
木の階段区間が終わると溶岩と石段の登りになります。こうしたところですといつもは嫌がる階段が有り難く思えますね。一時的に雨が止んだので、前のハイカーさんらは合羽を脱いでいますが、この先ですぐにまた降り始めました。
 山頂までの最後の登り区間はこんな岩だらけのところなので、補助用のロープが張られていました。ハイカーの数が多いせいか、左右に設けられていて、登山者下山者ともに使えるようになっていました。
山頂までの最後の登り区間はこんな岩だらけのところなので、補助用のロープが張られていました。ハイカーの数が多いせいか、左右に設けられていて、登山者下山者ともに使えるようになっていました。
 1
1
山頂までの最後の登り区間はこんな岩だらけのところなので、補助用のロープが張られていました。ハイカーの数が多いせいか、左右に設けられていて、登山者下山者ともに使えるようになっていました。
 そして11時55分に山頂到着! 実は厳密には漢拏山の最高地点は山上湖の対岸側なのですが、そちらは立ち入り禁止になっていて、ここが現時点で登れる最高地点になります。ここまで4時間半掛かりましたが、途中、紗羅岳(サラオルム)に寄っていますので、実質4時間丁度の登頂になりました。
そして11時55分に山頂到着! 実は厳密には漢拏山の最高地点は山上湖の対岸側なのですが、そちらは立ち入り禁止になっていて、ここが現時点で登れる最高地点になります。ここまで4時間半掛かりましたが、途中、紗羅岳(サラオルム)に寄っていますので、実質4時間丁度の登頂になりました。
 2
2
そして11時55分に山頂到着! 実は厳密には漢拏山の最高地点は山上湖の対岸側なのですが、そちらは立ち入り禁止になっていて、ここが現時点で登れる最高地点になります。ここまで4時間半掛かりましたが、途中、紗羅岳(サラオルム)に寄っていますので、実質4時間丁度の登頂になりました。
 本当なら山上湖の白鹿潭(ペクロクタム)がこんな感じできれいに見られるはずだったんですが、向こうを覗いてみてもただ真っ白なだけ…。
本当なら山上湖の白鹿潭(ペクロクタム)がこんな感じできれいに見られるはずだったんですが、向こうを覗いてみてもただ真っ白なだけ…。
 1
1
本当なら山上湖の白鹿潭(ペクロクタム)がこんな感じできれいに見られるはずだったんですが、向こうを覗いてみてもただ真っ白なだけ…。
 山頂には結構人が多かったですが、風が強く吹いていて寒い上、雨も降っているので、じっくり休まずすぐ戻っていく人も多かったです。今まで登りで汗をかいていたので、頂上で冷い風にさらされてかなり寒くなってきました。さっさと昼食を取って下山します。
山頂には結構人が多かったですが、風が強く吹いていて寒い上、雨も降っているので、じっくり休まずすぐ戻っていく人も多かったです。今まで登りで汗をかいていたので、頂上で冷い風にさらされてかなり寒くなってきました。さっさと昼食を取って下山します。
 1
1
山頂には結構人が多かったですが、風が強く吹いていて寒い上、雨も降っているので、じっくり休まずすぐ戻っていく人も多かったです。今まで登りで汗をかいていたので、頂上で冷い風にさらされてかなり寒くなってきました。さっさと昼食を取って下山します。
 漢拏山は火気禁止なので、いつも登山時に味わっている「出前山頂」が味わえません。仕方ないので、前日に市内のスーパーで買っておいた海苔巻き(キムパプ/キンパッ)を食べましたが、どうも美味しくないですね。日本のコンビ二の紅鮭やおかかのおにぎりの方が断然美味いと思っちゃいます。レストランでもそうでしたが、意外と韓国は食材や料理の値段が高い割りに、味がイマイチな場合が多く、単純にキムチ一つをとっても、何かリンゴのような果物の味が強く感じられ、辛子とニンニク、塩辛の酸味などと合わさって、とても美味いとは思えませんでしたね。日本の焼肉屋が美味しいのは、中国が発祥のラーメンと同じく、独自進化しているのが良く分かりますね。
漢拏山は火気禁止なので、いつも登山時に味わっている「出前山頂」が味わえません。仕方ないので、前日に市内のスーパーで買っておいた海苔巻き(キムパプ/キンパッ)を食べましたが、どうも美味しくないですね。日本のコンビ二の紅鮭やおかかのおにぎりの方が断然美味いと思っちゃいます。レストランでもそうでしたが、意外と韓国は食材や料理の値段が高い割りに、味がイマイチな場合が多く、単純にキムチ一つをとっても、何かリンゴのような果物の味が強く感じられ、辛子とニンニク、塩辛の酸味などと合わさって、とても美味いとは思えませんでしたね。日本の焼肉屋が美味しいのは、中国が発祥のラーメンと同じく、独自進化しているのが良く分かりますね。
 1
1
漢拏山は火気禁止なので、いつも登山時に味わっている「出前山頂」が味わえません。仕方ないので、前日に市内のスーパーで買っておいた海苔巻き(キムパプ/キンパッ)を食べましたが、どうも美味しくないですね。日本のコンビ二の紅鮭やおかかのおにぎりの方が断然美味いと思っちゃいます。レストランでもそうでしたが、意外と韓国は食材や料理の値段が高い割りに、味がイマイチな場合が多く、単純にキムチ一つをとっても、何かリンゴのような果物の味が強く感じられ、辛子とニンニク、塩辛の酸味などと合わさって、とても美味いとは思えませんでしたね。日本の焼肉屋が美味しいのは、中国が発祥のラーメンと同じく、独自進化しているのが良く分かりますね。
 昼食を早々に済ませて下山開始です。下りは勾配のキツい観音寺(クァヌムサ)登山道を使います。済州島はアワビのような形の横に広がった楕円形の島ですが、その形の元になる漢拏山も当然同じように横に広がる形の山です。往路で使った城坂岳(ソンパナク)登山道がその横側のなだらかな稜線を登るのに対し、この観音寺(クァヌムサ)登山道は北側の急斜面を通る道になっていて、距離は1kmほど短いものの、入口の標高が低いこともあって、登りで使うには難儀する道です。
昼食を早々に済ませて下山開始です。下りは勾配のキツい観音寺(クァヌムサ)登山道を使います。済州島はアワビのような形の横に広がった楕円形の島ですが、その形の元になる漢拏山も当然同じように横に広がる形の山です。往路で使った城坂岳(ソンパナク)登山道がその横側のなだらかな稜線を登るのに対し、この観音寺(クァヌムサ)登山道は北側の急斜面を通る道になっていて、距離は1kmほど短いものの、入口の標高が低いこともあって、登りで使うには難儀する道です。
 0
0
昼食を早々に済ませて下山開始です。下りは勾配のキツい観音寺(クァヌムサ)登山道を使います。済州島はアワビのような形の横に広がった楕円形の島ですが、その形の元になる漢拏山も当然同じように横に広がる形の山です。往路で使った城坂岳(ソンパナク)登山道がその横側のなだらかな稜線を登るのに対し、この観音寺(クァヌムサ)登山道は北側の急斜面を通る道になっていて、距離は1kmほど短いものの、入口の標高が低いこともあって、登りで使うには難儀する道です。
 早速急な勾配を下りますが、しばらくは木の階段が設置されていて歩きやすくなっています。階段の色が何か赤茶けて見えますが、実は城坂岳(ソンパナク)登山道では見られなかった赤くて脆い岩石が多くなって、それらが潰されて砂になったものが染み付いたもののようです。
早速急な勾配を下りますが、しばらくは木の階段が設置されていて歩きやすくなっています。階段の色が何か赤茶けて見えますが、実は城坂岳(ソンパナク)登山道では見られなかった赤くて脆い岩石が多くなって、それらが潰されて砂になったものが染み付いたもののようです。
 0
0
早速急な勾配を下りますが、しばらくは木の階段が設置されていて歩きやすくなっています。階段の色が何か赤茶けて見えますが、実は城坂岳(ソンパナク)登山道では見られなかった赤くて脆い岩石が多くなって、それらが潰されて砂になったものが染み付いたもののようです。
 山頂に近いところにも木は立っていましたが、多くが森林限界よりも高いところのためか枯れていました。今のところ天候が悪かったのでフィルムの消費はまだ4〜5枚ですが、下り始めたら雨が止んできました。
山頂に近いところにも木は立っていましたが、多くが森林限界よりも高いところのためか枯れていました。今のところ天候が悪かったのでフィルムの消費はまだ4〜5枚ですが、下り始めたら雨が止んできました。
 0
0
山頂に近いところにも木は立っていましたが、多くが森林限界よりも高いところのためか枯れていました。今のところ天候が悪かったのでフィルムの消費はまだ4〜5枚ですが、下り始めたら雨が止んできました。
 こちらの道には土もところどころ出てきて、水溜りもあって靴が汚れないように気を付けて歩きます。考えてみると、これまで雨が降っていても泥汚れになる区間は皆無でした。
こちらの道には土もところどころ出てきて、水溜りもあって靴が汚れないように気を付けて歩きます。考えてみると、これまで雨が降っていても泥汚れになる区間は皆無でした。
 1
1
こちらの道には土もところどころ出てきて、水溜りもあって靴が汚れないように気を付けて歩きます。考えてみると、これまで雨が降っていても泥汚れになる区間は皆無でした。
 観音寺(クァヌムサ)登山道には標高を示す碑がほとんど設けられていませんでした。この1800mのやつと下の方にあった1000mのものだけでしたね。
観音寺(クァヌムサ)登山道には標高を示す碑がほとんど設けられていませんでした。この1800mのやつと下の方にあった1000mのものだけでしたね。
 0
0
観音寺(クァヌムサ)登山道には標高を示す碑がほとんど設けられていませんでした。この1800mのやつと下の方にあった1000mのものだけでしたね。
 木を埋め込んだ階段と石段の道が続きます。勾配がキツいので、下りでは体が前に出やすくなり、一見グリップの良さそうな岩も実は結構雨で滑りやすくなっていて、合計3回足が流れてコケそうになりました。
木を埋め込んだ階段と石段の道が続きます。勾配がキツいので、下りでは体が前に出やすくなり、一見グリップの良さそうな岩も実は結構雨で滑りやすくなっていて、合計3回足が流れてコケそうになりました。
 0
0
木を埋め込んだ階段と石段の道が続きます。勾配がキツいので、下りでは体が前に出やすくなり、一見グリップの良さそうな岩も実は結構雨で滑りやすくなっていて、合計3回足が流れてコケそうになりました。
 一旦急な下りが落ち着くと、平坦な展望台みたいなところに出ました。尾根道から谷間に出てきたようです。
一旦急な下りが落ち着くと、平坦な展望台みたいなところに出ました。尾根道から谷間に出てきたようです。
 0
0
一旦急な下りが落ち着くと、平坦な展望台みたいなところに出ました。尾根道から谷間に出てきたようです。
 展望台の先から見回すと、水のない渓谷が見えました。雨の日にも水がないのだから、ここを水が流れる時は台風時のような大雨の時だけなんでしょうね。
展望台の先から見回すと、水のない渓谷が見えました。雨の日にも水がないのだから、ここを水が流れる時は台風時のような大雨の時だけなんでしょうね。
 0
0
展望台の先から見回すと、水のない渓谷が見えました。雨の日にも水がないのだから、ここを水が流れる時は台風時のような大雨の時だけなんでしょうね。
 展望台から少し下ると先の方で吊橋が見えてきました。位置はまだ全体の1/4くらいしか進んでいません。
展望台から少し下ると先の方で吊橋が見えてきました。位置はまだ全体の1/4くらいしか進んでいません。
 0
0
展望台から少し下ると先の方で吊橋が見えてきました。位置はまだ全体の1/4くらいしか進んでいません。
 この吊橋は竜鎮閣(ヨンジンカク)吊橋という名で、登山道の橋としては妙に立派です。相当お金を掛けていますが、軽自動車なら通れそうなほどの幅でした。
この吊橋は竜鎮閣(ヨンジンカク)吊橋という名で、登山道の橋としては妙に立派です。相当お金を掛けていますが、軽自動車なら通れそうなほどの幅でした。
 0
0
この吊橋は竜鎮閣(ヨンジンカク)吊橋という名で、登山道の橋としては妙に立派です。相当お金を掛けていますが、軽自動車なら通れそうなほどの幅でした。
 その橋の端にはこんな石像が。チョゴリを着た女性が大きな瓶を背負っている像ですが、昔の済州島の女性はこうして家から湧き水の出るところまで瓶を担いで汲みに行っていたそうです。女性の仕事なんだそうですが、かなりハードなことをやっていたんですね。ちなみに、昔の済州島の男性はぐうたらな者が多く、女性が海女などで稼いで家を支えていたそうです。
その橋の端にはこんな石像が。チョゴリを着た女性が大きな瓶を背負っている像ですが、昔の済州島の女性はこうして家から湧き水の出るところまで瓶を担いで汲みに行っていたそうです。女性の仕事なんだそうですが、かなりハードなことをやっていたんですね。ちなみに、昔の済州島の男性はぐうたらな者が多く、女性が海女などで稼いで家を支えていたそうです。
 1
1
その橋の端にはこんな石像が。チョゴリを着た女性が大きな瓶を背負っている像ですが、昔の済州島の女性はこうして家から湧き水の出るところまで瓶を担いで汲みに行っていたそうです。女性の仕事なんだそうですが、かなりハードなことをやっていたんですね。ちなみに、昔の済州島の男性はぐうたらな者が多く、女性が海女などで稼いで家を支えていたそうです。
 橋の反対側には湧き水が出ていました。せっかくだから瓶と言う訳にはいきませんが、500ccのペットボトルに水を汲んで、帰路で味わうことにしました。
橋の反対側には湧き水が出ていました。せっかくだから瓶と言う訳にはいきませんが、500ccのペットボトルに水を汲んで、帰路で味わうことにしました。
 1
1
橋の反対側には湧き水が出ていました。せっかくだから瓶と言う訳にはいきませんが、500ccのペットボトルに水を汲んで、帰路で味わうことにしました。
 このルートは渓谷沿いを進むことが多いので、小さな枯れ沢と合流することも少しありましたが、やっぱり水があるかどうかで随分景観の度合いが異なりますね。そう思うと、やはり水の豊富な地元丹沢の渓谷の方が美しく思えますね。ただし、こちらにはヒルはいませんけどね(笑。
このルートは渓谷沿いを進むことが多いので、小さな枯れ沢と合流することも少しありましたが、やっぱり水があるかどうかで随分景観の度合いが異なりますね。そう思うと、やはり水の豊富な地元丹沢の渓谷の方が美しく思えますね。ただし、こちらにはヒルはいませんけどね(笑。
 1
1
このルートは渓谷沿いを進むことが多いので、小さな枯れ沢と合流することも少しありましたが、やっぱり水があるかどうかで随分景観の度合いが異なりますね。そう思うと、やはり水の豊富な地元丹沢の渓谷の方が美しく思えますね。ただし、こちらにはヒルはいませんけどね(笑。
 「おっ、韓国版鹿柵か?」と思いきや、落石防止の柵でした。車道の林道ならいざ知らず、登山ルートにこうしたものを設置するんですから、かなりの投資ですよね。ちなみに、漢拏山では鹿は害獣ではなく逆に保護されているそうです。タクシーの運ちゃんがやたらに自慢気に鹿が見られると言っていましたが、日本ではうんざりするほど見られるので、それについてはどうでも良かったです。
「おっ、韓国版鹿柵か?」と思いきや、落石防止の柵でした。車道の林道ならいざ知らず、登山ルートにこうしたものを設置するんですから、かなりの投資ですよね。ちなみに、漢拏山では鹿は害獣ではなく逆に保護されているそうです。タクシーの運ちゃんがやたらに自慢気に鹿が見られると言っていましたが、日本ではうんざりするほど見られるので、それについてはどうでも良かったです。
 1
1
「おっ、韓国版鹿柵か?」と思いきや、落石防止の柵でした。車道の林道ならいざ知らず、登山ルートにこうしたものを設置するんですから、かなりの投資ですよね。ちなみに、漢拏山では鹿は害獣ではなく逆に保護されているそうです。タクシーの運ちゃんがやたらに自慢気に鹿が見られると言っていましたが、日本ではうんざりするほど見られるので、それについてはどうでも良かったです。
 漢拏山では大変珍しい土だけの区間。ただし、50mも続かずに岩が出てきましたけどね(^∇^)。
漢拏山では大変珍しい土だけの区間。ただし、50mも続かずに岩が出てきましたけどね(^∇^)。
 0
0
漢拏山では大変珍しい土だけの区間。ただし、50mも続かずに岩が出てきましたけどね(^∇^)。
 標高1500m程のところにある竜鎮閣(ヨンジンカク)休憩所。ここも城坂岳(ソンパナク)登山道のつつじ畑(チンダルレバッ)休憩所と同じく、12時半が登山リミットの刻限です。
標高1500m程のところにある竜鎮閣(ヨンジンカク)休憩所。ここも城坂岳(ソンパナク)登山道のつつじ畑(チンダルレバッ)休憩所と同じく、12時半が登山リミットの刻限です。
 0
0
標高1500m程のところにある竜鎮閣(ヨンジンカク)休憩所。ここも城坂岳(ソンパナク)登山道のつつじ畑(チンダルレバッ)休憩所と同じく、12時半が登山リミットの刻限です。
 竜鎮閣(ヨンジンカク)休憩所内部。入口近くの狭い部屋に管理人がいて、ストーブを焚いてラジオを聴いていましたが、ここでも食料品や水を購入できるみたいです。それにしてもこの登山道は利用者が少ないですね。中には一人のハイカーもいませんでした。
竜鎮閣(ヨンジンカク)休憩所内部。入口近くの狭い部屋に管理人がいて、ストーブを焚いてラジオを聴いていましたが、ここでも食料品や水を購入できるみたいです。それにしてもこの登山道は利用者が少ないですね。中には一人のハイカーもいませんでした。
 0
0
竜鎮閣(ヨンジンカク)休憩所内部。入口近くの狭い部屋に管理人がいて、ストーブを焚いてラジオを聴いていましたが、ここでも食料品や水を購入できるみたいです。それにしてもこの登山道は利用者が少ないですね。中には一人のハイカーもいませんでした。
 やはりこの休憩所もここまでモノレールで物資を運んでいるようです。管理者もこれに乗ってやって来るのでしょうね。丹沢にあるモノレールとほとんど同じものでしたが、あちらは林業で用いているのに対し、こちらは観光登山用に設けられている点で異なりますね。
やはりこの休憩所もここまでモノレールで物資を運んでいるようです。管理者もこれに乗ってやって来るのでしょうね。丹沢にあるモノレールとほとんど同じものでしたが、あちらは林業で用いているのに対し、こちらは観光登山用に設けられている点で異なりますね。
 0
0
やはりこの休憩所もここまでモノレールで物資を運んでいるようです。管理者もこれに乗ってやって来るのでしょうね。丹沢にあるモノレールとほとんど同じものでしたが、あちらは林業で用いているのに対し、こちらは観光登山用に設けられている点で異なりますね。
 ここの休憩所には外側にラウンジのようなスペースがあり、外側で爽快な中で休むこともできます。まぁ、霧の中では全く意味がないですけどね(^∇^)。
ここの休憩所には外側にラウンジのようなスペースがあり、外側で爽快な中で休むこともできます。まぁ、霧の中では全く意味がないですけどね(^∇^)。
 1
1
ここの休憩所には外側にラウンジのようなスペースがあり、外側で爽快な中で休むこともできます。まぁ、霧の中では全く意味がないですけどね(^∇^)。
 休憩所からの下りもまだまだキツいです。やはりこちらはご覧のように土質の区間が多くなりますが、泥ヌタにはなっていませんね。
休憩所からの下りもまだまだキツいです。やはりこちらはご覧のように土質の区間が多くなりますが、泥ヌタにはなっていませんね。
 0
0
休憩所からの下りもまだまだキツいです。やはりこちらはご覧のように土質の区間が多くなりますが、泥ヌタにはなっていませんね。
 中間地点にあった分岐。地図には記載されていない道で、一体どこに向かうのかサッパリ分かりません。ハングルでは「ウォンチョムピ」と書かれているようですが、全く意味不明なので、そちらには寄りませんでした。
中間地点にあった分岐。地図には記載されていない道で、一体どこに向かうのかサッパリ分かりません。ハングルでは「ウォンチョムピ」と書かれているようですが、全く意味不明なので、そちらには寄りませんでした。
 0
0
中間地点にあった分岐。地図には記載されていない道で、一体どこに向かうのかサッパリ分かりません。ハングルでは「ウォンチョムピ」と書かれているようですが、全く意味不明なので、そちらには寄りませんでした。
 こんな岩の間の狭くなったところをすり抜ける箇所もありました。もしこれが城坂岳(ソンパナク)側にあったら大混雑になるだろうなと空想しながら抜けました。
こんな岩の間の狭くなったところをすり抜ける箇所もありました。もしこれが城坂岳(ソンパナク)側にあったら大混雑になるだろうなと空想しながら抜けました。
 0
0
こんな岩の間の狭くなったところをすり抜ける箇所もありました。もしこれが城坂岳(ソンパナク)側にあったら大混雑になるだろうなと空想しながら抜けました。
 歩いていたら岩の上から細い木の幹が立っていて、葉を広げていました。「どうなってんの?」と裏に進んでみると、1本だけ根が長く岩を這うようにして岩の切れ目に食い込んでいて、どこかその先で土に至っているんでしょう。それにしても、この木、よくもまぁ岩の上で立っていられるもんだと、感心しちゃいました。
歩いていたら岩の上から細い木の幹が立っていて、葉を広げていました。「どうなってんの?」と裏に進んでみると、1本だけ根が長く岩を這うようにして岩の切れ目に食い込んでいて、どこかその先で土に至っているんでしょう。それにしても、この木、よくもまぁ岩の上で立っていられるもんだと、感心しちゃいました。
 0
0
歩いていたら岩の上から細い木の幹が立っていて、葉を広げていました。「どうなってんの?」と裏に進んでみると、1本だけ根が長く岩を這うようにして岩の切れ目に食い込んでいて、どこかその先で土に至っているんでしょう。それにしても、この木、よくもまぁ岩の上で立っていられるもんだと、感心しちゃいました。
 この風景はナンだか丹沢で見慣れた感じがしますね。丹沢ならブナの原生林ですが、こちらの木は何でしょう。霧に包まれていてこれはこれで自然を感じられて良い雰囲気です。
この風景はナンだか丹沢で見慣れた感じがしますね。丹沢ならブナの原生林ですが、こちらの木は何でしょう。霧に包まれていてこれはこれで自然を感じられて良い雰囲気です。
 1
1
この風景はナンだか丹沢で見慣れた感じがしますね。丹沢ならブナの原生林ですが、こちらの木は何でしょう。霧に包まれていてこれはこれで自然を感じられて良い雰囲気です。
 こちらの登山道では2個しかない標高表示の碑。1000m地点ですから、もう950m下って来たことになります。でも、まだ400m下らないと出口には至りませんが、勾配が緩んで歩く距離自体は長くなります。
こちらの登山道では2個しかない標高表示の碑。1000m地点ですから、もう950m下って来たことになります。でも、まだ400m下らないと出口には至りませんが、勾配が緩んで歩く距離自体は長くなります。
 0
0
こちらの登山道では2個しかない標高表示の碑。1000m地点ですから、もう950m下って来たことになります。でも、まだ400m下らないと出口には至りませんが、勾配が緩んで歩く距離自体は長くなります。
 しばらく下っているとベンチが見えました。吊橋のところで写真を撮っている時に抜かして行った人達がここで休んでいました。彼らに限ったことではないですが、向こうのハイカーはとにかく急いで歩いています。まるでトレランみたいなペースです。しかし、休憩所では大体皆休んでいますね。ですから、抜かされてもいつの間にか追い付いてしまうんですが、大声で話しながら歩いていたり、他人がいてもお構いなしに音楽を鳴らしていたり、男なのに香水の臭いが強烈だったりしますから、写真を撮ったり、立ったまま水を飲んで休んだりして、少し間を置いて歩くようにしていました。
しばらく下っているとベンチが見えました。吊橋のところで写真を撮っている時に抜かして行った人達がここで休んでいました。彼らに限ったことではないですが、向こうのハイカーはとにかく急いで歩いています。まるでトレランみたいなペースです。しかし、休憩所では大体皆休んでいますね。ですから、抜かされてもいつの間にか追い付いてしまうんですが、大声で話しながら歩いていたり、他人がいてもお構いなしに音楽を鳴らしていたり、男なのに香水の臭いが強烈だったりしますから、写真を撮ったり、立ったまま水を飲んで休んだりして、少し間を置いて歩くようにしていました。
 0
0
しばらく下っているとベンチが見えました。吊橋のところで写真を撮っている時に抜かして行った人達がここで休んでいました。彼らに限ったことではないですが、向こうのハイカーはとにかく急いで歩いています。まるでトレランみたいなペースです。しかし、休憩所では大体皆休んでいますね。ですから、抜かされてもいつの間にか追い付いてしまうんですが、大声で話しながら歩いていたり、他人がいてもお構いなしに音楽を鳴らしていたり、男なのに香水の臭いが強烈だったりしますから、写真を撮ったり、立ったまま水を飲んで休んだりして、少し間を置いて歩くようにしていました。
 そのベンチのところにはトイレが設置されていました。耽羅渓谷(タンラケグッ)待避所と言うところみたいです。
そのベンチのところにはトイレが設置されていました。耽羅渓谷(タンラケグッ)待避所と言うところみたいです。
 0
0
そのベンチのところにはトイレが設置されていました。耽羅渓谷(タンラケグッ)待避所と言うところみたいです。
 もうそろそろなだらかになるのかと思いきや、まだまだこんな下りの階段が続きます。確かにこの道を登りで使うと大変ですね。
もうそろそろなだらかになるのかと思いきや、まだまだこんな下りの階段が続きます。確かにこの道を登りで使うと大変ですね。
 0
0
もうそろそろなだらかになるのかと思いきや、まだまだこんな下りの階段が続きます。確かにこの道を登りで使うと大変ですね。
 やっと階段が終わるかなと言うところに渓谷があって、アーチ橋が備えられていました。これも先ほどの吊橋同様にお金が掛かっていますね。幅も4人が横に並んで歩けるくらいです。
やっと階段が終わるかなと言うところに渓谷があって、アーチ橋が備えられていました。これも先ほどの吊橋同様にお金が掛かっていますね。幅も4人が横に並んで歩けるくらいです。
 1
1
やっと階段が終わるかなと言うところに渓谷があって、アーチ橋が備えられていました。これも先ほどの吊橋同様にお金が掛かっていますね。幅も4人が横に並んで歩けるくらいです。
 橋を渡ってからは勾配が一気に緩みます。上の方で登りのハイカー2人とすれ違いましたが、やはり下りで使われることが圧倒的に多いようですが、そもそも城坂岳(ソンパナク)登山道をUターンして帰る人が8割以上になるようです。
橋を渡ってからは勾配が一気に緩みます。上の方で登りのハイカー2人とすれ違いましたが、やはり下りで使われることが圧倒的に多いようですが、そもそも城坂岳(ソンパナク)登山道をUターンして帰る人が8割以上になるようです。
 0
0
橋を渡ってからは勾配が一気に緩みます。上の方で登りのハイカー2人とすれ違いましたが、やはり下りで使われることが圧倒的に多いようですが、そもそも城坂岳(ソンパナク)登山道をUターンして帰る人が8割以上になるようです。
 しばらく渓谷沿いの道になりますが、雨が降っても岩の間からすぐに水が地下に吸い込まれてしまい、「流れ」は全くありません。ただし、こんな感じで岩の凹部に水が溜まっている点は上の方の渓谷とは異なりますね。
しばらく渓谷沿いの道になりますが、雨が降っても岩の間からすぐに水が地下に吸い込まれてしまい、「流れ」は全くありません。ただし、こんな感じで岩の凹部に水が溜まっている点は上の方の渓谷とは異なりますね。
 0
0
しばらく渓谷沿いの道になりますが、雨が降っても岩の間からすぐに水が地下に吸い込まれてしまい、「流れ」は全くありません。ただし、こんな感じで岩の凹部に水が溜まっている点は上の方の渓谷とは異なりますね。
 少しすると、道の脇にこんな案内図が描かれた板が設けられたスペースがありました。そこに入ると渓谷側が良く見えます。
少しすると、道の脇にこんな案内図が描かれた板が設けられたスペースがありました。そこに入ると渓谷側が良く見えます。
 0
0
少しすると、道の脇にこんな案内図が描かれた板が設けられたスペースがありました。そこに入ると渓谷側が良く見えます。
 ここには洞穴があって、「クリン洞穴」と言うそうです。規模はそう大きくはないですが、目の前で見るとなかなか立派なものでした。
ここには洞穴があって、「クリン洞穴」と言うそうです。規模はそう大きくはないですが、目の前で見るとなかなか立派なものでした。
 0
0
ここには洞穴があって、「クリン洞穴」と言うそうです。規模はそう大きくはないですが、目の前で見るとなかなか立派なものでした。
 そして道は渓谷の上を渡渉と言うかそのまま進みます。晴れた日にはこの水もすぐに乾いてしまうのでしょうね。
そして道は渓谷の上を渡渉と言うかそのまま進みます。晴れた日にはこの水もすぐに乾いてしまうのでしょうね。
 0
0
そして道は渓谷の上を渡渉と言うかそのまま進みます。晴れた日にはこの水もすぐに乾いてしまうのでしょうね。
 平坦な区間になって半分くらい進んでいます。この位置表示の案内板は大変親切で良いですね。日本でも主要な山と言うか尾根道に設置して欲しいですね。
平坦な区間になって半分くらい進んでいます。この位置表示の案内板は大変親切で良いですね。日本でも主要な山と言うか尾根道に設置して欲しいですね。
 0
0
平坦な区間になって半分くらい進んでいます。この位置表示の案内板は大変親切で良いですね。日本でも主要な山と言うか尾根道に設置して欲しいですね。
 下の方は淵があってそれなりの水量がありました。丁度桜が散って水面に花びらが浮いていましたが、漢拏山ではこの時点で5分位の残りでした。ソメイヨシノではなく、済州島の山桜だそうです。
下の方は淵があってそれなりの水量がありました。丁度桜が散って水面に花びらが浮いていましたが、漢拏山ではこの時点で5分位の残りでした。ソメイヨシノではなく、済州島の山桜だそうです。
 1
1
下の方は淵があってそれなりの水量がありました。丁度桜が散って水面に花びらが浮いていましたが、漢拏山ではこの時点で5分位の残りでした。ソメイヨシノではなく、済州島の山桜だそうです。
 最終区間は木道が整備されていて、途中いくつもの説明表示板が立てられていました。漢拏山の動物や昆虫、草花や木々、水の流れやその他諸々の説明がいくつも道端に据えられていました。ハングル・英語・中国語・日本語で説明文が書かれているので有り難いです。
最終区間は木道が整備されていて、途中いくつもの説明表示板が立てられていました。漢拏山の動物や昆虫、草花や木々、水の流れやその他諸々の説明がいくつも道端に据えられていました。ハングル・英語・中国語・日本語で説明文が書かれているので有り難いです。
 0
0
最終区間は木道が整備されていて、途中いくつもの説明表示板が立てられていました。漢拏山の動物や昆虫、草花や木々、水の流れやその他諸々の説明がいくつも道端に据えられていました。ハングル・英語・中国語・日本語で説明文が書かれているので有り難いです。
 そしてついに観音寺(クァヌムサ)登山道8.7kmを踏破しました。時刻は午後4時7分ですから、下りでの目安時間の通り、およそ4時間の行程になりました。下りでこれくらい掛かるんだから、あのキツい勾配の登りだと目安の5時間では無理かも知れませんね。
そしてついに観音寺(クァヌムサ)登山道8.7kmを踏破しました。時刻は午後4時7分ですから、下りでの目安時間の通り、およそ4時間の行程になりました。下りでこれくらい掛かるんだから、あのキツい勾配の登りだと目安の5時間では無理かも知れませんね。
 1
1
そしてついに観音寺(クァヌムサ)登山道8.7kmを踏破しました。時刻は午後4時7分ですから、下りでの目安時間の通り、およそ4時間の行程になりました。下りでこれくらい掛かるんだから、あのキツい勾配の登りだと目安の5時間では無理かも知れませんね。
 観音寺(クァヌムサ)登山道は出口で使う人が多いためか、泥落とし用にエアガンが設置されていました。使ってみましたが、そもそもあまり泥が付いていなかったので無意味でした。駐車場(有料)は大変広いのですが、車はあまり並んでいませんでした。道を挟んで反対側に店があり、そこの駐車場にタクシーが3台止まっていて下山客を狙っていました。
観音寺(クァヌムサ)登山道は出口で使う人が多いためか、泥落とし用にエアガンが設置されていました。使ってみましたが、そもそもあまり泥が付いていなかったので無意味でした。駐車場(有料)は大変広いのですが、車はあまり並んでいませんでした。道を挟んで反対側に店があり、そこの駐車場にタクシーが3台止まっていて下山客を狙っていました。
 0
0
観音寺(クァヌムサ)登山道は出口で使う人が多いためか、泥落とし用にエアガンが設置されていました。使ってみましたが、そもそもあまり泥が付いていなかったので無意味でした。駐車場(有料)は大変広いのですが、車はあまり並んでいませんでした。道を挟んで反対側に店があり、そこの駐車場にタクシーが3台止まっていて下山客を狙っていました。
 こちらは朝送ってもらったタクシー(日本語を話せる運ちゃんでした)に夕方も来てもらうように約束していて、出口の1.2km手前で電話しておいたので、ちょっと待っただけでスムーズに帰れました。待っている間に道の向こう側にいた鳥ですが、見たことのない鳥ですね。大きさは鳩をわずかに小さくしたくらいですが、何と言う鳥でしょうか。
こちらは朝送ってもらったタクシー(日本語を話せる運ちゃんでした)に夕方も来てもらうように約束していて、出口の1.2km手前で電話しておいたので、ちょっと待っただけでスムーズに帰れました。待っている間に道の向こう側にいた鳥ですが、見たことのない鳥ですね。大きさは鳩をわずかに小さくしたくらいですが、何と言う鳥でしょうか。
 1
1
こちらは朝送ってもらったタクシー(日本語を話せる運ちゃんでした)に夕方も来てもらうように約束していて、出口の1.2km手前で電話しておいたので、ちょっと待っただけでスムーズに帰れました。待っている間に道の向こう側にいた鳥ですが、見たことのない鳥ですね。大きさは鳩をわずかに小さくしたくらいですが、何と言う鳥でしょうか。
 後半は雨が止みましたが、結局登山中は真っ白な雲の中で、遠景はほとんど見ることができませんでした。ただ、観音寺(クァヌムサ)登山道では渓谷沿いの道で近場の景観が楽しめたのだけは幸いでした。結構な高低差を延々と登るような登山道で疲れますが、考えてみると例えば丹沢で言うなら宮ヶ瀬から丹沢三峰縦走ルートで丹沢山まで11km歩く方が、たくさんの起伏があってはるかに疲れるんですよね。でも、この日は体調不良で薬でごまかしての登山でしたから、とにかくダルかったです。翌日帰国して成田から車で横浜に戻り車を降りた瞬間、もの凄い悪寒で震えが止まらず、高熱で寝込んでしまいましたが、何とか雨の中でも歩き切れて良かったです。
後半は雨が止みましたが、結局登山中は真っ白な雲の中で、遠景はほとんど見ることができませんでした。ただ、観音寺(クァヌムサ)登山道では渓谷沿いの道で近場の景観が楽しめたのだけは幸いでした。結構な高低差を延々と登るような登山道で疲れますが、考えてみると例えば丹沢で言うなら宮ヶ瀬から丹沢三峰縦走ルートで丹沢山まで11km歩く方が、たくさんの起伏があってはるかに疲れるんですよね。でも、この日は体調不良で薬でごまかしての登山でしたから、とにかくダルかったです。翌日帰国して成田から車で横浜に戻り車を降りた瞬間、もの凄い悪寒で震えが止まらず、高熱で寝込んでしまいましたが、何とか雨の中でも歩き切れて良かったです。
 1
1
後半は雨が止みましたが、結局登山中は真っ白な雲の中で、遠景はほとんど見ることができませんでした。ただ、観音寺(クァヌムサ)登山道では渓谷沿いの道で近場の景観が楽しめたのだけは幸いでした。結構な高低差を延々と登るような登山道で疲れますが、考えてみると例えば丹沢で言うなら宮ヶ瀬から丹沢三峰縦走ルートで丹沢山まで11km歩く方が、たくさんの起伏があってはるかに疲れるんですよね。でも、この日は体調不良で薬でごまかしての登山でしたから、とにかくダルかったです。翌日帰国して成田から車で横浜に戻り車を降りた瞬間、もの凄い悪寒で震えが止まらず、高熱で寝込んでしまいましたが、何とか雨の中でも歩き切れて良かったです。


 トプ・ガバチョ
トプ・ガバチョ

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手




























































































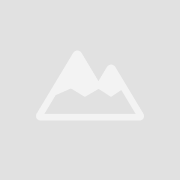






いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する