最終更新:ok12mikan
基本情報
| 標高 | 1999.7m |
|---|---|
| 場所 | 北緯35度19分10秒, 東経138度18分40秒 |
山頂の標識には、静岡県側の大谷嶺(1999.7m)と山梨県側の行田山(2000m)がある。ただしお互いの山名に異論があるのか、どうも破壊しあっているようだ。県界にある山は呼び名が違うことが多いので道迷いに注意下さい。
山伏経由で西日影沢コース周遊下山はお控えください。
10月台風被害により3架橋が流され、また登山道も崩落個所があり危険です、特に雨の増水時渡渉困難になり遭難の怖れがあります。
登下山とも自粛中(通行止め)です。早期再開通は困難が予想されます。
ヤマレコ、ヤマップ等への投稿も遭難を助長する文言はお控えください。
現在登山道の安全整備管理はできませんので自己責任でお願いします。
山伏経由で西日影沢コース周遊下山はお控えください。
10月台風被害により3架橋が流され、また登山道も崩落個所があり危険です、特に雨の増水時渡渉困難になり遭難の怖れがあります。
登下山とも自粛中(通行止め)です。早期再開通は困難が予想されます。
ヤマレコ、ヤマップ等への投稿も遭難を助長する文言はお控えください。
現在登山道の安全整備管理はできませんので自己責任でお願いします。
| 山頂 |
|---|
山の解説 - [出典:Wikipedia]
大谷崩(おおやくずれ)は、静岡市葵区の大谷嶺(おおやれい)の南斜面にある、1707年(宝永4年)の宝永地震によってできた山体崩壊である。1858年に富山県で起きた鳶山崩れ、1911年に長野県で起きた稗田山崩れとともに、日本三大崩れのひとつとされる。
大谷嶺は標高1999.7m安倍川(あべかわ)の水源のひとつである。大谷崩の位置に崩壊地があったことは1530年(享禄3年)の文献にはすでに書かれていると記されている。
崩壊で発生した土砂は1億2000万m3と推定され、これが三河内川を堰止めて大池を生じ、明治初頭まで存在していた。また下流に滝もつくりだしており、この滝は土砂のために真っ赤な水を流し続けたことから、「赤水の滝」()と呼ばれている。
現在でも大雨の後には多量の土砂崩落が見られる。山体崩壊の迫力のある形状とともに、春の新緑、秋の紅葉、冬の雪化粧などの景観にも優れることから、山の麓まで訪れる観光客も見られる。





 大谷嶺の山行記録へ
大谷嶺の山行記録へ

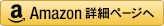








 Loading...
Loading...

