最終更新:まとやん/的場 一峰🍡
基本情報
| 標高 | 1729m |
|---|---|
| 場所 | 北緯35度22分16秒, 東経133度32分46秒 |
| 山頂 | |
|---|---|
| 危険個所 | |
| 展望ポイント |
山の解説 - [出典:Wikipedia]
大山(だいせん)は、日本の鳥取県にある標高1,729メートルの山。成層火山であるが、活火山としては扱われていない。日本百名山や日本百景にも選定され、鳥取県のシンボルの一つとされている。大山は中国山地の連なりからやや北に離れた位置にある独立峰の火山で、その裾野は日本海に達しており主峰の剣ヶ峰や三鈷峰、烏ヶ山や船上山などの峰を持つ。山体は東西約35キロメートル、南北約30キロメートル、総体積約120立方キロメートル。日本列島におけるデイサイト質火山の中でも最大級の規模である。
広義には南東側に連なる擬宝珠山・蒜山(上蒜山、中蒜山、下蒜山)・皆ヶ山などの蒜山火山群。
最高点は剣ヶ峰であるが、剣ヶ峰に至る縦走路が危険であることから古くから第二峰の弥山(みせん 1,709メートル)で祭事が行われたことから、一般には弥山を頂上としている。
一帯は大山隠岐国立公園に指定されており、標高800メートルから1,300メートルは西日本最大のブナ林に覆われ、その上部には亜高山針葉樹林帯がなく低木林や草原の高山帯になっている。山頂付近に見られるダイセンキャラボクの純林は国の特別天然記念物に指定されている。また、国の鳥獣保護区(大規模生息地)に指定されている(面積5,156 ha、うち特別保護地区2,266 ha)。
周辺の地域では古くから大山信仰が根強い。現存する最古の記述は『出雲国風土記』の国引き神話で、「島根半島を引き寄せた縄を繋ぎ固めるために立てた杭が石見国の三瓶山とこの大山である」とされている。
弥生時代には強力な神が住む霊峰とされ、仏教伝来後、山腹に建立された大山寺は山岳信仰や道教も採り入れながら真言宗の信仰の地として多くの修行者が訪れた。その後、大山寺は865年に宗旨が改められ天台宗別格本山角磐山大山寺として指定された。
大山は古くから修験道や仏教の修行地とされたが女人禁制とはされず、14世紀中頃に成立したとされる『大山寺縁起』では男女や身分の違いなく修行できると記されている。ただ、金門から上の地域は一般の入山が制限され、特に江戸時代には年1回の弥山禅定の儀式に大山寺の僧侶2名と先達3名しか登ることが認められなかった(大山寺の僧侶はすべて男性だったため、この山域に実質的に女性が入ることはなかった)。また、江戸時代には男女を問わず遭難者が多発しており、旧暦11月24日から2月15日まで期間は女性の大山寺参拝は禁止されていた。
明治時代になると廃仏毀釈が実施され、1875年(明治8年)には大山寺の寺号が廃絶されて寺領も多くが没収された。1903年(明治36年)に大山寺の寺号は復活したものの、42あった僧房は10となった。
大山山麓は昭和初期から開拓が始まったが因伯牛の放牧地が広がり土地利用は低位であった。1941年(昭和16年)からは旧日光村の標高600メートル付近の400町歩で松江刑務所の受刑者による開拓作業が始まったが十分な成果は得られなかった。戦後、満州からの引き揚げ者などが入植し始めると開拓域は標高1000メートル付近にまで広がった。
山頂を保護するための取り組みとして、登山時に石を1つリュックに入れて登山し山頂に置いて下山するという「一木一石運動」が、1985年(昭和60年)に結成された「大山の頂上を保護する会」によって行われている。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
「剣ヶ峰」 に関連する記録(最新10件)
大山・蒜山
76 41 2
2025年07月26日(日帰り)



 剣ヶ峰の山行記録へ
剣ヶ峰の山行記録へ

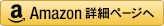











 Loading...
Loading...

