 丹生橋より九度山駅寄りにあるこの駐車場から出発します。ここは18時閉鎖。もっと慈尊院寄りにはより使いやすい駐車場もありました【九度山駐車場にて】
丹生橋より九度山駅寄りにあるこの駐車場から出発します。ここは18時閉鎖。もっと慈尊院寄りにはより使いやすい駐車場もありました【九度山駐車場にて】
2021年08月21日 09:26撮影 by
�,
 1
1
8/21 9:26
丹生橋より九度山駅寄りにあるこの駐車場から出発します。ここは18時閉鎖。もっと慈尊院寄りにはより使いやすい駐車場もありました【九度山駐車場にて】
 小さな標示を頼りに慈尊院を目指します【九度山駐車場〜慈尊院】
小さな標示を頼りに慈尊院を目指します【九度山駐車場〜慈尊院】
2021年08月21日 09:34撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:34
小さな標示を頼りに慈尊院を目指します【九度山駐車場〜慈尊院】
 趣ある入口です【慈尊院にて】
趣ある入口です【慈尊院にて】
2021年08月21日 09:39撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:39
趣ある入口です【慈尊院にて】
 塔の左手に見える石段が、町石道の入口です【慈尊院にて】
塔の左手に見える石段が、町石道の入口です【慈尊院にて】
2021年08月21日 09:39撮影 by
�,
 1
1
8/21 9:39
塔の左手に見える石段が、町石道の入口です【慈尊院にて】
 まずは本堂で道中安全を祈願します【慈尊院にて】
まずは本堂で道中安全を祈願します【慈尊院にて】
2021年08月21日 09:41撮影 by
�,
 1
1
8/21 9:41
まずは本堂で道中安全を祈願します【慈尊院にて】
 石段へ。上にある丹生官省符神社が案内されています【慈尊院にて】
石段へ。上にある丹生官省符神社が案内されています【慈尊院にて】
2021年08月21日 09:42撮影 by
�,
 1
1
8/21 9:42
石段へ。上にある丹生官省符神社が案内されています【慈尊院にて】
 中間の踊り場に百八十町石があります【慈尊院〜丹生官省符神社】
中間の踊り場に百八十町石があります【慈尊院〜丹生官省符神社】
2021年08月21日 09:42撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:42
中間の踊り場に百八十町石があります【慈尊院〜丹生官省符神社】
 神社前を通ります。ここでもお参り【丹生官省符神社にて】
神社前を通ります。ここでもお参り【丹生官省符神社にて】
2021年08月21日 09:44撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:44
神社前を通ります。ここでもお参り【丹生官省符神社にて】
 次は…石と分かりやすく案内されていますが、それはここ限りでした【丹生官省符神社〜展望台】
次は…石と分かりやすく案内されていますが、それはここ限りでした【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 09:45撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:45
次は…石と分かりやすく案内されていますが、それはここ限りでした【丹生官省符神社〜展望台】
 神社出てすぐに百七十九が出現。一町=約109mですから、約100mごとには現れます【丹生官省符神社〜展望台】
神社出てすぐに百七十九が出現。一町=約109mですから、約100mごとには現れます【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 09:46撮影 by
�,
 1
1
8/21 9:46
神社出てすぐに百七十九が出現。一町=約109mですから、約100mごとには現れます【丹生官省符神社〜展望台】
 しばらく進んで農道横断地点。そこに道の解説板がありました【丹生官省符神社〜展望台】
しばらく進んで農道横断地点。そこに道の解説板がありました【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 09:54撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:54
しばらく進んで農道横断地点。そこに道の解説板がありました【丹生官省符神社〜展望台】
 こんな立派な道を渡ります【丹生官省符神社〜展望台】
こんな立派な道を渡ります【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 09:54撮影 by
�,
 0
0
8/21 9:54
こんな立派な道を渡ります【丹生官省符神社〜展望台】
 竹林の中をゆるく登っていきます【丹生官省符神社〜展望台】
竹林の中をゆるく登っていきます【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 09:56撮影 by
�,
 1
1
8/21 9:56
竹林の中をゆるく登っていきます【丹生官省符神社〜展望台】
 路面を見ると雨後であることがよくわかります。しかし、このときは降ってはいません【丹生官省符神社〜展望台】
路面を見ると雨後であることがよくわかります。しかし、このときは降ってはいません【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 10:01撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:01
路面を見ると雨後であることがよくわかります。しかし、このときは降ってはいません【丹生官省符神社〜展望台】
 柿園の中を登ります。町石も道よりもずいぶん高いところに置かれています【丹生官省符神社〜展望台】
柿園の中を登ります。町石も道よりもずいぶん高いところに置かれています【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 10:08撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:08
柿園の中を登ります。町石も道よりもずいぶん高いところに置かれています【丹生官省符神社〜展望台】
 展望台と聞くと行ってみたくなります【丹生官省符神社〜展望台】
展望台と聞くと行ってみたくなります【丹生官省符神社〜展望台】
2021年08月21日 10:09撮影 by
�,
 0
0
8/21 10:09
展望台と聞くと行ってみたくなります【丹生官省符神社〜展望台】
 柿の木の先には先ほど越えた農道、遠くにはまだ雲の多い山並みが見えています【展望台にて】
柿の木の先には先ほど越えた農道、遠くにはまだ雲の多い山並みが見えています【展望台にて】
2021年08月21日 10:09撮影 by
�,
 0
0
8/21 10:09
柿の木の先には先ほど越えた農道、遠くにはまだ雲の多い山並みが見えています【展望台にて】
 柿の木が並ぶ先に橋本方面の市街が見えます【展望台にて】
柿の木が並ぶ先に橋本方面の市街が見えます【展望台にて】
2021年08月21日 10:10撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:10
柿の木が並ぶ先に橋本方面の市街が見えます【展望台にて】
 振り返って撮影)柿園の中を気分よく進む道を登っていきます【展望台〜笠取峠】
振り返って撮影)柿園の中を気分よく進む道を登っていきます【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:15撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:15
振り返って撮影)柿園の中を気分よく進む道を登っていきます【展望台〜笠取峠】
 柿園を過ぎると、山道らしくなってきます【展望台〜笠取峠】
柿園を過ぎると、山道らしくなってきます【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:22撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:22
柿園を過ぎると、山道らしくなってきます【展望台〜笠取峠】
 コースを外れて少々のところに榧蒔石があります【展望台〜笠取峠】
コースを外れて少々のところに榧蒔石があります【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:26撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:26
コースを外れて少々のところに榧蒔石があります【展望台〜笠取峠】
 銭壷石とのこと。傍らの石のことなのか、その石には賽銭が多数【展望台〜笠取峠】
銭壷石とのこと。傍らの石のことなのか、その石には賽銭が多数【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:28撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:28
銭壷石とのこと。傍らの石のことなのか、その石には賽銭が多数【展望台〜笠取峠】
 百五十六町石です【展望台〜笠取峠】
百五十六町石です【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:29撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:29
百五十六町石です【展望台〜笠取峠】
 雨引山への分岐点です。雨引山へと行ってみます【展望台〜笠取峠】
雨引山への分岐点です。雨引山へと行ってみます【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:34撮影 by
�,
 0
0
8/21 10:34
雨引山への分岐点です。雨引山へと行ってみます【展望台〜笠取峠】
 雨引山山頂部です。小さな祠がありますが、やや荒れ気味に見えます【展望台〜笠取峠】
雨引山山頂部です。小さな祠がありますが、やや荒れ気味に見えます【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:42撮影 by
�,
 0
0
8/21 10:42
雨引山山頂部です。小さな祠がありますが、やや荒れ気味に見えます【展望台〜笠取峠】
 神社の柵も倒れかかっています【展望台〜笠取峠】
神社の柵も倒れかかっています【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:42撮影 by
�,
 0
0
8/21 10:42
神社の柵も倒れかかっています【展望台〜笠取峠】
 手製山名標も吊されています【展望台〜笠取峠】
手製山名標も吊されています【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:42撮影 by
�,
 0
0
8/21 10:42
手製山名標も吊されています【展望台〜笠取峠】
 百四十九町石です。仲良く二基並んでいます【展望台〜笠取峠】
百四十九町石です。仲良く二基並んでいます【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 10:58撮影 by
�,
 1
1
8/21 10:58
百四十九町石です。仲良く二基並んでいます【展望台〜笠取峠】
 弘法大師の石像があります。接待場とのこと【展望台〜笠取峠】
弘法大師の石像があります。接待場とのこと【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 11:01撮影 by
�,
 0
0
8/21 11:01
弘法大師の石像があります。接待場とのこと【展望台〜笠取峠】
 百四十七町石です【展望台〜笠取峠】
百四十七町石です【展望台〜笠取峠】
2021年08月21日 11:02撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:02
百四十七町石です【展望台〜笠取峠】
 百四十二町石です【笠取峠〜二ツ鳥居】
百四十二町石です【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:12撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:12
百四十二町石です【笠取峠〜二ツ鳥居】
 わかりにくいですが、この辺りは沢状になっています。水流の中を進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
わかりにくいですが、この辺りは沢状になっています。水流の中を進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:16撮影 by
�,
 0
0
8/21 11:16
わかりにくいですが、この辺りは沢状になっています。水流の中を進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
 六本杉峠です。大きな標示の通り、三谷坂が合流。本コースも左手に90度以上曲がって進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
六本杉峠です。大きな標示の通り、三谷坂が合流。本コースも左手に90度以上曲がって進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:21撮影 by
�,
 0
0
8/21 11:21
六本杉峠です。大きな標示の通り、三谷坂が合流。本コースも左手に90度以上曲がって進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
 ここだけ町石の格好が違います【笠取峠〜二ツ鳥居】
ここだけ町石の格好が違います【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:23撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:23
ここだけ町石の格好が違います【笠取峠〜二ツ鳥居】
 百三十三町石で小都知の峯を経由する道が分かれます。町石道を行きたいので、巻き道方向へと進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
百三十三町石で小都知の峯を経由する道が分かれます。町石道を行きたいので、巻き道方向へと進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:27撮影 by
�,
 0
0
8/21 11:27
百三十三町石で小都知の峯を経由する道が分かれます。町石道を行きたいので、巻き道方向へと進みます【笠取峠〜二ツ鳥居】
 こちらはこちらで町石が続きます【笠取峠〜二ツ鳥居】
こちらはこちらで町石が続きます【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:32撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:32
こちらはこちらで町石が続きます【笠取峠〜二ツ鳥居】
 百廿六町石です。”廿”という漢字がいいです【笠取峠〜二ツ鳥居】
百廿六町石です。”廿”という漢字がいいです【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:37撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:37
百廿六町石です。”廿”という漢字がいいです【笠取峠〜二ツ鳥居】
 百廿六町石です。割れていますが、くっつけてあるようです【笠取峠〜二ツ鳥居】
百廿六町石です。割れていますが、くっつけてあるようです【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:39撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:39
百廿六町石です。割れていますが、くっつけてあるようです【笠取峠〜二ツ鳥居】
 古峠に到着です。百二十四町石もあります【笠取峠〜二ツ鳥居】
古峠に到着です。百二十四町石もあります【笠取峠〜二ツ鳥居】
2021年08月21日 11:40撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:40
古峠に到着です。百二十四町石もあります【笠取峠〜二ツ鳥居】
 その先二ツ鳥居にあずまやがあります。ここで昼食にします【二ツ鳥居にて】
その先二ツ鳥居にあずまやがあります。ここで昼食にします【二ツ鳥居にて】
2021年08月21日 11:45撮影 by
�,
 0
0
8/21 11:45
その先二ツ鳥居にあずまやがあります。ここで昼食にします【二ツ鳥居にて】
 西面が展望できます。山間の集落などが見下ろせます【二ツ鳥居にて】
西面が展望できます。山間の集落などが見下ろせます【二ツ鳥居にて】
2021年08月21日 11:56撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:56
西面が展望できます。山間の集落などが見下ろせます【二ツ鳥居にて】
 目の前に二ツ鳥居があります。【二ツ鳥居にて】
目の前に二ツ鳥居があります。【二ツ鳥居にて】
2021年08月21日 11:57撮影 by
�,
 0
0
8/21 11:57
目の前に二ツ鳥居があります。【二ツ鳥居にて】
 百十八町石です。最近のもののようです。梵字が気になります【二ツ鳥居〜矢立】
百十八町石です。最近のもののようです。梵字が気になります【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 11:59撮影 by
�,
 1
1
8/21 11:59
百十八町石です。最近のもののようです。梵字が気になります【二ツ鳥居〜矢立】
 白蛇の岩です【二ツ鳥居〜矢立】
白蛇の岩です【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:04撮影 by
�,
 0
0
8/21 12:04
白蛇の岩です【二ツ鳥居〜矢立】
 振り返って撮影)右手から降りてきました。左手から来る道はゴルフ場からの道です。背後、この先に進むとティーグラウンドが隣接していました【二ツ鳥居〜矢立】
振り返って撮影)右手から降りてきました。左手から来る道はゴルフ場からの道です。背後、この先に進むとティーグラウンドが隣接していました【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:08撮影 by
�,
 0
0
8/21 12:08
振り返って撮影)右手から降りてきました。左手から来る道はゴルフ場からの道です。背後、この先に進むとティーグラウンドが隣接していました【二ツ鳥居〜矢立】
 その先で神田地蔵堂です【二ツ鳥居〜矢立】
その先で神田地蔵堂です【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:10撮影 by
�,
 1
1
8/21 12:10
その先で神田地蔵堂です【二ツ鳥居〜矢立】
 百七町石です【二ツ鳥居〜矢立】
百七町石です【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:17撮影 by
�,
 1
1
8/21 12:17
百七町石です【二ツ鳥居〜矢立】
 百二町石です。時折横の樹間にはゴルフ場が見えます【二ツ鳥居〜矢立】
百二町石です。時折横の樹間にはゴルフ場が見えます【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:23撮影 by
�,
 1
1
8/21 12:23
百二町石です。時折横の樹間にはゴルフ場が見えます【二ツ鳥居〜矢立】
 九十六町石です。結構大ぶりです【二ツ鳥居〜矢立】
九十六町石です。結構大ぶりです【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:31撮影 by
�,
 1
1
8/21 12:31
九十六町石です。結構大ぶりです【二ツ鳥居〜矢立】
 笠木峠に着きました。ここからも上古沢駅へのエスケープがあります【二ツ鳥居〜矢立】
笠木峠に着きました。ここからも上古沢駅へのエスケープがあります【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 12:45撮影 by
�,
 0
0
8/21 12:45
笠木峠に着きました。ここからも上古沢駅へのエスケープがあります【二ツ鳥居〜矢立】
 七十五または七十六です。左面は「右 七十六」とも読めますので。よくわかりません【二ツ鳥居〜矢立】
七十五または七十六です。左面は「右 七十六」とも読めますので。よくわかりません【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 13:01撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:01
七十五または七十六です。左面は「右 七十六」とも読めますので。よくわかりません【二ツ鳥居〜矢立】
 七十二町石です。いよいよ残りは4割です【二ツ鳥居〜矢立】
七十二町石です。いよいよ残りは4割です【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 13:06撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:06
七十二町石です。いよいよ残りは4割です【二ツ鳥居〜矢立】
 七十町石です【二ツ鳥居〜矢立】
七十町石です【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 13:09撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:09
七十町石です【二ツ鳥居〜矢立】
 六十一町石です。ここからずっと下降して矢立峠に着きます【二ツ鳥居〜矢立】
六十一町石です。ここからずっと下降して矢立峠に着きます【二ツ鳥居〜矢立】
2021年08月21日 13:21撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:21
六十一町石です。ここからずっと下降して矢立峠に着きます【二ツ鳥居〜矢立】
 峠でいったん車道に顔を出します【矢立にて】
峠でいったん車道に顔を出します【矢立にて】
2021年08月21日 13:22撮影 by
�,
 0
0
8/21 13:22
峠でいったん車道に顔を出します【矢立にて】
 目の前には茶屋が見えます【矢立にて】
目の前には茶屋が見えます【矢立にて】
2021年08月21日 13:22撮影 by
�,
 0
0
8/21 13:22
目の前には茶屋が見えます【矢立にて】
 茶屋に向かう途中には、六十町石があります【矢立にて】
茶屋に向かう途中には、六十町石があります【矢立にて】
2021年08月21日 13:24撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:24
茶屋に向かう途中には、六十町石があります【矢立にて】
 名物やきもち食べたくもあり。クルマでも来れるようなので、次回の楽しみとしました【矢立にて】
名物やきもち食べたくもあり。クルマでも来れるようなので、次回の楽しみとしました【矢立にて】
2021年08月21日 13:33撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:33
名物やきもち食べたくもあり。クルマでも来れるようなので、次回の楽しみとしました【矢立にて】
 五十町坂の入口には、道標代わりの石標があります。こういった石標もあり、全部で216の道標が建っているようです【矢立にて】
五十町坂の入口には、道標代わりの石標があります。こういった石標もあり、全部で216の道標が建っているようです【矢立にて】
2021年08月21日 13:36撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:36
五十町坂の入口には、道標代わりの石標があります。こういった石標もあり、全部で216の道標が建っているようです【矢立にて】
 ”袈裟掛石”とのこと。時代劇の太刀合わせしか浮かびません【矢立〜大門】
”袈裟掛石”とのこと。時代劇の太刀合わせしか浮かびません【矢立〜大門】
2021年08月21日 13:42撮影 by
�,
 0
0
8/21 13:42
”袈裟掛石”とのこと。時代劇の太刀合わせしか浮かびません【矢立〜大門】
 押上石です。これも弘法大師の謂れがあるようです【矢立〜大門】
押上石です。これも弘法大師の謂れがあるようです【矢立〜大門】
2021年08月21日 13:44撮影 by
�,
 0
0
8/21 13:44
押上石です。これも弘法大師の謂れがあるようです【矢立〜大門】
 ここも仲良く並んでいます【矢立〜大門】
ここも仲良く並んでいます【矢立〜大門】
2021年08月21日 13:46撮影 by
�,
 1
1
8/21 13:46
ここも仲良く並んでいます【矢立〜大門】
 四十五町石でしょうか【矢立〜大門】
四十五町石でしょうか【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:00撮影 by
�,
 1
1
8/21 14:00
四十五町石でしょうか【矢立〜大門】
 ここで国道を横断します。脇には仮設トイレが並びます【矢立〜大門】
ここで国道を横断します。脇には仮設トイレが並びます【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:08撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:08
ここで国道を横断します。脇には仮設トイレが並びます【矢立〜大門】
 横断後も登っていきます【矢立〜大門】
横断後も登っていきます【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:09撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:09
横断後も登っていきます【矢立〜大門】
 登るとここにもあずまやです【矢立〜大門】
登るとここにもあずまやです【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:14撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:14
登るとここにもあずまやです【矢立〜大門】
 遠くには龍門山とのことですが、その辺りにちょうど木が茂っています【矢立〜大門】
遠くには龍門山とのことですが、その辺りにちょうど木が茂っています【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:14撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:14
遠くには龍門山とのことですが、その辺りにちょうど木が茂っています【矢立〜大門】
 国道脇を下降していきます。国道の対岸に四里石があります【矢立〜大門】
国道脇を下降していきます。国道の対岸に四里石があります【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:16撮影 by
�,
 1
1
8/21 14:16
国道脇を下降していきます。国道の対岸に四里石があります【矢立〜大門】
 度々現れますが、谷渡りには石積みが整備されています【矢立〜大門】
度々現れますが、谷渡りには石積みが整備されています【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:20撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:20
度々現れますが、谷渡りには石積みが整備されています【矢立〜大門】
 三十三町石です。傍らには切り株のベンチがあります【矢立〜大門】
三十三町石です。傍らには切り株のベンチがあります【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:22撮影 by
�,
 1
1
8/21 14:22
三十三町石です。傍らには切り株のベンチがあります【矢立〜大門】
 いよいよ三十町石です【矢立〜大門】
いよいよ三十町石です【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:27撮影 by
�,
 1
1
8/21 14:27
いよいよ三十町石です【矢立〜大門】
 鏡石とはこれでしょうか。路傍にも石がありますが、テカリがあるのは斜面上の石です【矢立〜大門】
鏡石とはこれでしょうか。路傍にも石がありますが、テカリがあるのは斜面上の石です【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:32撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:32
鏡石とはこれでしょうか。路傍にも石がありますが、テカリがあるのは斜面上の石です【矢立〜大門】
 山頂部に来て渓流沿いになります。山頂部に平坦地が広がるからこそでしょうか【矢立〜大門】
山頂部に来て渓流沿いになります。山頂部に平坦地が広がるからこそでしょうか【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:34撮影 by
�,
 0
0
8/21 14:34
山頂部に来て渓流沿いになります。山頂部に平坦地が広がるからこそでしょうか【矢立〜大門】
 二十町石です【矢立〜大門】
二十町石です【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:46撮影 by
�,
 1
1
8/21 14:46
二十町石です【矢立〜大門】
 十三町石でしょうか。この先で小雨を受け、雨具準備をすることになります【矢立〜大門】
十三町石でしょうか。この先で小雨を受け、雨具準備をすることになります【矢立〜大門】
2021年08月21日 14:57撮影 by
�,
 1
1
8/21 14:57
十三町石でしょうか。この先で小雨を受け、雨具準備をすることになります【矢立〜大門】
 最後の急坂を登り切ると、大門が眼前に現れます【大門にて】
最後の急坂を登り切ると、大門が眼前に現れます【大門にて】
2021年08月21日 15:17撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:17
最後の急坂を登り切ると、大門が眼前に現れます【大門にて】
 振り返って撮影)ここから顔を出しました【大門にて】
振り返って撮影)ここから顔を出しました【大門にて】
2021年08月21日 15:17撮影 by
�,
 0
0
8/21 15:17
振り返って撮影)ここから顔を出しました【大門にて】
 仁王像の吽形です【大門にて】
仁王像の吽形です【大門にて】
2021年08月21日 15:20撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:20
仁王像の吽形です【大門にて】
 阿形です【大門にて】
阿形です【大門にて】
2021年08月21日 15:21撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:21
阿形です【大門にて】
 六町石が大門の背後にあります【大門にて】
六町石が大門の背後にあります【大門にて】
2021年08月21日 15:21撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:21
六町石が大門の背後にあります【大門にて】
 門前町とは言わないでしょうが、大門から金堂へと続く道を見ます【大門〜千手橋BS】
門前町とは言わないでしょうが、大門から金堂へと続く道を見ます【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:23撮影 by
�,
 0
0
8/21 15:23
門前町とは言わないでしょうが、大門から金堂へと続く道を見ます【大門〜千手橋BS】
 四町石が路傍にあります。いくつも飛び抜かしているようです【大門〜千手橋BS】
四町石が路傍にあります。いくつも飛び抜かしているようです【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:24撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:24
四町石が路傍にあります。いくつも飛び抜かしているようです【大門〜千手橋BS】
 金堂です【大門〜千手橋BS】
金堂です【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:29撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:29
金堂です【大門〜千手橋BS】
 根本大塔です【大門〜千手橋BS】
根本大塔です【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:46撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:46
根本大塔です【大門〜千手橋BS】
 戻って一町石を探します。まず看板を見つけましたが、石が見当たりません【大門〜千手橋BS】
戻って一町石を探します。まず看板を見つけましたが、石が見当たりません【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:48撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:48
戻って一町石を探します。まず看板を見つけましたが、石が見当たりません【大門〜千手橋BS】
 見逃していた「一町石」を発見しました。金堂境内側にありました【大門〜千手橋BS】
見逃していた「一町石」を発見しました。金堂境内側にありました【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:50撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:50
見逃していた「一町石」を発見しました。金堂境内側にありました【大門〜千手橋BS】
 金剛峯寺にも立ち寄ります【大門〜千手橋BS】
金剛峯寺にも立ち寄ります【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:59撮影 by
�,
 1
1
8/21 15:59
金剛峯寺にも立ち寄ります【大門〜千手橋BS】
 境内です【大門〜千手橋BS】
境内です【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 15:59撮影 by
�,
 0
0
8/21 15:59
境内です【大門〜千手橋BS】
 バスが来ました【大門〜千手橋BS】
バスが来ました【大門〜千手橋BS】
2021年08月21日 16:14撮影 by
�,
 1
1
8/21 16:14
バスが来ました【大門〜千手橋BS】
 まずはケーブルカーで降ります【高野山駅にて】
まずはケーブルカーで降ります【高野山駅にて】
2021年08月21日 16:29撮影 by
�,
 1
1
8/21 16:29
まずはケーブルカーで降ります【高野山駅にて】
 極楽橋駅の中。ドレスアップされています。ケーブルカーから電車には改札くぐらずにで乗り換えです【極楽橋駅にて】
極楽橋駅の中。ドレスアップされています。ケーブルカーから電車には改札くぐらずにで乗り換えです【極楽橋駅にて】
2021年08月21日 16:39撮影 by
�,
 1
1
8/21 16:39
極楽橋駅の中。ドレスアップされています。ケーブルカーから電車には改札くぐらずにで乗り換えです【極楽橋駅にて】
 南海の山岳区間ワンマン列車。こうや花鉄道の愛称があるようです【極楽橋駅にて】
南海の山岳区間ワンマン列車。こうや花鉄道の愛称があるようです【極楽橋駅にて】
2021年08月21日 16:41撮影 by
�,
 1
1
8/21 16:41
南海の山岳区間ワンマン列車。こうや花鉄道の愛称があるようです【極楽橋駅にて】
 九度山駅に到着しました。真田六文銭が目立ちます。ここから駐車場に歩いて、今日は終了です【極楽橋駅にて】
九度山駅に到着しました。真田六文銭が目立ちます。ここから駐車場に歩いて、今日は終了です【極楽橋駅にて】
2021年08月21日 17:12撮影 by
�,
 1
1
8/21 17:12
九度山駅に到着しました。真田六文銭が目立ちます。ここから駐車場に歩いて、今日は終了です【極楽橋駅にて】



 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手










































































































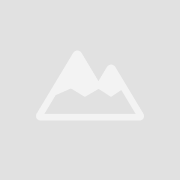





いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する