 池袋東口を出発
池袋東口を出発
 0
0
3/19 11:00
池袋東口を出発
 サンシャイン60通りはたいへんな賑わい
サンシャイン60通りはたいへんな賑わい
 0
0
3/19 11:06
サンシャイン60通りはたいへんな賑わい
 サンシャイン60を右に見つつ春日通りに向かう
サンシャイン60を右に見つつ春日通りに向かう
 0
0
3/19 11:11
サンシャイン60を右に見つつ春日通りに向かう
 帝京平成大池袋キャンパス前にポツンと子育て地蔵尊。詳細不明
帝京平成大池袋キャンパス前にポツンと子育て地蔵尊。詳細不明
 0
0
3/19 11:15
帝京平成大池袋キャンパス前にポツンと子育て地蔵尊。詳細不明
 その先の角を右に入り、JR山手線を宮仲橋で渡ります
その先の角を右に入り、JR山手線を宮仲橋で渡ります
 0
0
3/19 11:21
その先の角を右に入り、JR山手線を宮仲橋で渡ります
 明治通りに入り、旧中山道との交差点手前の公園は千川上水調整池跡
明治通りに入り、旧中山道との交差点手前の公園は千川上水調整池跡
 0
0
3/19 11:37
明治通りに入り、旧中山道との交差点手前の公園は千川上水調整池跡
 千川上水は元禄九年(1696)江戸市民の飲料水として玉川上水を分水したもの。詳細は写真を
千川上水は元禄九年(1696)江戸市民の飲料水として玉川上水を分水したもの。詳細は写真を
 0
0
3/19 11:37
千川上水は元禄九年(1696)江戸市民の飲料水として玉川上水を分水したもの。詳細は写真を
 今でも公園地下に沈殿池があり、六義園に水を供給しているそうです
今でも公園地下に沈殿池があり、六義園に水を供給しているそうです
 0
0
3/19 11:38
今でも公園地下に沈殿池があり、六義園に水を供給しているそうです
 明治通りを挟んで「千川上水分配堰碑」が立っています
明治通りを挟んで「千川上水分配堰碑」が立っています
 0
0
3/19 11:44
明治通りを挟んで「千川上水分配堰碑」が立っています
 西巣鴨交差点で中山道を渡り、ガソリンスタンド裏手の八幡通り商店会が旧街道
西巣鴨交差点で中山道を渡り、ガソリンスタンド裏手の八幡通り商店会が旧街道
 0
0
3/19 11:53
西巣鴨交差点で中山道を渡り、ガソリンスタンド裏手の八幡通り商店会が旧街道
 商店会の奥には滝野川八幡神社が鎮座。創建は建仁二年(1202)。文治五年(1189)に頼朝が勧請との伝承も
商店会の奥には滝野川八幡神社が鎮座。創建は建仁二年(1202)。文治五年(1189)に頼朝が勧請との伝承も
 0
0
3/19 12:32
商店会の奥には滝野川八幡神社が鎮座。創建は建仁二年(1202)。文治五年(1189)に頼朝が勧請との伝承も
 八幡神社先を左に進むと四本木稲荷神社。かつて東京砲兵工廠銃包製造所の構内社であった四本木稲荷神社を分祀したものとか
八幡神社先を左に進むと四本木稲荷神社。かつて東京砲兵工廠銃包製造所の構内社であった四本木稲荷神社を分祀したものとか
 0
0
3/19 12:41
八幡神社先を左に進むと四本木稲荷神社。かつて東京砲兵工廠銃包製造所の構内社であった四本木稲荷神社を分祀したものとか
 入口にあった四本木詣の作法では、清め壺に心のわだかまりを吐いてからお参りするようです
入口にあった四本木詣の作法では、清め壺に心のわだかまりを吐いてからお参りするようです
 0
0
3/19 12:46
入口にあった四本木詣の作法では、清め壺に心のわだかまりを吐いてからお参りするようです
 四本木稲荷神社は、敷地内の小社を改修したもので、製造所の工事に伴って古墳を壊したことの祟りを恐れたものとか
四本木稲荷神社は、敷地内の小社を改修したもので、製造所の工事に伴って古墳を壊したことの祟りを恐れたものとか
 0
0
3/19 12:42
四本木稲荷神社は、敷地内の小社を改修したもので、製造所の工事に伴って古墳を壊したことの祟りを恐れたものとか
 音無もみじ緑地公園を抜けて、旧街道沿いの金剛寺に向かいます
音無もみじ緑地公園を抜けて、旧街道沿いの金剛寺に向かいます
 0
0
3/19 12:51
音無もみじ緑地公園を抜けて、旧街道沿いの金剛寺に向かいます
 ここは『江戸名所図会』に描かれた「松橋弁財天窟 石神井川」。崖下の岩屋の中には、弘法大師の作と伝わる弁財天像がまつられていたとか
ここは『江戸名所図会』に描かれた「松橋弁財天窟 石神井川」。崖下の岩屋の中には、弘法大師の作と伝わる弁財天像がまつられていたとか
 0
0
3/19 12:53
ここは『江戸名所図会』に描かれた「松橋弁財天窟 石神井川」。崖下の岩屋の中には、弘法大師の作と伝わる弁財天像がまつられていたとか
 金剛寺は、源頼朝が武蔵国へ攻め入る時には陣をはった場所と云われ、八代将軍吉宗の命により楓が植樹され「紅葉寺」とも呼ばれているとか
金剛寺は、源頼朝が武蔵国へ攻め入る時には陣をはった場所と云われ、八代将軍吉宗の命により楓が植樹され「紅葉寺」とも呼ばれているとか
 0
0
3/19 12:58
金剛寺は、源頼朝が武蔵国へ攻め入る時には陣をはった場所と云われ、八代将軍吉宗の命により楓が植樹され「紅葉寺」とも呼ばれているとか
 山門横の石仏石塔。右端の板碑型庚申塔は貞享元年(1684)、中央は角柱型の石仏で寛政十年(1798)、左端の西国三十三所供養塔は寛政九年(1797)のもの
山門横の石仏石塔。右端の板碑型庚申塔は貞享元年(1684)、中央は角柱型の石仏で寛政十年(1798)、左端の西国三十三所供養塔は寛政九年(1797)のもの
 0
0
3/19 12:56
山門横の石仏石塔。右端の板碑型庚申塔は貞享元年(1684)、中央は角柱型の石仏で寛政十年(1798)、左端の西国三十三所供養塔は寛政九年(1797)のもの
 境内には冨士講の先達として活躍した安藤冨五郎の顕彰碑もありました
境内には冨士講の先達として活躍した安藤冨五郎の顕彰碑もありました
 0
0
3/19 12:59
境内には冨士講の先達として活躍した安藤冨五郎の顕彰碑もありました
 紅葉橋を渡り、旧街道を赤羽に向かいます
紅葉橋を渡り、旧街道を赤羽に向かいます
 0
0
3/19 13:01
紅葉橋を渡り、旧街道を赤羽に向かいます
 途中、王子稲荷神社に立寄り。治承四年(1180)には、源頼朝が義家の鎧や薙刀等を奉納したと伝わる。現在の社殿は、徳川第十一代将軍家斉の寄進とか
途中、王子稲荷神社に立寄り。治承四年(1180)には、源頼朝が義家の鎧や薙刀等を奉納したと伝わる。現在の社殿は、徳川第十一代将軍家斉の寄進とか
 0
0
3/19 13:15
途中、王子稲荷神社に立寄り。治承四年(1180)には、源頼朝が義家の鎧や薙刀等を奉納したと伝わる。現在の社殿は、徳川第十一代将軍家斉の寄進とか
 ご近所の名主の滝にも寄り道。こちらは落差8mの男滝
ご近所の名主の滝にも寄り道。こちらは落差8mの男滝
 0
0
3/19 13:23
ご近所の名主の滝にも寄り道。こちらは落差8mの男滝
 三平坂を上って旧街道に復帰すると、三叉路の桜の下に二塔の石塔
三平坂を上って旧街道に復帰すると、三叉路の桜の下に二塔の石塔
 0
0
3/19 13:36
三平坂を上って旧街道に復帰すると、三叉路の桜の下に二塔の石塔
 日光御成道と合流してすぐ、左に地福寺。京都仁和寺の僧侶が、源頼義の奥州征伐に随行した際この地に留まり、康平年間(1058〜1064)に創建したという
日光御成道と合流してすぐ、左に地福寺。京都仁和寺の僧侶が、源頼義の奥州征伐に随行した際この地に留まり、康平年間(1058〜1064)に創建したという
 0
0
3/19 13:45
日光御成道と合流してすぐ、左に地福寺。京都仁和寺の僧侶が、源頼義の奥州征伐に随行した際この地に留まり、康平年間(1058〜1064)に創建したという
 山門の六地蔵は、どれも大きさが異なっていて珍しい。一番左の地蔵菩薩像は「鎌倉街道の地蔵様」と呼ばれるもので実は庚申塔だとか
山門の六地蔵は、どれも大きさが異なっていて珍しい。一番左の地蔵菩薩像は「鎌倉街道の地蔵様」と呼ばれるもので実は庚申塔だとか
 0
0
3/19 13:45
山門の六地蔵は、どれも大きさが異なっていて珍しい。一番左の地蔵菩薩像は「鎌倉街道の地蔵様」と呼ばれるもので実は庚申塔だとか
 境内の桜は「太閤千代しだれ」。秀吉が花見の茶会を催した京都・醍醐次の桜を組織培養で蘇らせたものだそうです
境内の桜は「太閤千代しだれ」。秀吉が花見の茶会を催した京都・醍醐次の桜を組織培養で蘇らせたものだそうです
 0
0
3/19 13:47
境内の桜は「太閤千代しだれ」。秀吉が花見の茶会を催した京都・醍醐次の桜を組織培養で蘇らせたものだそうです
 十条富士塚は道路拡張のためか工事中。新たに令和の富士塚がお目見えするようです
十条富士塚は道路拡張のためか工事中。新たに令和の富士塚がお目見えするようです
 0
0
3/19 13:52
十条富士塚は道路拡張のためか工事中。新たに令和の富士塚がお目見えするようです
 その先、右に西音寺。文明ニ年(1470)開山といわれる古刹で、徳川家光も日光社参の折、この寺で休憩したという
その先、右に西音寺。文明ニ年(1470)開山といわれる古刹で、徳川家光も日光社参の折、この寺で休憩したという
 0
0
3/19 13:58
その先、右に西音寺。文明ニ年(1470)開山といわれる古刹で、徳川家光も日光社参の折、この寺で休憩したという
 山門前に笠つき高さ1.3mほど六面搭。各面に立姿の地蔵を一尊ずつ浮彫し、その上に弥陀と観音、勢至の三尊を三面に一体ずつを浮き彫りにした珍しいもの
山門前に笠つき高さ1.3mほど六面搭。各面に立姿の地蔵を一尊ずつ浮彫し、その上に弥陀と観音、勢至の三尊を三面に一体ずつを浮き彫りにした珍しいもの
 0
0
3/19 13:58
山門前に笠つき高さ1.3mほど六面搭。各面に立姿の地蔵を一尊ずつ浮彫し、その上に弥陀と観音、勢至の三尊を三面に一体ずつを浮き彫りにした珍しいもの
 環七通りの交差点角には八雲神社。寛政8年(1796)の創建とされ、明治の神仏分離政策前は神仏習合による牛頭天王を祀る「牛頭天王社」であったそうです
環七通りの交差点角には八雲神社。寛政8年(1796)の創建とされ、明治の神仏分離政策前は神仏習合による牛頭天王を祀る「牛頭天王社」であったそうです
 0
0
3/19 14:03
環七通りの交差点角には八雲神社。寛政8年(1796)の創建とされ、明治の神仏分離政策前は神仏習合による牛頭天王を祀る「牛頭天王社」であったそうです
 清水坂で武蔵野台地を緩やかに下って行きます
清水坂で武蔵野台地を緩やかに下って行きます
 0
0
3/19 14:07
清水坂で武蔵野台地を緩やかに下って行きます
 JR埼京線のガードをくぐり、右の坂を上ると法真寺の題目塔が立っています
JR埼京線のガードをくぐり、右の坂を上ると法真寺の題目塔が立っています
 0
0
3/19 14:17
JR埼京線のガードをくぐり、右の坂を上ると法真寺の題目塔が立っています
 その坂の途中、右の長い階段を上り、香取神社を参拝
その坂の途中、右の長い階段を上り、香取神社を参拝
 0
0
3/19 14:19
その坂の途中、右の長い階段を上り、香取神社を参拝
 香取神社の創建は不明ですが、本殿は三代将軍家光公により慶安三年(1650)に上野東照宮の旧本殿を移築したものと云われます
香取神社の創建は不明ですが、本殿は三代将軍家光公により慶安三年(1650)に上野東照宮の旧本殿を移築したものと云われます
 0
0
3/19 14:20
香取神社の創建は不明ですが、本殿は三代将軍家光公により慶安三年(1650)に上野東照宮の旧本殿を移築したものと云われます
 境内には、七つの力石が並び、五つの力石にはそれぞれ十九貫目(約71Kg)から五十五貫目(約206Kg)の重さと「小川留五郎」と名前が刻まれていました
境内には、七つの力石が並び、五つの力石にはそれぞれ十九貫目(約71Kg)から五十五貫目(約206Kg)の重さと「小川留五郎」と名前が刻まれていました
 0
0
3/19 14:22
境内には、七つの力石が並び、五つの力石にはそれぞれ十九貫目(約71Kg)から五十五貫目(約206Kg)の重さと「小川留五郎」と名前が刻まれていました
 階段を下り坂を上り詰めると法真寺に着きます
階段を下り坂を上り詰めると法真寺に着きます
 0
0
3/19 14:27
階段を下り坂を上り詰めると法真寺に着きます
 法真寺は天正元年(1573)の開山と伝えられ、慶安二年(1649)には三代将軍家光より十三石二斗の領知朱印状を賜っているとか
法真寺は天正元年(1573)の開山と伝えられ、慶安二年(1649)には三代将軍家光より十三石二斗の領知朱印状を賜っているとか
 0
0
3/19 14:28
法真寺は天正元年(1573)の開山と伝えられ、慶安二年(1649)には三代将軍家光より十三石二斗の領知朱印状を賜っているとか
 鐘撞堂の梵鐘には宝暦七年三月十三日の文字が刻まれていました
鐘撞堂の梵鐘には宝暦七年三月十三日の文字が刻まれていました
 0
0
3/19 14:29
鐘撞堂の梵鐘には宝暦七年三月十三日の文字が刻まれていました
 旧街道に戻り、赤羽に向かうと稲付一里塚の説明板が。稲付一里塚は日本橋から三里目にあたり、この先、200mほどの所にあったそうです
旧街道に戻り、赤羽に向かうと稲付一里塚の説明板が。稲付一里塚は日本橋から三里目にあたり、この先、200mほどの所にあったそうです
 0
0
3/19 14:36
旧街道に戻り、赤羽に向かうと稲付一里塚の説明板が。稲付一里塚は日本橋から三里目にあたり、この先、200mほどの所にあったそうです
 赤羽西派出所から西へ上る真正寺坂の入口にある庚申塔。庚申塔には「これより いたはしみち」と刻まれ、御成道と中山道を結ぶ道となっていたようです
赤羽西派出所から西へ上る真正寺坂の入口にある庚申塔。庚申塔には「これより いたはしみち」と刻まれ、御成道と中山道を結ぶ道となっていたようです
 0
0
3/19 14:37
赤羽西派出所から西へ上る真正寺坂の入口にある庚申塔。庚申塔には「これより いたはしみち」と刻まれ、御成道と中山道を結ぶ道となっていたようです
 さらに真正寺坂の先、左に入る坂の上には竜宮城を思わす普門院の山門が見えます
さらに真正寺坂の先、左に入る坂の上には竜宮城を思わす普門院の山門が見えます
 0
0
3/19 14:41
さらに真正寺坂の先、左に入る坂の上には竜宮城を思わす普門院の山門が見えます
 境内には、ブッダガヤの寺院を模したといわれる納骨堂がありました
境内には、ブッダガヤの寺院を模したといわれる納骨堂がありました
 0
0
3/19 14:43
境内には、ブッダガヤの寺院を模したといわれる納骨堂がありました
 旧街道に戻り、すぐ先を左に上がると稲付城跡。太田道灌が築城したといわれる戦国時代の砦跡で、江戸城と岩槻城を中継するための山城だったそうです
旧街道に戻り、すぐ先を左に上がると稲付城跡。太田道灌が築城したといわれる戦国時代の砦跡で、江戸城と岩槻城を中継するための山城だったそうです
 0
0
3/19 14:49
旧街道に戻り、すぐ先を左に上がると稲付城跡。太田道灌が築城したといわれる戦国時代の砦跡で、江戸城と岩槻城を中継するための山城だったそうです
 現在は、道灌六世の孫太田資宗(1600〜1680)が先祖ゆかりの地を大事にし、境内を整備して静勝寺となっています
現在は、道灌六世の孫太田資宗(1600〜1680)が先祖ゆかりの地を大事にし、境内を整備して静勝寺となっています
 0
0
3/19 14:53
現在は、道灌六世の孫太田資宗(1600〜1680)が先祖ゆかりの地を大事にし、境内を整備して静勝寺となっています
 本堂前の道灌堂があり、厨子内には木造の太田道灌坐像が祀られているそうです
本堂前の道灌堂があり、厨子内には木造の太田道灌坐像が祀られているそうです
 0
0
3/19 14:53
本堂前の道灌堂があり、厨子内には木造の太田道灌坐像が祀られているそうです
 赤羽駅で旧街道は消えますが、駅構内を東口に抜けて、線路際のの道を北へ進みます
赤羽駅で旧街道は消えますが、駅構内を東口に抜けて、線路際のの道を北へ進みます
 0
0
3/19 14:58
赤羽駅で旧街道は消えますが、駅構内を東口に抜けて、線路際のの道を北へ進みます
 突当りの大通り正面に宝幢院。開山は寛正二年(1461)と云われ、家光から朱印を与えられて繁栄したそうです
突当りの大通り正面に宝幢院。開山は寛正二年(1461)と云われ、家光から朱印を与えられて繁栄したそうです
 0
0
3/19 15:13
突当りの大通り正面に宝幢院。開山は寛正二年(1461)と云われ、家光から朱印を与えられて繁栄したそうです
 法幢院前は日光岩槻道と板橋道が合流する交通の要所で、門前に残された道標には「南 江戸道」「東 川口善光寺道 日光岩付道」の文字が読み取れました
法幢院前は日光岩槻道と板橋道が合流する交通の要所で、門前に残された道標には「南 江戸道」「東 川口善光寺道 日光岩付道」の文字が読み取れました
 0
0
3/19 15:12
法幢院前は日光岩槻道と板橋道が合流する交通の要所で、門前に残された道標には「南 江戸道」「東 川口善光寺道 日光岩付道」の文字が読み取れました
 駐車場奥に並ぶ庚申塔。左の板碑型の庚申塔は北区で最古の庚申塔で造立は寛永十六年(1639)。右側の地蔵菩薩立像は延宝八年(1686)の造立といわれます
駐車場奥に並ぶ庚申塔。左の板碑型の庚申塔は北区で最古の庚申塔で造立は寛永十六年(1639)。右側の地蔵菩薩立像は延宝八年(1686)の造立といわれます
 0
0
3/19 15:14
駐車場奥に並ぶ庚申塔。左の板碑型の庚申塔は北区で最古の庚申塔で造立は寛永十六年(1639)。右側の地蔵菩薩立像は延宝八年(1686)の造立といわれます
 本堂前、堂宇の中に並ぶ六地蔵は元文五年(1740)十二月から寛保元年(1741)二月の1年3ヶ月間で造立されたものだそうだ
本堂前、堂宇の中に並ぶ六地蔵は元文五年(1740)十二月から寛保元年(1741)二月の1年3ヶ月間で造立されたものだそうだ
 0
0
3/19 15:15
本堂前、堂宇の中に並ぶ六地蔵は元文五年(1740)十二月から寛保元年(1741)二月の1年3ヶ月間で造立されたものだそうだ
 宝幢院を出て新荒川大橋に向かうと、右手のマンションの植込みの中に「岩槻街道岩淵宿問屋場跡之碑」。岩淵宿は岩槻街道で日本橋から最初の宿場です
宝幢院を出て新荒川大橋に向かうと、右手のマンションの植込みの中に「岩槻街道岩淵宿問屋場跡之碑」。岩淵宿は岩槻街道で日本橋から最初の宿場です
 0
0
3/19 15:24
宝幢院を出て新荒川大橋に向かうと、右手のマンションの植込みの中に「岩槻街道岩淵宿問屋場跡之碑」。岩淵宿は岩槻街道で日本橋から最初の宿場です
 新荒川大橋で荒川を渡り、川口宿へ
新荒川大橋で荒川を渡り、川口宿へ
 0
0
3/19 15:29
新荒川大橋で荒川を渡り、川口宿へ
 途中、荒川土手に下りると、ここは岩淵の渡船場址。源頼朝のもとに奥州から義経が参陣する際、ここを渡ったとか。説明板もここにあります
途中、荒川土手に下りると、ここは岩淵の渡船場址。源頼朝のもとに奥州から義経が参陣する際、ここを渡ったとか。説明板もここにあります
 0
0
3/19 15:31
途中、荒川土手に下りると、ここは岩淵の渡船場址。源頼朝のもとに奥州から義経が参陣する際、ここを渡ったとか。説明板もここにあります
 新荒川大橋を渡り、土手上から見下ろす一本道は川口宿です
新荒川大橋を渡り、土手上から見下ろす一本道は川口宿です
 0
0
3/19 15:46
新荒川大橋を渡り、土手上から見下ろす一本道は川口宿です
 土手下、交差点脇の公園には鎌倉橋の碑があります。小川に架けられた橋で南中学校の中に礎石が残っているそうです
土手下、交差点脇の公園には鎌倉橋の碑があります。小川に架けられた橋で南中学校の中に礎石が残っているそうです
 0
0
3/19 15:47
土手下、交差点脇の公園には鎌倉橋の碑があります。小川に架けられた橋で南中学校の中に礎石が残っているそうです
 川口宿には古い家屋も残されています
川口宿には古い家屋も残されています
 0
0
3/19 15:50
川口宿には古い家屋も残されています
 すぐ先の細い路地を左に入ると旧本陣門。ブロック塀に挟まれ、昔の佇まいはあまり感じられません
すぐ先の細い路地を左に入ると旧本陣門。ブロック塀に挟まれ、昔の佇まいはあまり感じられません
 0
0
3/19 15:52
すぐ先の細い路地を左に入ると旧本陣門。ブロック塀に挟まれ、昔の佇まいはあまり感じられません
 本陣門の先の路地奥には、明治33年(1900)に建てられたレンガ造りの発電所跡が。現在は倉庫として使われているようです
本陣門の先の路地奥には、明治33年(1900)に建てられたレンガ造りの発電所跡が。現在は倉庫として使われているようです
 0
0
3/19 15:57
本陣門の先の路地奥には、明治33年(1900)に建てられたレンガ造りの発電所跡が。現在は倉庫として使われているようです
 静かな川口宿を抜けると突当りに錫杖寺があります
静かな川口宿を抜けると突当りに錫杖寺があります
 0
0
3/19 16:07
静かな川口宿を抜けると突当りに錫杖寺があります
 門前に残された凱旋橋跡は、日露戦争の凱旋祝賀会に際し、錫杖寺杁用水に架設された石造りアーチ型の凱旋橋の遺跡です
門前に残された凱旋橋跡は、日露戦争の凱旋祝賀会に際し、錫杖寺杁用水に架設された石造りアーチ型の凱旋橋の遺跡です
 0
0
3/19 16:07
門前に残された凱旋橋跡は、日露戦争の凱旋祝賀会に際し、錫杖寺杁用水に架設された石造りアーチ型の凱旋橋の遺跡です
 錫杖寺は天平十二年(740)行基による開山。元和八年(1622)二代将軍秀忠の日光社参以来、歴代将軍日光社参の休憩所に定めらたといいます
錫杖寺は天平十二年(740)行基による開山。元和八年(1622)二代将軍秀忠の日光社参以来、歴代将軍日光社参の休憩所に定めらたといいます
 0
0
3/19 16:09
錫杖寺は天平十二年(740)行基による開山。元和八年(1622)二代将軍秀忠の日光社参以来、歴代将軍日光社参の休憩所に定めらたといいます
 境内には幕末の大奥御年寄瀧山の墓があり、瀧山が使っていた駕籠が寄進されているそうです
境内には幕末の大奥御年寄瀧山の墓があり、瀧山が使っていた駕籠が寄進されているそうです
 0
0
3/19 16:13
境内には幕末の大奥御年寄瀧山の墓があり、瀧山が使っていた駕籠が寄進されているそうです
 錫杖寺から東へ旧街道へ向かう道筋に御成街道の石碑。ここに錫杖寺と御成道の説明板が立っています
錫杖寺から東へ旧街道へ向かう道筋に御成街道の石碑。ここに錫杖寺と御成道の説明板が立っています
 0
0
3/19 16:18
錫杖寺から東へ旧街道へ向かう道筋に御成街道の石碑。ここに錫杖寺と御成道の説明板が立っています
 旧街道を北へ。川口元郷駅まで進み、今日の旅を終えました
旧街道を北へ。川口元郷駅まで進み、今日の旅を終えました
 0
0
3/19 16:24
旧街道を北へ。川口元郷駅まで進み、今日の旅を終えました



 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手



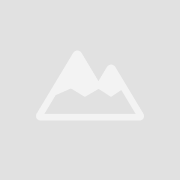










いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する