六郎山〜カロート山〜夏切山 ☆地図読み&縦走下見☆

- GPS
- 05:18
- 距離
- 9.5km
- 登り
- 968m
- 下り
- 952m
コースタイム
| 天候 | 曇り |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2016年06月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
写真
徳島県でも江戸時代、剣山周辺で木地師が活躍し、半田漆器(はんだしっき)の成立に影響をあたえた。しかし、明治時代以後、山での自由な活動が制限され、生活の場である山に植林が進むにつれて木地師も姿を消していった。
(徳島県立博物館HPより)
装備
| 個人装備 |
長袖シャツ
ズボン
靴下
グローブ
雨具
帽子
靴
ザック
ザックカバー
昼ご飯
行動食
飲料
地形図
コンパス
笛
計画書
ヘッドランプ
予備電池
GPS
ファーストエイドキット
保険証
携帯
時計
タオル
ツェルト
カメラ
熊鈴
|
|---|
感想
今回は継続して行っている地図読みトレーニング。
そして、秋の縦走に備えて六郎山〜カロート山〜夏切山を歩いてコースの下見を兼ねての登山です。
まずは六郎山の登山口を目指して自宅を3時過ぎに出発。
眠たい眼を擦りながらもあっけない位に今日は順調に登山口へと到着。
すぐに準備して登山開始です。
今日も1万分の1地形図を片手に実際の地形と見比べながら歩いていきます。
登山口の標高が730m位。そこから沢沿いに徐々に高度を上げながら標高900m位まで進んでいくと傾斜が緩やかな場所、木地師の辻というところへ到着。
ここからは谷に沿ってあがって行きます。
地形図と実際の地形をじっくりと見比べながら、自分は今どの辺りを登っているのか?コンパスと気圧計(高度計)で推測しながらですが、地図には記載のない小さな谷や尾根等を間違って認識することもあるので、ハッキリした地形がないかどうか周りを見渡しながら進んでいくとやがて沢の分岐点に到着。
それぞれの沢の方向と地形図が合致。高度計の数値とも合致。
これでほぼ間違いなく自分のいる位置は特定できたのですが、信用し過ぎも禁物なので継続して周りの地形を良く観察しながら登ります。
(これやっていると辛い登りも全然苦になりません。)
やがて標高1200m位で植生が植林から自然林へと変わり、残り50m程で稜線へとたどり着くので上を見上げると空も見えてきだして、まず自分の位置認識が間違いないことを確認。
稜線へと出ると、どこら辺の稜線へと出たのか確認・・・
確認・推測・確認・推測・・・ずっとこれの繰り返しですが飽きません。
六郎山へと到着してみると、この日は曇りですが眺望は良く、遠くの山並みが見渡せます。地図を出して山座同定をしてから次の峰、カロート山を目指します。
途中、痩せ尾根や岩場もあって慎重になりましたが無事に到着。
ここでも眺望を楽しみ、六郎山へと引き返して次の峰、夏切山を目指します。
稜線歩きをしながらも地形萌えで観察しながら歩くとあっという間に次の峰へと到着する感じがします。
夏切山に到着して四方の景色を楽しんでから下山開始。
六郎山方向へと戻る途中で尾根が分岐した地形があるのでコンパスあてて方向を確認して進んでいくと間違ってる!?何で???
元の場所へと登り返し確認するとコンパスあてた場所から見る左右の尾根の確度が10度位で非常に間違えやすい。けど、地形図を良く見たら左右どちらの尾根を降りるのかは分かるハズなんですが、自分を過信してしまい基本的な考えさえ思いつかず、集中力・観察力の欠如にやや自信喪失…
気を取り直して、今回は登山道ではない尾根を選んでおりていきますが、境界尾根なので境界杭にそって明瞭な踏み跡があり、登山道と言ってもいい位の道が下の方まで続いてました。
沢が近づいてくると道も伐採した杉の木で分からなくなったので後は適当に沢を目指して下降していき登山道へと復帰。
再び沢沿いに歩いて登山口へと戻ってきて朝練終了です。
今回も地図読みの面白さと奥深さを痛感した半日でした。
コメント
この記録に関連する登山ルート
この場所を通る登山ルートは、まだ登録されていません。
ルートを登録する
 shichi7
shichi7

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手







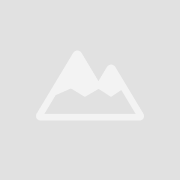







いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する