白馬岳

- GPS
- 08:40
- 距離
- 15.8km
- 登り
- 1,905m
- 下り
- 1,311m
コースタイム
白馬尻 07:10
葱平 09:05
白馬岳頂上宿舎 10:10-10:20
白馬山荘 10:35-10:40
白馬岳 10:55-11:10
三国境 11:30
小蓮華山 12:00-12:05
白馬大池 13:00-13:10
天狗原 14:10-14:15
栂池自然園 15:00
| 天候 | 終日見事なまでの快晴で、午前中は南アルプス全山や富士山までもが明瞭に眺められるほど空気も澄んでいました。 |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2009年09月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
電車 バス
ケーブルカー(ロープウェイ/リフト)
白馬駅 05:50-(松本電鉄バス)-06:17 猿倉バス停 (帰り) 自然園 15:08-(栂池ロープウェイ + 栂池ゴンドラリフト)-15:42 栂池高原 16:43-(松本電鉄バス)-17:11 白馬駅 |
| コース状況/ 危険箇所等 |
※登山行程が1日に収まっているため、1日行程として登録しましたが、前日に松本へ移動して前泊しているので、行程全体としては1泊2日となっています。 このルートは標準コースタイムの合計が11時間を超えているため、余程朝早くから登り始めない限り、1日で歩き切るのは困難です。通常は1泊2日で歩くルートだと思います。 白馬岳までの登りでは、雪渓を歩きますので、滑落や落石に対する注意が必要ですが、それ以外は問題なく歩けます。 白馬岳から先、小蓮華山を越えて白馬大池までは、爽快な稜線歩きが楽しめて、歩きにくい箇所もありません。 白馬大池と乗鞍岳の間も、岩がゴロゴロした中を登るようになりますが、傾斜がきつくない上に、滑りにくくて靴底のグリップが良く効く岩なので、特に問題とはならないでしょう。 ただし乗鞍岳から天狗原へは、岩の急斜面を延々と下る、かなり厳しい道になります。手を使わないと下れない箇所も多く、相当に神経を使うので気疲れします。 長い下りの間、途中で気を抜ける所も全くないので、長距離を歩いてきた末の下山路としては、一般的にはほかのルートを選択するほうが安全だと感じました。 ※デジカメを持ち歩くようになる以前のため、写真はありません。 |
感想
普通は1日で歩かないような長いルートですが、夜行の臨時快速「ムーンライト信州」と、それに接続する臨時バスを組み合わせて、早朝から歩き始めることで、なんとか1日で歩き切る計画としました。
ただし、せっかく遠出するのだから、当日の天気を直前までしっかり見極めて、確実に好天を狙って出掛けたいところです。そう考えると、全席指定の「ムーンライト信州」を何日も前から押さえたりする気にはなりませんでした。それに、寝台ではない普通の客車では移動中ろくに休めないという点でも、夜行での移動はあまり気が進みません。
そこで、前日のうちに松本まで入ってホテルで宿泊してゆっくり休み、「ムーンライト信州」には松本から先だけ乗ることにしました。これなら予め指定席を取っておかなくても大丈夫でしょう。
朝4時半に松本駅のホームに出て「ムーンライト信州」を待ちます。入線してきた夜行快速の車内を見ると、かなり空席が目立ったので、途中駅でかなり人を降ろしたか、または最初から満席ではなかったのかもしれません。
そして予想通り、松本では大半の人が下車して、車内の人の数も少なくなります。豊科や穂高でもそこそこの人が降りていき、さらに信濃大町では残っていた乗客の半数以上が降りて、白馬に着く頃には、同じ車両の乗客は数えるほどになっていました。
白馬駅からは、猿倉行きのバスに乗り継ぎます。バスは1台だけで、座席があらかた埋まるくらいの乗客数でした。
でも次の八方まで来ると、駅からの人数を上回る乗客が待っていました。周辺のホテルなどで宿泊していた人たちなのでしょう。すでにもう1台のバスが先着していましたが、座り切れない人たちがこちらの車両にも加わってきて、ほぼ完全な満席となって猿倉へと向かうことになりました。
猿倉に着くと、まだ早朝なのに周辺の駐車場はすでに満車に近く、猿倉荘の前も大勢の人で賑わっていました。歩き始めは林道歩きで、登山道に変わってからも緩やかな登りが続き、白馬尻までは特に息が上がることもなく到着です。
そして右手に雪渓を見ながら、夏道を登ること約30分で、登山道が雪渓の中に下りていく地点まで来ました。ここで初めての使用となる軽アイゼンを着用して、楽しみにしていた雪渓歩きが始まります。
事前には全くイメージが湧いていなかった軽アイゼンでの雪渓歩きですが、意外なほど普通に歩けると分かって安心しました。ストックによるサポートもほとんど必要ないくらいです。
歩くのに問題はありませんでしたが、さすがに雪の上、吹き下ろす風の冷たいこと。シャツの袖を長袖にしてもかなり涼しい思いをしたので、もし風が強かったりすれば、何か羽織る必要に迫られたでしょう。
そんな調子で40分ほど登った頃、登山コースは雪渓を外れて左岸の斜面に取り付き、ここで雪渓歩きは終わります。この時期すでに、大雪渓の上部では秋道を行く迂回路に切り替わっていて、雪渓歩きはそう長くは続かないのでした。
近くにいた人たちからは、「これじゃ大雪渓じゃなくて中雪渓だよ」と残念がる会話も聞こえてきます。しかし楽に歩けていたものの、滑らないように緊張もさせられたので、初めての雪渓歩きとしては、このくらいの長さがちょうど良かったのかもしれません。
雪渓を抜けた後、しばらくは急登が続き、やがて登山口からの標高差も1000mを越えていきます。空気も薄くなるためか、かなり疲労を感じるようになって、再三立ち止まって呼吸を整える必要がありました。
頂上宿舎が頭上に見えてから、そこに着くまでの間が、この日最もつらい登りだったでしょうか。なんとか頂上宿舎に着くと、その前からは八ヶ岳や南アルプスや富士山がクッキリと見えていて、頂上からの大展望にも一層の期待が高まります。
頂上宿舎前で少し休憩して疲労回復をはかりましたが、その後も白馬山荘までは辛い登りが続きます。さらに稜線に上がると冷たい風が吹いていて、涼しいを通り越して寒いくらいです。白馬山荘に着いた時点で、真っ先にウインドブレーカーを着用しました。
それでも白馬山荘の裏手に回ると、頭上には目指す頂上がいよいよその姿を現していて、もう残す距離もさほどのものでもありませんでした。
白馬岳の頂上に着くと、期待通りに、遮るものの全くない360度の大展望が広がりました。北アルプス全山は言うに及ばず、南アルプスまでの日本アルプス全山が見えています。東西にもスッキリとした眺めが広がり、北を見れば眼下には日本海という、あまりにも見事な大パノラマには、ただただ圧倒されるばかりでした。
ひとつだけ難があるとすれば、北からの風がうなる程の強さで吹き荒れており、それがまたひどく冷たいとあって、寒さに耐えて立っているのは5分がやっとです。次から次へと現れる人たちも、短い時間の滞在でどんどんと退散していきます。
でも山頂を僅かに南側に外れたところに、北風を避けられる向きの岩陰が見つかったので、そこでしばらく過ごしていくことにしました。風さえよけてしまえば、日差しがあって暖かいので、その場所だけは信じられない程に穏やかで居心地の良い空間です。しかもその位置からは、北アルプス核心部の山ひだの中に、ひときわ鮮やかなエメラルドグリーンの黒部湖が見えていました。
白馬岳からは、北へと伸びる稜線を進んでいきます。これから歩く尾根が遠くまでどこまでも見渡せていて、景色だけを見れば実に爽快な尾根歩きです。
しかし相変わらず快適さを阻んでいるのが北からの強風で、稜線上では真正面から襲いかかるようになっていました。人が煽られるまでの威力はありませんが、もしこれ以上に強まったりすればそれが危うくなりそうな程です。特に頂上付近から離れるまでは、かなりの脅威を感じつつの下り始めでした。
風さえ別にすれば、稜線上の登山道はいたって歩きやすく、ほどなく三国境に出ると、ここで雪倉岳・朝日岳方面への道を分けて右手の白馬大池方面へと進みます。
いくつかのコブを越えた後で、ひときわ顕著なピークにたどり着くと、そこが小蓮華山。一昨年、山頂が崩落して標高値が3mも低く訂正されたニュースはまだ記憶に新しいです。
岩屑が折り重なる山頂は現在も立入禁止で、頂上を踏むことはできませんでしたが、東側に少し下った登山道脇で北風に当たらない岩陰を見つけて、そこで少し足を休めていきます。
小蓮華山からの下りにかかると、北東へ伸びる稜線のその先に、白馬大池が初めて視界に入ってきます。ここからは、ほぼ常にその池を見ながらの下りとなりました。登山道は相変わらず歩きやすく、眺めも抜群の爽快な道。さらに風も収まって、過ごしやすくもなっています。
快適に下り続けて、白馬大池小屋やテントサイトのある、北側の池畔に出ました。小屋の前で休んでいる人が多いのに対して、小屋の裏手に回ると池のすぐ近くまで下りることができて、しかも人が少なくて静かでした。
白馬大池の水面の向こうには、これまで歩いてきた稜線がたおやかに続き、その先に小蓮華山という眺めが広がっています。まるで絵葉書からそのまま切り取ったような、ちょっと忘れがたい美しさでした。
白馬大池の先では、安山岩のゴロゴロした中に続く道を、ダラダラとかなり長い距離登り返します。
登り切った所から振り返ると、そこから白馬大池を見下ろす眺めがまた格別でした。そこには「乗鞍岳頂上」という標識が立てられていましたが、右手を見ればさらに高い場所があったので、厳密な頂上ではない模様でした。
乗鞍岳を越えて下りに変わっても、安山岩のゴロゴロした道はそのまま続きます。しかも傾斜が次第に急になっていき、手を使わないと下れない箇所が増えていきます。滑らない岩なので大きな危険を感じることはありませんが、岩ばかりが広く積み重なる斜面では、ルートがやや不明瞭な箇所も出てくるようになりました。
かなり神経を使わされる上に、下るにつれて傾斜も増すばかりで、だんだん精神的に疲れてきてしまいます。下を見れば、天狗原が遥か先に小さく見えて、この厳しい下りが際限なく続くように感じられて滅入ります。疲れても気を抜くことが許されない急降下なので、長距離を歩いてきた末の下山路としては、一般的にはほかのルートを選択するほうが安全だと感じました。
どうにか天狗原とほぼ同じレベルまで下り、いよいよ傾斜が平坦に近くなっても、それでも安山岩のゴロゴロ道が続くので、次第に泣きが入りそうになります。ようやく目の前に湿原と、その中に続く木道が現れた時は、もうホッとしたなどというものではありませんでした。
天狗原の湿原では草紅葉がかなり進んでいて、黄金色の彩りが深まろうとしている頃合い。草紅葉の見頃はもう少し先になるようです。
天狗原を後にして樹林帯に入ると、再び見るのもウンザリな安山岩がゴロゴロする道に逆戻りで、急な傾斜もまだ随所に残っていました。やっと普通の道になったのは、いい加減すぐ下に栂池自然園の建物が見えてきた頃です。
栂池ビジターセンターや栂池山荘、栂池ヒュッテが建ち並ぶ所まで来ると、そこからはもう観光客の領域でした。登山道もここで終わって、あとは舗装道路に変わります。
そしてロープウェイとリフトを乗り継いで栂池高原へ下ると、15:30発の南小谷駅行きの路線バスが出た直後でした。
当初の目論みではこれに乗るつもりだったのですが、最後に安山岩との格闘が長く続いて、想定よりもペースが大幅に落ちたため間に合わなかったのです。
そのバスであれば、9時過ぎには帰宅できるはずだったので、この僅かな時間差で帰宅時間が1時間半も遅れてしまうことになりました。
次の路線バスまで1時間ほどあったので、バス停近くの喫茶店で腹ごしらえをしつつ時間を潰していきます。店内からバス停の様子を窺っていると、長野駅行きの特急バスが来て、周囲にいた人たちをあらかた乗せて去っていきました。
この栂池-長野間の特急バスは全く視野に入っておらず、存在すら知らなかったのでしたが、実はこれに乗れば、9時半頃には帰宅することができたのでした。
でもそれは帰宅後に分かったこと。そのまま次に出る白馬駅行きのバスを待ち、大糸線の鈍行を2本乗り継ぎ、さらに最終の特急あずさに乗って、なんとか11時前に帰宅しました。
詳細な記録のページ
http://cellist.my.coocan.jp/yama/mt2009_07_09/mt2009_07_09.html#20090920

 cellist
cellist

 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大









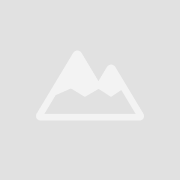







いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する