日本三百名山
信州百名山
甲信越百名山
東海の百山
日本の山岳標高1003山
長野県の山(分県登山ガイド)
信州ふるさと120山
日本の山1000
長野県の名峰百選
東海周辺週末の山登りベスト120
信州山歩き(中信・南信編)
ふるさと百名山
中央アルプス
南木曽岳(なぎそだけ) / 泣きびそ岳、金時山、揚籠山、額付山、中岐蘇岳、奈岐蘇岳
最終更新:ヤマレコ/YamaReco
アルプスを目指す足慣らしに最適な木曽の霊峰

南木曽岳は長野県の山で、中央アルプスの南西に位置しています。日本三百名山に選ばれるほか、御嶽山、木曽駒ヶ岳とともに「木曽の三岳」に数えられています。

標高は1679mですが登り応えがあり、本格的な登山が経験できる山として人気を得ています。

南木曽岳には、いくつもの別名が存在しています。雨が多いことから「泣きびそ岳」、額が付くほど急な登りから「額付山(ひたいつけやま)」などと呼ばれるほか、坂田金時の伝説にちなんで「金時山」とも称されています。伝説によれば、坂田金時はこの山の「金時の洞窟」で生まれ、生後間もなく「金時の産湯の池」で身を清められたと伝えられています。

また「揚籠山(あげろうやま、あげろやま)」の山名も持ち、これは中山道の宿場町である妻籠(つまご)や馬籠(まごめ)の上空にそびえるからとする説があります。さらに「中岐蘇岳」や「奈岐蘇岳」といった表記もあるようです。
古くは修行場の山

南木曽岳は古くは山岳修験の山でした。山頂に「南木曽嶽大神」を祀る石碑が佇んでいたり、摩利支天と呼ばれる仏教の神様に由来したピークがあります。

さらに、お地蔵様が登山者の無事を見守りながら、道行く人々に寄り添っています。
中央アルプスや御嶽山をよく望む

南木曽岳は花崗岩で構成されており、山頂部は巨岩が点在しています。

標高1677mの地点には「南木曽岳頂上」の石碑と二等三角点が設置されています。ここは木々に囲まれており、見晴らしはありません。

そこからやや北の、南木曽嶽大神のそばには大岩の展望台があり、御嶽山や乗鞍岳を悠々と望むことができます。

さらに稜線を進むと、笹原に赤い屋根が目立つ南木曽岳避難小屋を見下ろします。

周囲は開けており、ベンチのある展望台からは中央アルプスや北アルプスなどがよく見えます。

また摩利支天大神見晴台は、南木曽岳の山頂部や恵那山がよく見える場所です。
木曽五木が茂る山

山域は「木曽五木」の森が広がっており、五木とはヒノキ、アスナロ(ヒバ、アスヒ)、コウヤマキ、ネズコ(クロベ)、サワラの常緑針葉樹で、優れた建築材として古くから重宝されてきました。しかし、過度の伐採によって山が荒廃したため、江戸時代には厳しい伐採規制が敷かれ、森林の保護が進められました。
定番ルートは蘭からの時計回り

南木曽岳は急峻な箇所が多く、かつて修験僧が鍛錬していたのも頷けるほどです。
主なルートは2本で「蘭(あららぎ)ルート」と「上の原ルート」ですが、よく選ばれているのは蘭ルートです。ルートの名前は、登山口のある地名にちなんでいます。

木製の階段が長く続いたり、鎖場があったりと険しさを感じられるため、日本アルプス登山へ向けた練習登山もよく行われています。

このルートは途中で二手に分かれています。左手が登り専用、右手が下り専用の一方通行のため、時計回りに周回します。

「上の鎖場」は迂回して巻くこともできます。

登山口の近くの蘭美林自然探勝園は、ちょっとしたハイキングスポットです。登山後のクーリングダウンに立ち寄るハイカーも多くいるようです。
見どころは2つの夫婦滝で、2段で真っすぐに落ちる「男滝」と、滑るように水が流れる「女滝」があります。
| 登山口 |
蘭登山口 上の原登山口 |
|---|---|
| 周辺の山小屋 | 南木曽岳避難小屋 |
基本情報
| 標高 | 1679m |
|---|---|
| 場所 | 北緯35度35分32秒, 東経137度38分39秒 |
(あららぎルート)ハシゴが多い・トレーニングに最適
(上の原ルート)後半は、藪こぎ
(上の原ルート)後半は、藪こぎ
| 山頂 | |
|---|---|
| 展望ポイント | 山頂展望台・摩利支天 |
山の解説 - [出典:Wikipedia]
南木曽岳(なぎそだけ)は、木曽山脈(中央アルプス)南西部、長野県南木曽町にある標高1,679 m、長野県の「県自然環境保全地域」の指定を受けている山である。木曽山脈(中央アルプス)の主稜線から西に派生する尾根上にある。御嶽山、木曽駒ヶ岳とともに、木曽の三岳に数えられており、古くから信仰の山として修験者に登られていた。また、木曽地域で登山対象の山として、南木曽岳・風越山・糸瀬山の3山が、木曽三山と言われている。花崗岩質の岩山で、山頂付近では花崗岩の巨石が乱立し、鏡ヶ池と呼ばれる池があるが、樹木に覆われていて展望はない。三角点の北東100 m程の位置に、標高1,679 mの最高地点となる標高点があり、周辺の岩の上からは、御嶽山、北アルプス、中央アルプスなどの視界が良好な箇所かある。
別名が、「泣きびそ岳」、「金時山」、「揚籠山」(あげろやま)であり、『金時の産湯の池』伝説のある池がある。また金時が生まれたと伝えられる『金時の洞窟』がある。
付近の山
この場所に関連する本
この場所を通る登山ルート
この場所を通る登山ルートはまだ登録されていません。
おすすめルート
-
中級 日帰り 中央アルプス



 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月御嶽山・木曽駒ヶ岳とともに木曽三岳のひとつに数えられる南木曽岳。 登りは急できつい部分もありますが、山頂付近は別世界の様な自然庭園。巨岩と巨木の静かな山歩きを楽しみます。
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月御嶽山・木曽駒ヶ岳とともに木曽三岳のひとつに数えられる南木曽岳。 登りは急できつい部分もありますが、山頂付近は別世界の様な自然庭園。巨岩と巨木の静かな山歩きを楽しみます。




 南木曽岳の山行記録へ
南木曽岳の山行記録へ

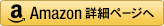









 Loading...
Loading...

