弘法小屋尾根〜間ノ岳〜農鳥岳〜広河内岳〜笹山

- GPS
- 54:52
- 距離
- 28.0km
- 登り
- 3,309m
- 下り
- 3,702m
コースタイム
- 山行
- 6:30
- 休憩
- 0:10
- 合計
- 6:40
- 山行
- 8:55
- 休憩
- 0:15
- 合計
- 9:10
- 山行
- 5:13
- 休憩
- 1:35
- 合計
- 6:48
| 天候 | 曇り時々晴れ |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2014年09月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
バス 自家用車
|
| コース状況/ 危険箇所等 |
弘法小屋尾根は踏跡も曖昧でマークも無い。 当然ながら地形図は必須(もう1人の方は昭文社の地図を見ていた!) ロープはあった方が安心かも(無ければ危険という事では無いと思う) 広河内岳〜笹山は一部踏跡が薄い。 白河内岳付近はやたら広い。 ケルンが沢山あるので目印になる。 |
写真
感想
かつて、koujouchou さんが辿った弘法小屋尾根。
這松の藪と格闘し、尾根にテントを張る。。。
う〜ん行って見たい、と暖めていたルート。
核心部は2935前後の岩稜帯
冬季踏破している伊那山仲間さんは、懸垂下降で下りている。
とりあえず補助ロープとスリングと金物を持っていく。
ちなみに1月に伊那山仲間さんとはニアミスをしている。
私が農鳥を越えれずに引き返すと間ノ岳からトレースがあったので、てっきり北岳からの往復かと思ったら伊那山仲間さんのトレースだったらしい。
いつものように出発に手間取って530バス出発10分前に到着すると、既にバスは満員。何とかお願いして載せてもらった。山梨交通さん、ごめんなさい。
駐車場発の3台も満車で、尚積み残しが50人ぐらいいた...
何という混雑ぶり。
野呂川発電所は私を含めて4名
2名の方は釣師で、北沢に行くと言っていた。
取り付き点までは工事道路があって、渡渉点は丸太がかかっていた。
ここで沈没してはまずいと思って靴を脱いだ。
釣師の方は丸太をすいすいと渡っていた。
暫く整備された道を行く。
1500過ぎて突然右にトラバースし始める。
尾根通しのはずだったので違うと思いながらとりあえずすぐ右の尾根まで行ってみる。
地形図を出して確認する。
しまった、高度計を初期化するのを忘れていた。
私の高度は1650を指している。
北沢と池山沢の合流に取水口がありそうだが、この道はその管理道路か。
2つの尾根は平行して似たようなもの。
右のほうが合流手前の傾斜がきびしそう。
なので戻って1855の尾根を上がる事にする。
鬱蒼とした森の中で、名前がわからないきのこがあちらこちらにあった。
三角点の少し手前で休んでいると、朝一緒だった方が抜いていった。
その後お会いしなかったので、さっさと登って行ったのだろう。
森林限界を超えると予定通り這松様がやってきた。
背丈を越える2mぐらいか。
幹も腕ぐらいの太さで、ちょっとやそっとではどいてくれない。
雪なら一回踏み固めればそのままだが、這松は1回踏んでも離すと直ぐに戻ってしまう。
なので、通過するまでずっと押さえ込んでおかねばならない。
お陰で、3日間、ずっと筋肉痛になってしまった。
12を過ぎて幕営できそうな地べたがある。きっと、koujouchou さんがテント出した所だろう。未だ時間的には早いが、格闘で疲れてしまった事と、この先とても出現んしそうも無い雰囲気だったのでテントを張る。
80cm幅の1人用が丁度入るスペースができて、のんびりする。
ガズがきれて間ノ岳が見えたり、北岳が見える。
景色を独り占めして、何という贅沢。
夜寒いと思ったら、氷点下になっていて、アウターには霜が付いていた。
もう、秋が近い。
朝日を眺めてからゆっくり撤収。
また、這松の中を行く。
2821を過ぎると問題の岩稜帯となる。
上から覗くと何とかなりそうなので、3点支持で確実に下りる。
下りが2箇所あるが、結局何も使用しなかった。
コルを過ぎて最後の登り。
右を巻いてガレを上がっても行けそうだったが、折角なので尾根通しに行ってみる。
最初の5mぐらいの岩が緊張した。
ホールドはしっかりしているのだが、ザックを背負っている事と、もし落ちれば怪我は必至なので緊張した。
間ノ岳の稜線に出る。
すごい、人が大勢歩いている!
登山道から離れた位置なので、合流する時に怒られないかちょっと心配になる。
間ノ岳頂上も人でごった返している。
こんな人口密度、初めてだ。
今回の3連休はとりわけ人が多そうだ。
さっさと通過して、農鳥小屋へ。
ここも人が多くて、小屋番さんも忙しそう。
深沢さんもヘルメット姿で歩き回っていた。
予定では水場に下りようかと思っていたが、気温が低い事もあって1.7ぐらい残っているので通過する事に。
冬にあきらめた西農鳥の登りを観察する。
確かに40度ぐらいの傾斜だろうか。
楽ではないが登れない傾斜でもなさそう。
当時視界が無く、ガスの間から見える登りは、まるで1枚の巨大な氷の壁に見えた。
まぁ、疲れとかいろいろあったので精神的に余力が無かったのだろう。
また改めて訪ねる時はあるだろうか。
農鳥岳を通過して、大門沢下降点を過ぎるとようやく静かな山になってきた。
広河内岳では1人、私と同じく南下するとの事。
しかし、時刻は14時で中途半端な時刻になってしまった。
とりあえず歩く。
今日は行けるところまで行って、明日は笹山東尾根を下る事にする。
東尾根の途中に水場があったのでそれまで水を持たせればよい。
15時を過ぎて東面に良さそうなテン場があったのでザックを降ろす。
甲府の街が見渡せるので、電波も掴みそうだ。
水が少ないので贅沢はできないが玉葱と卵と鍋キューブの雑炊が旨い。
最終日、今日は下りるだけだ。
白河内岳を過ぎて樹林帯に入ると、北上してきた方と出会う。
8年前も歩いているが、随分人が増えた、と話していた。
私もいつか山伏まで歩いてみたい。
笹山からひたすら下る。
藪漕のお陰ですっかり筋肉痛で下りが辛い。
水場標識から右にトラバースする。
所々テープがあって、それを目印に進む。
谷間に伏流から出たばっかりの水があった。
ありがたく遠慮せずに飲む。
水を得たので森でラーメンを作る。
小バエが纏わり付くので、ダメ元でたまたま持っていた蚊取り線香を炊いてみる。
すると不思議に小バエは居なくなってしまった。
ゆっくりコーヒーも入れて、また東尾根を下った。
朝の稜線は寒いくらいだったのに標高を下げた下界は蒸し暑かった。


 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手



























































































































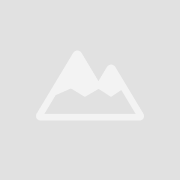









わ〜、きのこの写真が沢山!多くは毒キノコですけど
食べられるやつも、いくつか写っていますよ〜
このあたりって、きのこ好きには結構いいかもって思います。
が、急登すぎてきのこハントどころではありませんが。
きのこ先生、、、いやmikipomさん、
食べられるのもあったんですか!
判っていたら雑炊に一緒に入れて食べてみたかったです。
笹山東尾根もたくさん生えていましたね。
もう、撮る元気なかったです
遅コメになりすみません、、、
kiha58さんも、南アルプスじゃないですか
私が甲斐駒ヶ岳から眺めていた間ノ岳。
その裏側あたりで這松と戯れていたんですね〜
幕営地、いつも的確にいい所選んでますね。
這松とテントの一体化、って笑えました
見てましたよ〜ご主人と仲良く歩くところ(うそです
長衛山荘って駒仙小屋ですよね
私テント張った時は工事してました
定着も楽しそう
這松くん強烈です
私がどんだけあがいても奴は涼しい顔をしています
お陰で暫く筋肉痛でした
人が少ないのも納得です。。。(普通行かないか!)
3連休は南に行かれたんですね
ここ数年はこの界隈に行ってないので、是非行ってみたいです
写真もきれいですね
20 26番はこの辺では「じこぼう」と言ってめちゃめちゃ美味しいんですよ
18日 19日は連チャンで入笠に行ってじこぼう採りをしました
湯がいて冷凍庫に保存です
今日も天気いいのにお留守番
山がバッチリ見えてるのにテンション下がります
ええっ!
じこぼうだったんですか(が〜ん
食べたかったぁ--
もっと早く教えてくれればよかったのに(って無理か
実は生まれが北信の山に囲まれたど田舎で、ばあちゃんがじこぼの味噌汁作ってくれた記憶があるんですが、肝心なきのこが判らないんです(泣
もし、静かな山が好きなら、白峰南稜は天国かも
星空も朝焼けも独り占め。テン場で大きな声で歌ってもOKです
入笠山連荘ですね。(羨ましい
お留守番に快晴、ってお気の毒
いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する