快晴のテカリ→ヒジリ

 alpine3B
その他1人
alpine3B
その他1人 - GPS
- 25:15
- 距離
- 54.4km
- 登り
- 5,226m
- 下り
- 5,209m
コースタイム
- 山行
- 9:58
- 休憩
- 2:30
- 合計
- 12:28
- 山行
- 10:05
- 休憩
- 2:29
- 合計
- 12:34
| 天候 | 11/3 快晴 11/4 快晴強風 |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2023年11月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
自家用車
|
| コース状況/ 危険箇所等 |
遠山川側が切り立っているところは何カ所かあるが、普通にしてれば落ちない 水場は涸れ気味で、イザルガ岳手前の水場はなし、光岳小屋から標高80mほど下ったところに水場 茶臼小屋の水場はあったが夕方と朝で大分水量が違った 聖平は川に水が流れているところまで水平300mほど下った |
| その他周辺情報 | 飯田市街のほっ湯あっぷるなる施設で入浴 |
写真
感想
11月頭の3連休、なにやら季節外れの暖かさになるようで、奥美濃で泊まり沢でもするかな〜と思ったが、(よく同行者として登場する)長野県民氏が暇しているらしい。基本単独行マンもたまには誰かと山に登りたくなるもので、二人ともまだ行ったことのない光岳・聖岳を踏みに行くことにした。しかし計画段階で1泊2日の行程を組むと当然の午前3時だか4時出発で12時間以上の行動となり、貧弱な大阪府民の私は2泊3日に緩めるべきと主張するも、屈強な長野県民の彼に押し切られ1泊2日の行程となってしまった。一抹の不安を抱えつつ高速道路を飛ばして長野の集合場所へ向かったのだった。
野ウサギを2度ほど轢きそうになりながら長野県民氏の車で芝沢ゲートに着いたのは3時半。すでに多数の車が止まっていた。丑三つ時の林道を熊に怯えつつ進む。快調なペースで易老渡へ。こっからは易老岳まで850→2350といきなりバカみたいな登りで、しかもこの尾根ほとんど変化のない単調な登りなのである。重荷を背負っていることもあり、飛ばしすぎないようにと自戒しつつ登っていたつもりだがそれでも長野県民氏曰く出だしは相当早かったらしい。1450m付近の面平で完全に夜明けを迎え、紅葉の混じる見事な自然林の中を登っていく。4,50mごとに立ち小休憩、200mごとに大休止という感じでひたすら進む。2250mの三角点を越え、最後の登りをこなすとついに易老岳へ到着、易老渡から4時間であった。結局大分飛ばしとるやんけ!
ここにザックをデポ、サブザックで光岳に向かう。重荷を下ろしてまさに天にでも昇るような心地で鞍部へ下っていく。しかし光岳への沢筋の登りが始まると途端に亀の歩みになる。あとから思えばこれはシャリバテだったのだろう。それでも上にあるであろう水とピークを目指し歩み続け、傾斜が緩み始めると庭園のような草原となり、光岳手前の楽園へと躍り出た。再び軽い足取りとなり光岳小屋に到着、振り返ると大井川源流の深すぎる森と背後に存在感がでかすぎる富士山が現れた。普段活動のメインが近畿の人間としては富士山は「実はここから見えるんですよ!」みたいな看板が立ってても黄砂やらなんやらで全然見えんやんけ、という半ばイマジナリーマウンテンみたいになっていたので、実際に山から見えるのは新鮮な思いであった。とりあえずピークを踏みに行く、ピークは地味な感じだった。大井川側からのルートはまだはっきりとついているようだが、下があんなこと(林道が事実上廃道)になっている以上この道もいずれ消えるのだろう。
ピークからもどり光岳小屋で大休憩。水場はイザルガ分岐のところのは涸れているらしく、大井川側に標高差80ほどを降りないと無いらしい。しかしこの後茶臼小屋まで行かねばならぬ身としては補給しないわけにもいかず、渋々降りる。道はきっちりつけられており、これがホントの南アルプスの天然水ってね、と誰もが言いそうなことをいいながら満タンに補給した。あとは排便とシャリの補給と、実は睡眠時間が2時間くらいしかとれていなかったので少し横になって30分ほどの昼寝を取ったところだいぶ元気になり、易老岳へ引き返す。光岳小屋を目指す登山者は結構おり、確かに1泊2日でゆったり目指したり、あるいは日帰り前提で目指すにはいいとこなのかな、と思った。
易老岳から先は再び重荷での行動となり、膝、腿、ケツ、腰すべてにずっしりとダメージを受ける。さらにこの区間地形図ではなんとなくあるな程度にしか見えないアップダウンがかなり多く、そんでもって気まぐれに希望峰を目指して登り出したりするのでかなり堪えた。方々の体で希望峰に到着、太陽はもうすでに1時過ぎくらいから西日のようになってきており、3時ともなるとなんかもういつ引っ込んでもおかしくない感じである。仁田岳なぞ登る気も起きず本日最後の登り、茶臼岳へ急ぐ。ここの登りが個人的に一番きつかった。おそらくシャリバテ+最初の登りで飛ばした分のダメージなのだろうが、トラバース道でカットさせてくれよなどと半ばキレつつ登っていたような気がする。ようやく茶臼岳を踏み、広い稜線に下り、東側へ下り始めて茶臼小屋が見えてきた時には心底ほっとした。水場が涸れずに出ているのを確認してさらにほっとした。テントは他にも数張りあり、冬期小屋は結構賑わっていた。夕焼けの富士山を眺めながらテントを張り、今回も350×2担いできたどう考えても余計な荷物を消費しつつ、シャリバテの体に大量にソーセージ餃子麺を補給したのだった。夜中に一度起き出すと明るい月明かりの下、富士山がオリオン座を従えて闇夜の中に浮かび上がっていた。
2日目、3時前に起床。今日はシャリバテにならぬよう朝から炭水化物を摂取する。小屋周りの風は強風とまではいかないくらいで、空気の冷え込みもそこまでではなく快適に撤収することができた。
4時半ごろに稜線に出る。さすがに稜線上は遠山川側から風が強く吹き付けてくる。一度下ってから登り返しになるが、傾斜的にはそこまでしんどくはない。そこまで早くはないが継続して歩き続けられるペースを見つけられたようで着実に進んでいく。竹内門を越え上河内分岐手前でまだ暗い山腹を飛ぶ何か白いもの、どうやらライチョウらしい。冬期の白いライチョウの姿はまだ実物を見たことはなく、近くに寄ってきてくれないかなと思いつつ進むとグェーグェーと(求婚の?)声を上げながら一羽が10mくらいまで近寄ってきてくれた。飛び立った先の斜面を眺めると10羽くらいは戯れているような感じであり、朝からいいものを見られた。
さて日の出も近くなっており、上河内岳を避けて拝めるところまで急ぐ。鞍部につくとまだしばらく時間がある感じだったのでその上の2700ピークまで上り返しそこで日の出を迎えた。さすがに富士山のてっぺんから出てくる……という都合のいいことは起きなかったが、十二分に満足できるご来光だった。
ここから延々下って聖平へ向かう。どうせ登り返さないといけない標高なので気が重い。たどり着いた聖平で水を補給しようとするがこちらも光岳と同じで渇水気味で400mほど下らないと水が流れていなかった。再び水を満タンに蓄えて重荷での最後の登りへかかる。分岐にたどりつき、ああこれでもう重荷での登りはしなくていいんだという開放感に満たされた。
再びサブザックに切り替え聖岳を目指す。小聖岳への登りは樹林帯の中でかつ結構な急登であり、荷物を下ろしていても普通にしんどい。小聖にたどりつくと分岐から聖岳への標高差600mは残り6割ほどになっているのだが、その6割が圧倒的な存在感でそびえ立っている。そろそろ疲労が溜まってきている身には心を砕くに十分の光景、しかしこの好天で踏まねば何をしにきたかわからんので着実に登っていく。別に全然難しいわけではないので、小聖から登り続けること50分、ついに視界が開けて聖岳に到着した。さすがに展望は格別で南アルプスの名だたる峰々、遠くには中央アルプスも千畳敷カールがはっきりわかるくらいに浮かんでいた。ついでなので奥聖岳を踏みにいく。長野県民氏が絶好調で跳ねるように向かっていったが、ついて行こうとすると一瞬で今まで耐えていた心臓がへばる。ああ、そういえば自分の低酸素限界は2700mだと勝手に思っていたが、それはあくまで思うとおりのペースで動こうとした場合であってゆっくりペースなら3000くらいは耐えられるんだな?という新たな知見を得た。下りは大展望のなかザレ場をサクサク下っていく。行きはあれだけ息も絶え絶え登った斜面も半分の時間で強風と展望を楽しみながら降りることができた。
分岐で再度重荷となり、ここからは遠山川への激下りである。いや激下りといってもそこまで急なわけでもないが、こちらも易老岳への登りよろしくひたすら同じような下りが続くのである。最初は重荷のせいで思うほどスピードが出ずまた心が折れそうになったが、適応したのかやけくそなのか徐々にペースをあげていく。足はもうヨレヨレなので標高差200〜300くらいで座っての休憩を入れつつ進んでいく。そこまで急でないとは言ったがそれでも足を滑らせ滑落すれば止まれなさそうな沢筋へ落ちうるところとかもあり慎重さを持ちつつ下っていく。最後にはついに稜線を外れ、廃屋の前を通って西沢の徒渉地点へ到達した。聖岳分岐から2時間20分の格闘だった。この下りで私の足の親指は完全にへたってしまった。同行者は尾根の下半分から便意に襲われており、下り終了の喜びもそこそこに便が島に急ぐ。たどり着いた便が島は聖光小屋も営業しておりトイレも立派なのがあった。同行者はこの小屋を神と崇め、芝沢ゲートで飲むんだと話していたコーラをここで購入していた。ちなみに小屋のおじさんにこの行程を話すと「なかなかの強行軍だね〜ハハハ」とのことでした。
こっからは長い林道歩き、同行者と駄弁りながら易老渡を過ぎ、なんとか岩を過ぎ、林道崩壊地点を過ぎ、特に何も考えずに歩いていたらいつの間にやら芝沢ゲートに到着、これにて2日間、水平距離54km、累積標高5200mのハード山行は終わった。下山後ほっ湯あっぷるなる温泉で汗を流し、焼き肉の街らしい飯田でひさびさの贅沢夕食に舌鼓を打ったのだった。
☆光岳、おそらくそのアクセスの悪さから二度と行かない100名山にあげられたりするとこという印象だった。実際景色が無い状態ならその評価になるのもやむなしだろうが、今回の天気であればまた来たくなるとこであった。
聖岳はうんその、しんどかったです。素晴らしかったけどね。
ところで1泊2日で椹島→赤石→百間洞→ウサギ→聖→赤石ダム→椹島と回るというおじさんとすれ違ったが、そちらのルートもなかなかですね……


 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大 拍手
拍手














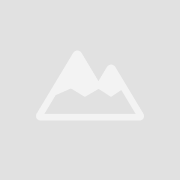








いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する