白根三山縦走、広河原〜白根御池〜北岳、間ノ岳、農鳥岳〜大門沢〜奈良田【山梨県、南アルプス】

- GPS
- 17:01
- 距離
- 26.7km
- 登り
- 2,796m
- 下り
- 3,483m
コースタイム
- 山行
- 4:47
- 休憩
- 2:25
- 合計
- 7:12
- 山行
- 8:25
- 休憩
- 1:22
- 合計
- 9:47
10/11
広河原648 ― 広河原山荘652 ― 大樺沢白根御池分岐707 ― 第一ベンチ731/734
― 第二ベンチ755/0805 ― 白根御池小屋840/910 ― 小休止940/944
― 大樺沢二俣からの道と合流1032 ― 小太郎山分岐1047/1110 ― 北岳肩の小屋1133/昼食/1218
― 両俣小屋への道の分岐1234 ― 北岳1251/1323 ― 吊尾根分岐1332
― 北岳山荘1402(泊)
10/12
北岳山荘/朝食/455 ― 中白根522/529 ― 次のピーク543/日の出/552 ― 間ノ岳612/622
― 三国平への分岐658 ― 農鳥小屋706/725 ― 西農鳥岳759/810 ― 農鳥岳838/859
― 大門沢下降点921/927 ― 新道旧道分岐標示941 ―「標高2,650M」945 ― 「標高2,450M」1005
― 「標高2,370M」1014 ― 木橋1020 ― 「標高2,200M」1034 ― 水場1051 ― 木橋2 1058
ー 「標高1,945M」1100 ― 木橋3 1104 ― 大門沢小屋 1121/昼食/1157 ― 木橋4 1201 ― 木橋5
― 八丁坂下の木橋 1309 ― 取水口の吊橋1327 ― 堰堤工事中の場所(本来の吊橋2)1336/1554
― 吊り橋3 1358 ― 工事道路からの登山口1402 ― 第一発電所1426 ― 奈良田駐車場1441
○行動時間
第一日 10/11 7:14
第二日 10/12 9:46
| 天候 | 晴れ |
|---|---|
| 過去天気図(気象庁) | 2014年10月の天気図 |
| アクセス |
利用交通機関:
バス 自家用車
10/10:会社=<自家用車>= 10/11:=奈良田=<バス>= 広河原―白根御池―北岳―北岳山荘(泊) 10/12:北岳山荘―間ノ岳―農鳥岳―大門沢―奈良田=<自家用車>=(奈良田温泉)=家 ●登山口へのアクセス ○奈良田 ・写真1にイメージマップを付けたので、参照されたい ・身延からの県道37号線をじっと進むと、自家用車で入ることのできる最後の集落が奈良田 ・駐車場(写真1では�)は、奈良田集落の手前側、身延からのバスの終点付近に約40台分が、また、奈良田集落を通り越してから、100台以上は入る広い駐車場(写真1では�)がある ・身延駅からのバスで約1時間30分、1,000円。一日わずか4便。バス停は写真1の� ・広河原へのバスは、写真1の�始発で�を経由して進む。他客時には�始発の増発便あり。今回も増発便があったため、バス停Aからでも、座っていくことができた ・山梨交通のバス停名称では、バス停Aが「奈良田駐車場」、バス停Bが「奈良田」 ○広河原 ・広河原へは、甲府・芦安、奈良田、北沢峠からのバスで行くことができる ・甲府駅からのバスで2時間弱。2,050円。奈良田からのバスで45分、1,130円。いずれの料金にも「利用者協力金」100円が含まれている ・広河原のバスターミナルからは、更に上流側に進み、野呂川にかかる大きな吊り橋を渡れば広河原山荘があり、そこからが北岳への登山道 |
| コース状況/ 危険箇所等 |
○コース状況 (1)広河原〜白根御池〜北岳〜北岳山荘 ・全般にマークや表示は整備されている。迷うことはなさそう ・特段の難所はないが、白根御池への登りや、白根御池からの草すべりのような急坂が長い。広河原から白根御池までの間にはベンチの設置箇所もある。いっぽう草すべりにはそれはない ・小太郎山分岐から先は、ずっと絶景ポイント ・肩の小屋から北岳へは、岩ゴロの登り。北岳は二つの顕著なピークを持つが、ルートは北ピークを通らず、最高点でもある南ピークにまっすぐに登っていく。途中の北ピークにも登ることはできる (2)北岳山荘〜間ノ岳〜農鳥岳〜大門沢下降点 ・山頂標識や途中の方向標示が多く設置されている ・間ノ岳から農鳥小屋の間では、石にペイントされたマークがある。また農鳥小屋から農鳥岳へは同様にペイントマーキングと“ノウトリ”と書かれた文字が時折見受けられる ・農鳥岳を過ぎるとさらに人も減り、ルート上のマーキング以外はあまり標示がない。大門沢下降点には慰霊碑を兼ねた鐘も設置されており、見失う心配は少ない (3)大門沢下降点〜大門沢小屋〜第一変電所〜奈良田 ・いっぺんに2,000Mを下降するルートだけあって、時間もかかるし疲れやすい ・早川町が付けた小さな標示以外には、殆ど標示はない ・早川町の標示は、大門沢小屋よりも上流側では標高が記入されており、位置の目安になる。しかし、それより下流側では札が貼ってあるだけで標高等は記入されていない ・ただし、コース全般に、リボンやペイントが多数設置されており、これを頼りにすればまず道を間違う心配はない。逆に言うと、印の見えない状態が長く続くことは道間違いをしている可能性が高いことになる ・上流からの景色の推移は、灌木が目立ち始めたら2,700M付近、小岩を敷き詰めた歩きにくい道になったら2,500M付近、大門沢の最上流部が見えたら2,110M付近、小屋1,800M付近など ・小屋よりも下流側では沢沿いがもっぱらだと思いがちだが、2度の沢渡りから下流側では、八丁坂に至るまで、ずいぶん沢から離れる。沢音すらしなくなる ・H26.10現在、二番目の吊り橋(上流からでも下流からでも)が撤去されて斜面防災工事が行われている。その部分では河原を歩き、仮設の橋梁を渡ることになるので、大雨時にはたいへんかも知れない |
| その他周辺情報 | ○買う、食べる ・奈良田に前夜あるいは当日朝に入るならば、買い物は奈良田に行く前に。国道52号線「上沢」交差点よりも手前(甲府側であれ静岡側であれ)にはコンビニがある。ここまで来ると、水や補給食の買い物はできない ・当然ながら、国道沿いにはコンビニも飲食店も多数ある ・奈良田や早川町内にもいくつかの飲食処があるが、終了時間が早いため注意を要する ○日帰り温泉 ・帰途、「奈良田の里」に立ち寄った。趣ある建物。小さな温泉。雰囲気がとてもよい ・そこ以外にも、早川町内の県道37号線付近には「湯島の湯」「すず里の湯」「ヘルシー美里」などいくつかの日帰り温泉がある |
写真
装備
| 個人装備 |
長袖シャツ
Tシャツ
ズボン
靴下
グローブ
防寒着
雨具
日よけ帽子
着替え
靴
予備靴ひも
ザック
ザックカバー
昼ご飯
行動食
非常食
飲料
ガスカートリッジ
コンロ
コッヘル
ライター
地図(地形図)
コンパス
計画書
ヘッドランプ
予備電池
GPS
筆記用具
ファーストエイドキット
常備薬
日焼け止め
保険証
携帯
時計
ナイフ
カメラ
|
|---|
感想
10/10(金)
13日以降接近が予想されている台風のせいか、天気予報が不安定だったが、最後の“晴れ”を信じて山行きを決定。
久しぶりに、マイカーを走らせて南アルプスへと向かうことに。会社から徒歩15分ほどの安いパーキングに駐めておいたマイカーで、大阪を18:45に出発。途中、高速道路に入ってからの浜松SAで夕食を摂り、身延のコンビニで最後の買い物をした後に、奈良田には午前1時過ぎに到着。
特に気になることもなかったのだが、あまり寝付けないままに、起床時刻。
10/11(土)
朝一番のバスには、「奈良田駐車場」バス停から乗車。このバス亭始発となるバスが一台は増発されているようなので、座れる可能性は高い。と思ったら、早くから行列ができており、列のずいぶん後方に並ぶ。なんとか最後の一席に座るも、バスは立ち席で超満員。
広河原には15分以上の遅れで到着。インフォーメーションセンターの2階で登山届けを提出し、身支度を検め、出発。
ちょうど時間の重なった芦安からのバスのためか、広河原山荘から先は既に渋滞。遠慮気味に、少しずつ追い越していく。しかし、分岐から白根御池コースを選ぶと、とたんに人が減った。
尾根筋の登りを続けるこのコースは見通しが利かない。加えてこの季節では草花も限られており、鑑賞するものにも事欠く。
修行のように黙々と登り、やがて登山道がきっぱりと方向転換、水平道を暫く進むと白根御池小屋に到着する。ここまで来ると、対岸の鳳凰三山が、一幅の絵のように堂々と聳えているのが見える。
きれいな水洗トイレをお借りし、この先に向けて備え。
間食したりしながらゆっくりと時間を過ぎし、改めて出発。
草すべりは草付きの急崖につけられたジグザグの急登。同様の歩みの方々それぞれが、息を切らしつつ、じっくりと歩を進めている。大樺沢からの道と合流するはずだが、と思いつつ進むも、なかなか合流点に至らない。最後まで続く急登の途中で、同じく急登で接近していたその道とようやく合流、まだ登ってようやく小太郎山への分岐点となった。
ここは、本日最初の絶景ポイント。富士山も静かに美しく聳えている。
甲斐駒ヶ岳はその白く美しい山頂部を誇っている。
鳳凰三山も実はそんなに白かったのかという山頂部を伸びやかに広げ、こちらに向かい合っている。
灌木帯も去り、開放的になった尾根筋の道をゆっくりと肩の小屋目指し登る。やがて、猫の額ほどの広がりに立つ肩の小屋に到着。ここで昼食にする。
ここも絶景であり、見渡していると、食べるのを忘れそうになる。
肩の小屋からの最後の登りは、岩ゴロの道。山頂と思って巻きながら登り詰めると、まずたどりつくのは北ピークであり、もう少し先にある真の山頂もようやく姿を現す。そこからは、山頂で楽しむ人たちを見ながら、それに惹かれるように登り切る。
山頂はまさに360度の絶景。この天候に感謝。先ほどまでは見えていなかった、間ノ岳、農鳥岳や、塩見岳から先にある南アルプス中南部の山々も姿を現す。
西には中央アルプス、やや北には穂高が辛うじて見えている。もちろん御嶽の噴煙も見えている。こちらには思わず手を合わせる。
富士山も遮るものなく見える。「日本一高いところから見る富士山だよ」と同行者に説明しているオジサンのおかげで気がついたが、確かにそうである。富士山に次ぐ第二の高峰なんだから。
北岳山頂から北面を下降し、北岳山荘へ向かう。なかなか手強い岩ゴロ斜面で、ジグザグを切りながら下降。やがて、吊り尾根からの道との合流点。吊り尾根からの登り道を上から覗いてみると、更に厳しい急斜面に見える。
そこを過ごし、あとは比較的緩やかな尾根道を山荘へ。14時過ぎの到着はやや早いが、昨晩寝ていないことを考えるとこれでいいだろうと割り切り。
夜は一つの布団を一人で使えるありがたい環境。
食事のあと、夕焼けを見に出てみると、北岳が真っ赤に染まっている。これまた美しい。でも、とても寒い。すぐに引っ込み、布団の中へ。翌朝までとてもよく寝られた。
○10/12(日)
この日も、好天を覗わせる夜明け前の空模様。いくつかの星座がはっきりと見えるが、同時に月が明るすぎるため、あまり星の数は多くないように感じる。
5時に始まる山荘の朝食では遅すぎると思い、お弁当をもらって山荘で済ます。それでも既に4:55、奈良田で温泉に入れるのか不安な時間になる。
しばらくは本来ヘッドランプの明かりで進むところだが、月明かりがあまりにも明るく、開放的な石砂地でもない限りは、月明かりで進むことができるくらい。
中白根が近づき、東の空が明らみ出す。中白根で日の出を待つか考えるが、それも惜しんで先へ。しばらくは西面を巻くので日が出てしまったのかがわからない。ともかくも次のピークへと急ぐ。
次のピークに到着とともに、一段高いところにいた一群から、「出た!」と歓声が上がる。急いでそちらを見ると、まさに日の出の瞬間。丹沢の辺りからの日の出。何枚もシャッターを切る。
そこからは、緩く登り続けて間ノ岳へ。山頂部は、昨日の北岳と同様に360度の大展望。
今日は、低い雲海に包まれており、山々の殆どがその上にぽっかりと浮かんでいる。それだけに、なおさら神秘的。残念ながら穂高・槍よりも北方は雲の中、関東北部も見えていないが、それ以外の山々は殆ど同定できる状態。ここから見る北岳は堂々とした山容。標高では日本第二位だが、それを越える威厳を感じさせる。
せっかくの絶景大展望だが、先も気になるので、進む。間ノ岳の山頂南端から農鶏小屋を見下ろすと、ずいぶん下に見える。それはそうで、約400mもの一気の下りである。しかも、400mの下降が全て見渡せるような、のっぺりとした斜面。そこをジグザグに下っていく、途中からは、大井川の源流となる農鳥沢が顕著になり、やがて三国平への分岐を過ごし、農鳥小屋へ。
何かと有名な小屋番氏がちょうどいらっしゃったので挨拶をするも、残念ながら特に反応はなかった。小屋の先の広がりで休憩し、再びの登りに備える。
西農鳥岳へは、岩ゴロの道を急登する。まずピークのような場所に着くが、そこは単なる転換点。西農鳥岳はもう少し先。頂上を見ながら進む。やがて山頂。そこから見ると、間ノ岳の大きさがよく分かる。丸っこい両肩、なだらかに長い手前の稜線。容量の大きな山だ。
西農鳥には、特殊東海製紙の建てた山名標が建っている。荒川岳など南アルプス南部ではおなじみのもの。確かに、間ノ岳よりも南下すると、西面は静岡県、大井川水系である。
西農鳥岳からは、岩くず帯を二度三度と昇降してようやく農鳥岳。山頂が狭く平べったい山。ただし、踏み跡のある範囲は限定されている。
とりわけ大きく見える塩見岳を筆頭に南アルプス南部の山々がよく見える。ただし聖岳は荒川中岳の後に隠れてしまっている。
後続の方の到着を待って、いよいよ長い長い下降に着手。
岩くずの緩斜面を淡々と降りると登りの方とすれ違い。今から山頂まで行って戻るらしいが、山頂とはどれなんだろう。
慰霊碑を兼ねた鐘が建つ下降点には意外に早く到着。そこからは急下降。時折、紅葉の美しい谷底が見えるが、そこに降り立つまでにも標高差700mくらいはあると思うとぞっとする。高度に応じて斜面の様相も次々と変わる。灌木が増え、やがて樹林帯、小岩だらけの膝に応える斜面、根張りのよい斜面と移ろい、ようやくさっき上から見た急渓谷に降り立った。
そこからも、容赦ない急斜面の下りはしばらく続き、ようやく解放されたと思ったら大門沢小屋に着いた。
古めかしいその小屋の前で昼食を摂る。昼食は北岳山荘のお弁当。朝バージョンとはご飯だけが違っている。昼用は白米ではなく、ちらし寿司になっている。
元気のある女性二人連れや、単独行の男性数人の会話を聞いていると、女性二人は京都、男性のうち一人は大阪から来ているようだ。関西からこのコースへは来にくいだろうと思っていたが、男性は当方と同様に車、女性はなんと公共交通機関でやって来たらしい。明日の台風を考えて、小屋泊まりではなく、下まで降りるそうだ。
そんな方々が降りてから、追うように下降開始。先ほどまでと変わらないくらいの所要時間の見込みであるため気も重い。
しかし、意外な速さで八丁坂が現れる。どうやら予定よりは早く降り着けそうだ。
やがて、大きな人工構造物、取水設備とともに、最初の吊り橋が現れ、山旅の終わりが近づいてきた。工事中で姿のない第二の吊り橋の先で最後の休憩。堰堤の上に寝転ぶと気分もよく、思わずうとうとしてしまう。
その先第三の吊り橋を渡ると、工事道路に吸収されてしまう。25分程度下ると行きのバスから見た変電所に到着。最後はバス道をとぼとぼ歩いて駐車場に到着。
“白根三山”とは言うが、一口では語れないほどに個性豊かなそれぞれの山に魅了された山行きであった。


 標高グラフを拡大
標高グラフを拡大
 拍手
拍手
























































































































































































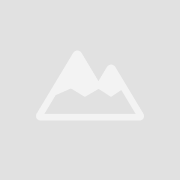






いいねした人
コメントを書く
ヤマレコにユーザー登録いただき、ログインしていただくことによって、コメントが書けるようになります。ヤマレコにユーザ登録する